環が風邪を引いた。それも結構重い風邪。
「環さん……どうですか?」
ベッドに深々と潜り込み、酷く咳き込む環に深知留が声を掛ける。
ここは龍菱家本邸の別棟――所謂離れという場所の一室。
「…………」
環から返事は返ってこない。
代わりに、熱で潤んだ双眸が深知留に向けられる。
「熱、下がりませんね」
深知留はベッド縁に腰掛け、環の額に自分の掌を当てる。
すると、
「来ちゃ駄目だって言ったろう……」
環は嗄れた声でそう言うと、深知留の手を掴んで自分の額から離す。そうする彼の手は怖いほどに熱い。
「だって、心配ですもの」
「俺は大丈夫だから、何のためにここにいると思ってる」
「大丈夫ですって」
深知留が答えれば、詰るように彼女を見つめる。
そう、環は風邪を引き込んでから先、自ら家庭内引っ越しをした。同室で過ごす深知留に染すまいと気遣って。それも、龍菱家の広さがあるからこそできる荒技。
しかし、当の深知留はどんなに駄目だと言っても、心配だからと暇さえあればここに入り浸っている。
環にすれば、それが嬉しいと言えば嬉しいのだが、自分の気遣いがまるで意味がないことに複雑でもある。
「もういいから、こんなところにいないで義姉さんとでも出かけておいで。
最後まで言えず、環はゲホゲホと咳き込む。
深知留はその背を優しくさすってやる。
(嫌ですよ。こんな環さん置いて、出かけられませんよ……)
深知留はふと、先ほど誘いに来た鈴のことを思い出す。
『感染源は他に任せて、遊びに行きましょう?』
彼女は開口一番そう言った。
あまりにストレートな物言いに深知留が驚いているうち、鈴は更に言った。
『心配しなくても、環さんの面倒を見てくれる人はたくさんいるから大丈夫よ。それに……一緒にいて深知留ちゃんに染ったら困るわよね? 環さん?』
それは……そう、まるで脅迫のような言葉。
環はそれに促されるよう、出かけてこいと深知留に言った。
だが、深知留は断った。もちろん丁重に。
大体、彼女の性格からして、環を置いて遊びにいけるわけがないのだ。
そのまましばらく環のそばにいれば、
「深知留……もういいから……」
再び環は深知留を遠ざけようとする。
が、
「もう今更、遅いです。感染するなら既にしてますよ」
深知留も引き下がらない。
環はもう諦めた、とでもいうかのようにふうっと一つ息を吐いた。
「ねぇ、環さんおでこ冷やしましょうか? 早く熱が下がるように」
深知留の問いに環は首を横に振る。
よく見れば、環は小刻みに震えていた。
「寒いですか?」
尋ねれば、彼は静かに首肯する。
すると深知留は「ちょっと待っててくださいね」と言って部屋を忙しそうに出て行った。
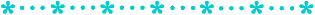
環がふと気が付くと、目の前に柔らかく微笑む深知留がいた。
どうやらウトウトしていたようだ。
「いいですよ、そのまま寝てて。もう少しで温かくなるから待っててくださいね」
「…………」
「今ね、湯たんぽお願いしてきました。毛布やお布団重ねても重いでしょ? 暖房強くするのも体にあまり良くないから、湯たんぽがないか探しに行ってきたんです」
深知留はフフッと笑って見せた。
「……ありがとう……」
環は素直に礼を述べたが、寒さは変わらず震えるせいで歯がカタカタと鳴る。
「……もうすぐ。もうすぐですからね」
深知留は少し表情を強ばらせ、環の髪を優しく撫でる。
しかし、環の震えが収まらない。
すると深知留は……
「環さん、ちょっとごめんなさい」
そんな断りとほぼ同時に、環の横たわるベッドへ潜り込んだのだ。
「み……ちる……?」
驚く環を余所に、深知留は環の隣に寝て彼をその胸に抱きしめるようにした。
「湯たんぽができるまで、わたしで我慢してください」
「でも、深知留……」
「染るから出てけ、なんて言わないでくださいね。人間湯たんぽ、結構温かいんですよ。昔ね、風邪引いてどうしようもなく寒い時、母がこうして一緒に寝てくれたことがあったんです」
そう言って柔らかく微笑んだ深知留に、環ももはや参ったとばかりに微笑み返した。
そして、彼は恋人の柔らかさに自らの身を任せることにした。いつもは抱いて眠る体に、こうして抱かれて眠るのも悪くない、と。
それから数分も経たないうちに、環は静かに寝息を立て始めた。その頃には震えもすっかり止んでいた。
そんな環の穏やかな寝顔を見ながら、深知留は彼の頭をゆっくりと撫でる。
「早く良くなってくださいね……」
小さく小さく独り言ちながら。
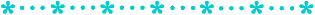
それからしばらくして、部屋のドアがノックされた。
部屋の外、ノックするのは鈴である。深知留が頼んだ湯たんぽをメイドから引き受けてやってきたのだ。
しかし、どんなに待っても室内から返事はない。
「深知留ちゃん、湯たんぽできたわよ? いないの?」
鈴は再びノックをする。
が、やはり返事はない。
何だか嫌な予感がして、
「どうしたの? 入るわよ?」
鈴はそのまま部屋に入った。
すると、
彼女の目に入ったのは……――
「あら……」
鈴は思わず安堵の溜息を吐いた。
ゲスト用の部屋の中央、鎮座する少し大きめのベッドの上――そこには、寄り添って寝息を立てる環と深知留の姿があった。
その時だった。
「……どうかしたのか?」
神妙な面持ちで、ドア口に立つのは雅だった。
弟の様子を見に来たら、ドアは半開きで中には鈴が立ちつくし……雅は一瞬得も言われぬ焦りを感じたのだ。
すると、鈴が柔らかい表情で振り返り、静かに、とでも言うかのように口元に人差し指を立てた。
意味も分からず雅が鈴の傍まで近寄れば、鈴は口元の指をそのままベッドの方へと向ける。
「返事がないから驚いて入ってみれば……本物が待てなくて、深知留ちゃんが湯たんぽになっちゃったみたい」
鈴はフフッと笑うと、雅もつられる様に硬い表情を綻ばせる。
「本当だ。これじゃあ、わざわざ部屋を移す必要もなかったな」
「そうね。……これも要らないみたいだしね。今夜は少し気温が下がるみたいだから、うちのベッドにでも入れておこうかしら」
すると、雅は「うちも要らないよ」と言った。
「え? 温かくていいじゃない」
鈴がそう言えば、雅は徐に鈴を背から抱きしめる。
そして、
「だって、俺だって湯たんぽ持ってるからね」
雅は鈴の耳元でそっと囁く。
鈴は「もぉ……」と言葉を漏らしたが、その表情はもちろん嬉しそうである。
そのまま二人は「おやすみ」と小さく言い残して、部屋を後にした。弟たちが良い夢を見られる様祈って。
この数日後、深知留が風邪を引き込んで家庭内引っ越しをしたのは、言わずもがな。それでも環がそこに入り浸ったのは、更に言わずもがな……。
