春の爽やかな風が頬を撫でる頃、
今日は鈴のお見合いの日だ。
もう何度目になるのか分からないお見合い……
遅れると連絡のあった先方を待つために、鈴はここで時間を潰していた。
そんな鈴の気持ちを支配するのは相手に対する期待でも不安でもない。
ただ、諦めだけ……
今日の相手はかの有名な菱屋グループの長男である、
お見合いをする前に他にも色々と情報を与えられたが、鈴は最低限しか記憶に留めていない。
だって、鈴は分かっていたから。
このお見合いも駄目になる、ということを。
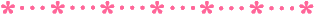
十五の夏――あの時から鈴の人生は一変した。
鈴の家、吉乃宮家は由緒正しき家柄であり、時代が時代なら華族と呼ばれる程の家だった。
その吉乃宮家の資産に目を付けた不当な輩が学校帰りの鈴を誘拐したのだ。
欲に目のくらんだ男達に拉致監禁され、果ては乱暴され掛けたが、警察の捜査により鈴は幸いにも未遂の状態で保護された。
しかし、その凄まじい体験は鈴の心に大きな傷を与えた。
精神的な負担からか、鈴にはその時の記憶がほとんど無い。
記憶が消えてしまったなら、それはそれで良かった。覚えていて良いことはないし、忘れてしまえるのならそれに越したことは無かったから。
しかし、それからすぐに、その心の傷は男性恐怖症という形で表に現れた。
男性が傍に近寄るだけで記憶が断片的に引き戻され、鈴はパニックを起こすようになったのだ。
両親も兄弟も友達も……最初はそんな鈴を優しく支えてくれた。「そのうちきっと良くなるよ」と言って。
だが、鈴の抱えた心の傷は深く、その症状が軽減することはあっても消えることはなかった。
事件の前から仲の良かった友達は、やがて鈴の傍から一人二人と順々に離れていった。事件の後にできた友達も、鈴の事情を知ると少しずつ距離を置いて離れていった。
高校に上がって、できた友達は……
「ごめん……本当にごめん……鈴の気持ちは分かるんだけど、わたし、これ以上支えてあげられないんだ。だから、ごめんね……」
鈴の事情を知っても『鈴の一番の友達だよ』と言っていたはずの彼女は、鈴がパニックを起こした姿を初めて見た後、そんな言葉を残してすぐに去っていった。
まるで火事場の火の粉を避けるかのように。
でも、鈴は彼女を恨んだりはしなかったし、傷つきもしなかった。
そんなのは良くあることで、仕方のないことだから。
だって……鈴自身でさえ、自分を持て余していたのだから、他人が支えられるわけがないと思っていたのだ。
そして、そもそも鈴は期待もしていない。
最初は、鈴だって一生懸命支えようとしてくれる友達に期待をし、頼ろうともした。
しかし、皆が皆、それなりの理由を口にして離れて行くのを見ているうちに、鈴は諦めることを覚えた。
最初から諦めていれば、相手が離れたとしても傷つかずに済むから。
次第に、鈴は殻に閉じこもるようになった。
他者には関わらず、関わらせず……そうしなければ、自身を守ることはできなかった。鈴なりの防御策だった。
そうやって氷のように冷たく寂しい壁を鈴は自分の周りに張り巡らせた。誰も溶かすことのできない厚い厚い壁を。
それでもなんとか大学までを卒業し、その頃には随分症状も安定してきた。いくらか波はあるものの、落ち着いている時は、身内やよく知った男性であれば、触れられても何も思わなくなり、知らぬ男性でも触れられさえしなければ、傍にいても何とか我慢ができるくらいには回復していた。
そんな鈴に、両親はお見合いを勧めるようになった。
たった一人の相手を見つけて、幸せになりなさい……と。
聞こえは良いが、鈴にはその裏に隠れる真意が分かっていた。
症状が落ち着いている今のうちに娘を誰かに押しつけてしまいたい……そんな両親の思いを。
彼らは既に娘を持て余していたのだ。
いつまで経っても完全に傷の癒えることのない娘をこれ以上支えきれず、逃げたくなったのだろう。
別にこれは鈴の思いこみではない。
悲しいことだが、事実なのだ。
あれは大学に入学したばかりの頃、新生活に慣れなかったせいか鈴の心は不安定で頻繁にパニックを起こした。
そんなある日、鈴は部屋から漏れる両親の会話をたまたま廊下で聞いてしまった。
「わたしには……もう無理よ。鈴を支えていけないわ……」
それは思い詰めたような母の声だった。
それに対して聞こえたのは、
「何を言っているんだ。お前母親だろう? 俺は仕事が忙しいんだ、くだらないことで煩わせるな」
溜息混じりの父の声だった。
いくら諦めることを覚えた鈴でも、両親の口から放たれたそれはとてもショックだった。 だから鈴は両親の意向に添うため、何も知らない振りをしてお見合いを受けた。
それで両親が楽になるのなら、そうしてやりたかったから。
ところが、ことはそんなにうまく運ばなかった。
最初のお見合いは会う前に先方に鈴の事情が知れて断られた。
その次は会うところまではいったが、相手が興信所を入れたらしく「縁がなかったということで」と断られた。
家柄のおかげか、お見合い相手に困ることがなかったのを幸いに、親は躍起になって何度も鈴にお見合いをさせた。何とか縁談をまとめようと。
やがて回数を重ねていくと、中には事情を知っても「鈴さんを支えたい」と言った男性たちがいた。ただそれは単に鈴のバックに付いている吉乃宮の財産や家柄が目的なだけで、誰も鈴のことなんか見ても、考えてもいなかった。
だから、結局彼らも鈴の扱いに困って最後は離れていった。
(今度の人だってきっと同じ……)
鈴はその視線をゆっくりと持ち上げ、近くに植えられている咲きかけの桜へと向けた。 両親は言っていた。彼は既に鈴の事情を知っている、と。
それでも断らずにお見合いを受けたのは……
(今度は偽善者? 家柄目当て? ……それとも、単なる酔狂かしら……)
鈴は氷のように冷め切った目で桜を見ていた。
なにより、そんな心配をする必要などないかもしれない。
仕事で遅れる……そんな理由を付けて結局姿を見せないお見合い相手は過去にもいたから。
既に三十分以上遅れているのが何よりの証拠である。
そのうち母親あたりが迎えに来るだろうと鈴は思っていた。
『お相手は急用ができて来られなくなったそうよ』
そんな適当な理由と一緒に。
その時、鈴の斜め後ろで砂利石を踏みしめる足音が聞こえた。
案の定、母が来たのだと思った鈴は振り返ろうともせず、ただ桜を見ていた。
「すぐに満開になるでしょうね」
突然聞こえたそれは、母の物とは違う声で鈴は慌てて桜から視線を落とす。
いつの間にか隣に立っていたのは見たことのない男性だった。
「でも、そんな目で見ては駄目ですよ。花は愛でられて咲き誇るもの……そんな悲しそうな冷たい目で見つめられたら、桜が冬だと勘違いして蕾に戻ってしまいます」
男性はそう言うと今まで桜へ向けていた視線をゆっくりと鈴へ移した。その表情には穏やかな笑みが浮かべられていた。
「龍菱……雅、さんですか?」
気が付けば、鈴は男性にそう尋ねていた。
単なる通りすがりの人かもしれないのに、鈴はなぜだかそれに自信があった。
「はい、鈴さん。お待たせして申し訳ございません。貴女が怒って帰っていたらどうしようかと思いました。待っていてくださって、本当に良かった」
雅はニコリと鈴に微笑みかけた。
それは計算も何もない、純粋な笑顔だった。少なくとも……鈴の目にはそんな風に写った。
春の日差しのように笑う人だと、その時の鈴は思った。
これが、鈴と雅の初めての出会いだった。
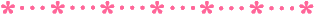
「……きて。……起きて、鈴」
聞き慣れた声に、鈴は意識を覚醒へと向かわせる。
ゆっくりと目を開けば、そこにはよく知る顔があった。
「あなた……」
「鈴、こんなところで寝ていると風邪を引くよ。季節は春になったけど、まだまだ寒いからね」
雅はそう言うと、鈴の肩にストールを掛けてくれた。
鈴は窓辺の椅子に座り、咲き始めた庭の桜を見ているうちに居眠りをしてしまった様だった。
「よく眠っていたね。夢でも見てた?」
そう言われて、鈴は記憶を辿ったが、どんな夢を見ていたのか今ひとつ思い出せなかった。ただ、随分と昔の夢を見ていたような気がした。
「何を見ていたか……忘れちゃったわ」
「きっと良い夢だよ。鈴の寝顔が穏やかだったからね。それより……今年もしっかり咲いてくれたね」
雅は窓辺に寄って、外の桜を眺めた。
鈴もすぐにその隣に立つ。
この木は、鈴が雅と結婚した時に、彼が記念にと庭に植えてくれた。それからずっと、春が来るたび花を咲かせてくれる。
「だって、毎日温かい目で見守っていたもの」
「温かい目で?」
「あら、忘れちゃったの? あなたと初めて会った日……冷たい悲しい目で見たら桜が冬だと思って蕾に戻ってしまうって教えてくれたでしょう?」
「それ……まだ、覚えてたんだ」
雅は隣に立つ鈴を視界に捕らえ、ふふっと笑みを零した。
それは、あの日鈴が見たのと同じ、春の日差しのような温かい笑顔だった。
「忘れないわよ。絶対に、ね」
だって……
(あの日あなたに出会えなければ、わたしの目は今でもきっと氷のように冷たいままだったわ……)
鈴は言葉の続きを心の中で静かに言い添えた。
あの日出会った時から、雅は時間を掛けて鈴を徐々に癒してくれた。
誰も成し遂げられなかったそれを、雅は投げ出すこともなく弛まぬ愛でゆっくりと、確実に。
それはまるで、固く閉ざされた冬に、春の温かい日差しが雪解を促すように……
−おわり−
