結依は話を終えた之親の横顔を見つめていた。
そして、心配した。
之親が今にも泣いてしまいそうだったから。
「本当はね、今日結依に聞くより前に、私は十年前の首謀者を知っていたんだ」
「え?」
それは結依にとって意外な言葉であった。
「……時代が動いてほとんどの者が成安の変を忘れようとしていた頃のことだよ。私は嘉月のことがどうしても頭から離れずにいたんだ。だから中務卿宮に真実を暴くための協力を依頼した。しかし、貴之親王が皇位継承権を放棄した密約を知らない彼がそれを受けてくれるわけがなかった」
それでも之親は諦めなかった。
来る日も来る日も由之に自分の気持ちを伝え続けた。どうしても嘉月がやったとは思えない、と。
やがて甥の熱意に負けた叔父はその協力に承諾した。彼もいつしか自分が嘉月を憎み切れていないことに感づいていたのだ。
「我々が真の首謀者を知ったのは、成安の変から五年以上も経ってからのことだったよ」
時代はいつの間にか槌屋のものとなっており、嘉月のことを記憶に留めている者などもうほとんどいなかった。
声を上げようにも、その時の槌屋の勢力は既に強大であり、真実を知ったところで之親も由之も動くことはできなかった。
「結依、知っているか? 前右大臣……今の太政大臣が病がちだったのは他でもない今の左大臣が毒を盛っていたからだ。……これも後の調べで分かったことだけどな」
二人の間に長い沈黙が続いた。
いつの間にか月に薄雲がかかり、光がわずかに陰った。
結依はそれを待つかのように静かに口を開いた。
「後悔していますか? ……父を少しでも憎み、疑ったこと……」
「あぁ、今もしているさ。できるなら……会って謝りたい。謝って済むことではないが、それでもきちんと謝りたい」
「そうですか……。でしたらもう後悔しないでください。これ以上後悔しても父は喜ばないと思います。父は東宮様を守りたくてその道を選んだのですから、いつまでも後悔していたらかえって悲しむでしょう。それに……父は心の広い人間だから大丈夫ですよ」
之親は結依の言葉に目を細めて笑った。
きっとこれとまったく同じことを言うであろう人物を之親は知っていたから。
之親はいつの間にか、目の前の結依に嘉月の面影を見ていた。
親子なのだから似ているというのは至極当たり前のことなのだが、之親はまるで今嘉月と話しているような気分だった。
「お前のその優しさは父親譲りだね」
「そう言ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます、東宮様」
「東宮か……。ねぇ結依……二人の時は名前で呼でくれないか?」
「…………」
之親の突然の申し出に結依は返事をしなかった。
しかしそれは拒絶という意味ではなく、ただ驚いたという表情だ。
「……昔、嘉月が私のことを一度だけ“之親”と呼んだことがあった。だから、今度は代わりにお前が呼んでくれないか?」
「之親親王様……?」
結依は戸惑いつつも、その名を声に出してみる。
「いや、敬称はいらない。之親でいい。……この都において、主上以外に私を名前で呼ぶ者はもういない。些細なことだがそれが少し寂しくてね。それに、本音を言えばお前に名前で呼ばれている弟たちが少し羨ましいんだ」
照れくさそうに笑う之親を見て結依は優しく笑った。
「之……親?」
結依も少し照れてその名を口にすると、之親は嬉しそうに微笑んだ。
「そうですね……せっかくある名前ですものね」
結依はその場に立ち上がって背伸びをした。今宵の月はこのまま手を伸ばせば届きそうなほど大きい。
結依を“陽月”と呼んでくれる者は少数だがまだいる。しかし“陽月姫”と呼ぶ者はいない。今までも、この先も、おそらくずっと……。
(一生呼んではもらえない名前……か)
結依は之親に聞こえないよう小さく溜息を吐いた。
之親は青白い月の光に照らされる結依の姿を、優しく愛おしむような目で見つめていた。そして、なぜか高鳴る胸に之親は心を躍らせていた。
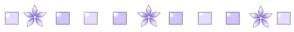
都の空は広い。
結依や総源たちが見つめる月を感慨深そうに見つめる男がもう一人いた。
「……か? ……督様。……右衛門督様!」
顕貢は誰かが呼ぶ声に、ふと我に返ったように月から視線を戻した。
気づけば隣には
「なんだ、どうかしたのか?」
「どうかしたのは右衛門督様ではないですか? まるで月にでも吸い込まれそうなお顔をされていましたよ」
部下である右衛門少将はその眉根に皺を寄せながら心配そうな顔をする。
「いや、静かな夜だと思ってな」
すると、右衛門少将は右手を顎に添え、そう言えば、と思い出すように言った。
「言われてみれば今宵は静かですね。
「月神姫?」
顕貢はその単語に即座に反応した。
「あぁ、例の賊のことですよ。ご存じでしょう? 都を騒がせる不思議な賊。何かを盗むわけでも殺生をするわけでもない、賊とも呼べないような奴のことですよ」
「その賊を月神姫、と言うのか?」
顕貢は問い直した。
「どうもそのようです。検非違使や下っ端の役人たちの間ではそう呼ばれているらしいですよ。月夜の晩に現れ神業のごとき身のこなしで姫君のような長き髪を翻す……それで、月神姫と。そうは言っても、その正体は少年かもしれませんし、もしかしたら中年の男性かもしれません。未だかつて誰も至近距離で見たことはないそうですからね」
「それならば、女性かもしれない、という可能性も十分にあるだろう?」
「それはもちろん十分に。……謎めく女盗賊、ですか。不謹慎ですが、捕まえる方としてはその方がやる気は出ますね。まぁ、望みも込めて今は正体不明の姫、ということにしておきましょう」
右衛門少将はフッと笑みをこぼした。
「正体不明の姫か……」
顕貢は再び視線を月に戻し、その頭には無意識のうちに結依の顔を思い浮かべていた。
顕貢にとって正体不明の姫と言えば結依のことである。
その結依とは乞巧奠の晩に会ったきり、もう三日も会っていない。たった三日だが顕貢にすれば十日以上会っていないような気分だ。
顕貢はあれから毎日結依に文を送っているが、返ってくるのは千波の代筆と思われるものばかりで当たり障りのない文面が綴られているだけだった。
おかげで顕貢はここしばらく憂鬱な気分だ。
まぁ、全く無視されるより何倍かマシではあるが、こんな月夜の綺麗な晩は思わず月を見つめながら物思いに耽ってしまうほどには顕貢も気力的に落ちていた。
(会いたい……な)
(近々また強行訪問でもしてみるか……)
顕貢は陰鬱な気分を転換するように大きく一つ息を吐いた。
「さて、そろそろ宿直に戻るとするか」
「はい。今宵はこのまま静かだとよいですね」
詰め所へ向かって歩き始めた顕貢の後を右衛門少将は小走りに追いかけた。
−第一部 完−
