「どーせわたしはもう若くないれすよー」
深知留はもはや何杯目になるのか分からないワインを煽り、据わった目で宙に向かって文句を言う。
「深知留ちゃん……それ、わたしの前で言う? あなたが若くなければわたしはどうするのよ」
鈴は同じワインをグラス内で揺らしながら溜息混じりに応対する。
すると、
「らって。わたしはもう女子高生には
深知留は呟くように言うと、そのまま項垂れてしまった。
鈴はそんな深知留を見ながら、どうしたものかしら、と肩を竦める。
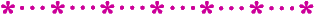
時は少々遡る――――
夕闇迫る頃、部屋で急ぎのレポートを書いていた深知留は、自身のノートパソコンが突然不調になり急遽環のパソコンを借りることにした。
そして難なくレポートを仕上げて必要分を印刷し、さてあとは片づけて夕食まで鈴の所へでも遊びに行こう……そう思った時のこと。
深知留の着ていた服の裾が机の上に積み上げられた本に引っかかり、そこにあった本やら書類やらがバサバサっと落ちてしまったのだ。
やってしまった、と慌てつつ深知留は床に散らばった本と書類を拾い集める。
しかし、途中で深知留はその手を止めた。なぜなら本と書類の他に写真が数枚あることに気づいたから。正確には、封筒からそれらの写真が飛び出していたのだ。
一体何の写真だろうと好奇心で一枚手に取ってみると、それはブロマイドらしかった。中央に写るのは最近テレビやその他のメディアで良く名前を聞くモデル。
(
深知留はその名前を瞬時に思い出す。
公表している年齢は確か十七歳で現役の女子高生。“サエリン”の愛称で親しまれる彼女は、同世代の女子中高生から絶大な支持を受けている。そのカリスマ性からか、彼女の持ち物、使っている物は公表した翌日には全国各地で品切れを起こすとさえ言われている。 ちなみに、サエリはその掴み所のない生意気な小悪魔キャラとエロティックさで世の男性達をも魅了し、その人気ぶりは中高生に限らずお父さん世代に至るまで幅広い。
今深知留が見ている写真の中のサエリもそれに然りであり、普通よりも凝ったデザインのセーラー服を身に纏った彼女は挑発的な笑みをこちらへと向けている。
それはそう、まるでその写真を見ている者を蠱惑するような眼差し……
環の机に何故こんなものが、と思いながら、深知留はあらぬ方向へと考えを巡らせ始めた。
(これ……環さんの私物……?)
そんな考えから、
(環さんて……こういう子が好み…………?)
そんな思考回路へ至るのには大して時間を要さなかった。
深知留とはどう考えてもタイプ的にかけ離れている西山サエリ。そんな彼女のブロマイドを持つほどに、環が彼女を好んでいたとしたら……
そんなことを悶々と考えているうちに時間はいつの間にか経過し、気づけばメイドが食事の用意が調ったと深知留を呼びに来てしまった。
深知留はそのまま手早く本と書類とその問題の写真を机に積み上げて鈴が待つダイニングルームへと向かった。
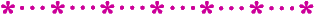
未だ西山サエリが思考回路を占める深知留は食事中、鈴の話にも集中できず適当な相槌を打っていた。
ちなみにテーブルに着いているのは鈴と深知留のみ。
雅は仕事の関係で食事を済ませてくると連絡があり、環は三日ほど前から神戸へ出張へ行っていて今日帰宅予定だ。
「環さん、今日何時頃になるの?」
「夕方神戸を出るって行ってましたけど、十時過ぎるとかって言ってたような気がします」
鈴の問いかけに答えながら深知留は、
(確か、西山サエリも神戸出身だっけ……)
どうでもいいことを考える。
そんな考え事をしていたせいで……
「……留ちゃん……深知留ちゃん!」
「え?」
深知留はうっかり鈴の話を無視してしまった。
「一体どうしたの。何だか今日は変よ? 落ち着かないっていうか……何か悩み事?」
心配そうに問いかける鈴に深知留は「何でもないですよ」と答える。
すると鈴は、
「あ、今日久しぶりに環さんが帰ってくるから待ち遠しいんでしょう? かれこれもう二週間ぶりじゃない?」
フフッと含み笑いをしながら深知留を構うように言った。
そう。深知留は環と既に二週間近く会っていない。
神戸へ行ったのは確かに三日前だが、その前に彼はアメリカへ飛んでいた。そこから帰国して深知留と会う間もなく神戸へ直行したのだ。
だから早く帰ってきて欲しいし会いたいのも間違ってはいないのだが、目下別の問題を熟考中の深知留は「まぁそうですねぇ……」と誤魔化すような返答しかできない。
そもそもこの二週間のブランクがあるからこそ、深知留はこんな馬鹿みたいなことで不安になったのかもしれない。毎日顔を合わせていれば何でもないことなのに。
もちろんそんな事情を知る由もない鈴は、「早く帰ってくると良いわね」と言い添えた。
◆◆◆
食後、鈴は友達にお土産でもらったから、と上質なワインを深知留に勧めた。
しばらくはダイニングルームで酌み交わしていたが、鈴も深知留も互いにお酒に強いために途中からはリビングルームへと場所を移した。
リビングルームの窓辺の一角、酒を酌み交わすには丁度いい少し小洒落たスペースで鈴は二本目のワインを開け、深知留のグラスに注いでやる。
「ねぇ、深知留ちゃん……やっぱり何かあったでしょう?」
深知留はそれに答える代わりにグラスを傾けて中の葡萄色を呑み込む。
勘のいい鈴はワインを飲み始めてすぐに深知留の異変に気づいた。
どうしたことか今日の深知留はグラスに注げば注いだだけ呷るのだ。
これまでにも鈴は何度か深知留と酒を飲んだことがあるが、彼女はいつももっと遠慮して量を抑えていたし、なおかつ楽しそうに飲んでいた覚えがある。
ところが、今日の深知留ときたら愛想笑いはするものの、始終難しい顔で何かを考えているようだ。その考え事に意識が向いているせいなのか、酒を自制する方へ意識が回っていない様子である。若しくは、何か思うところがあってそれを忘れるためにワザと量を飲んでいるのかもしれないが、そこまでは流石の鈴も分からない。
最初はそれも、先ほど食事の時に尋ねたように環が帰ってくるから気も漫ろになっているのかと鈴は思ったが、どうやらそんな様子とは異なる。
「わたしには言えないこと?」
返事のない深知留に鈴は再度尋ねる。
「…………」
しかしやはり返事はない。
「別に無理に聞く気はないわよ。でも、女同士だし何か力になれるかな、って。それにもし環さんのことで悩んでるなら誰に言うよりも力になれると思うけど?」
その時、既に深知留は随分酔いが回っていた。普段は結構な量を飲んでも顔色一つ変わることもないのに、既にその頬はピンク色に染まり目も心なしか潤んでいる。
そしてもう何か物を考えることも億劫で……
「西山サエリが……」
気づいた時には、深知留はそう言葉を紡いでいた。
◆◆◆
ひとしきり事情を説明し終えた深知留は、やがて酒の勢いも手伝ってかいじける方向へと進んでいった。その頃にはもはや呂律も回っておらず……
「どーせわたしは若くないれすよー」とか「男は結局若い女がいいんれすか?」とか「
そのたび、
―――深知留ちゃん、ちょっと落ち着きましょう? ね?
鈴はその台詞を何度言ったか知れない。
そんな中、鈴はことのあらましを自分の知りうる情報と合わせて理解していた。
最近、菱屋グループのアパレル部門が、ティーンエイジャーをターゲットとした新ブランドを立ち上げようとしていると数日前に雅が話していたのだ。そのブランドのイメージが『エロ可愛さ』を売りにしているために、イメージキャラクターとして西山サエリが選ばれたとも。
恐らく環が持っていたという彼女のブロマイドは、広報宣伝用に撮影した物だろう。というのも、雅の話では環がその新ブランド立ち上げの総責任者になっているとのことだったから。
それにもしも環が個人的に西山サエリを好んでいたとしても、深知留に見つかるような場所へブロマイドを置いたりはしないはずだと鈴は考えた。
もちろん、深知留を選んでいる時点で、それと正反対の西山サエリが環の好みだというのは九割九分の確率であり得ないが。
きっとそれを今深知留に話してあげればそれで全ては丸く収まる話なのだが、この時少しばかり別の考えを持ってしまっていた鈴は今すぐ事情を説明する気は無かった。
そして、
「ねぇ深知留ちゃん……わたしいいアイデアがあるんだけど」
鈴は再び空になった深知留のグラスにワインを注ぎながら提案をする。
深知留はそれを受けながら、少しばかり首を傾げる。
「あのね、今更女子高生に戻ることはできないけど、女子高生になることはできるのよ」
鈴の言わんとしていることが理解できない深知留はその首をさらに深く傾げる。
「ほら、前にアルメリアのセーラー服着たことあったでしょう? またあれ着て、帰ってきた環さんを誘惑しちゃえばいいのよ。西山サエリっぽく小悪魔みたいに積極的にね。そしたらきっと環さん、そんなブロマイドなんてどうでも良くなるから、ね?」
そう、前回冬服しか着せることができなかったために、鈴はいつか夏服も、と虎視眈々と機会を狙っていたのだ。しかも今度は前回とは訳が違う。深知留に着せるために彼女用にサイズの補正まで行っておいたという用意周到さだ。
その千載一遇とも言えるチャンスが、今ここでやってくるとは鈴自身も思っていなかった。
鈴は続ける。
「環さんだってね。西山サエリが好きとは限らないわよ? ほら、総じて男性ってコスプレに興味があるみたいだから。
そう言えば、と深知留は思い出す。
あの時、妹が欲しかったと異常な程に興奮を見せた雅。そして散々兄妹ごっこをした気がする。
しかもあの後しばらくして、ナースやらキャビンアテンダントやらに興味はないかと聞かれ、着せ替えごっこがしたくなったら衣装はあるからいつでも言うんだよ、と雅は言っていた。
「それに深知留ちゃん、サエリンに負けたくないでしょう?」
鈴の最後の一押しとも言える言葉に対し、
――着ません
いつもの深知留ならきっとそう言ったに違いない。後先を考えて、それから羞恥心も合わせれば絶対にそう言ったはずだ。
でも、
「着る。着ます。わたし……負けないもん。わたしらって……小悪魔になる!」
その時、酔った深知留にはそんな高等な思考回路も恥も存在しなかった。
自分だってやればできる! そんな根拠のない自信だけが深知留を支配していたのかもしれない。
