十二月二十四日――クリスマスイブ
高校三年生のこの時期、本来ならクリスマスも正月もなく必死に勉強して居るであろうこの時期、既に推薦で帝都大学理工学部へ合格している由利亜は自室のベッドに寝転がっていた。
「明日はもう誕生日かぁ……。今年で四回目、ね」
由利亜は今まで見ていたカレンダーから視線を上げて、枕元に座らせてある大きな熊のぬいぐるみを見た。その首元には青色のサテンのリボンが綺麗に結んである。
大きな熊のぬいぐるみ……これは小夜子、いや蒼からの初めての誕生日プレゼントだ。三年前、由利亜の十五歳の誕生日にこの熊は届けられた。大きな胡蝶蘭の鉢植えと一緒に。
小夜子との文通を始めて一年と少しが経過した頃、由利亜がある話を手紙に書いたのがキッカケだった。
『青色のリボンを首に巻いた熊のぬいぐるみを持っていると幸せになれる』
確か、由利亜はそんな内容を手紙に綴った覚えがある。
ただそれは本当に“最近はやっているモノ”として話のネタにしただけで、別におねだりをするつもりなど無かった。
その証拠に、その熊のぬいぐるみも本当はドイツに本社を構えるとある会社のものでなければならない、という限定付きであったが当時由利亜はそこまで詳しい事情は話さなかった。
それなのに、忘れもしない十二月二十五日の朝一番……青色のリボンを首に巻いた大きな熊のぬいぐるみが由利亜の元へと届けられたのだ。もちろん、噂のドイツ社製である。
年配でも女性なだけあってよく知ってるな……と、当時由利亜は小夜子に感心した。しかし実際のところは、困った蒼が深知留に助けを求めたと最近になって聞いた。
その次の年は何も言うまいと注意を払っていたのに、由利亜はうっかり愛用していた腕時計が壊れたことを手紙で漏らしてしまい、誕生日には可愛くてオシャレでセンスの良い、三拍子が見事に揃った腕時計が届いた。その年も大きな胡蝶蘭の鉢植え付きで。
ちなみに去年は、流石にボロを出さなくなった由利亜に痺れを切らした“小夜子”が「何か欲しいものは?」と尋ねてきた。由利亜が「何もいらない」と言い続けていると、当日には若い女性の間で一番人気のあるブランドのワンピースが届いたのだ。それも限定物で友達が手に入らない、と口々に言っていた色味だった。
実のところ、由利亜も他多くの子と一緒でそのワンピースが欲しかった。でも、高価な物だし限定品だし手に入れられる物ではないと諦めていたのだ。
だから由利亜は、申し訳ないと思いつつそのプレゼントには素直に喜んでしまった。そして、流石小夜子さん、乙女のツボを押さえてる……と甚く感激したものだ。もちろんこの時も深知留が縁の下の力持ちであったことは言うまでもない。
やはりこの年も胡蝶蘭の鉢植えが一緒に送られてきた。
そして今年は四回目となる誕生日、のはずなのだが……
「今年は……何も無いかもねぇ……」
由利亜は小さくため息を吐きながらカレンダーへと視線を戻した。
彼女の脳裏に数日前の蒼とのやりとりが思い起こされる。
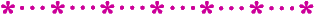
由利亜はその日の早朝、眠い目をこすりながらやっとの思いで出かける寸前の蒼を捕まえた。
一週間ぶりの再会だった。
というのも、ここ一週間ほどは二人は完全なすれ違い生活を送っていた。年末で仕事が忙しいのか蒼は由利亜が寝入った後に帰宅し、朝起きる前には出かけていた。酷い時は帰らずに会社に泊まったこともあった。
そんな蒼の状態を把握していた由利亜は、邪魔をするつもりなど毛頭無かったが、どうしても一つだけ彼に尋ねたいことがあったのだ。
『クリスマスもお仕事ですか?』
本当は、
『わたしの誕生日もお仕事ですか?』
とストレートに聞きたかったが、それでは誕生日プレゼントをねだっているようなので、敢えて遠回しに尋ねた。
すると蒼は、
『朝から大事な用事が入ってる』
と少しの躊躇いもなく答えた。
そう言われてしまったら由利亜はそれ以上は何も言えなくて、そのまま出かけてしまう蒼の背中を見送るよりなかった。
極論を言ってしまえば、由利亜は蒼に何かをプレゼントして欲しいわけでもないし、祝って欲しいわけでもない。ただ、誕生日という特別な日を蒼と2人で過ごしたいだけだった。蒼が傍にいてくれるなら、それで良かったのだ。
でも今の調子ではそれも夢で終わってしまいそうだ。
「もしかして……蒼さん、わたしの誕生日なんて忘れちゃったのかもね」
由利亜は熊の鼻をツンとつついて再びため息をついた。
◆◆◆
その日の晩、蒼は思いの外早く帰ってきた。
「お帰り、蒼さん。竜臣さんもお疲れ様です」
由利亜は帰ってきた蒼と竜臣を玄関で迎えた。
蒼は「ただいま」と答え、竜臣は深く一礼をした。
やはりどうしても諦めのつかなかった由利亜は、この際ダイレクトに明日はできるだけ早く帰って一緒にいて欲しい、と本人にお願いしようと思ったのだ。
多少強引で我が侭すぎる気もしたが、この際仕方がないと由利亜は割り切った。
「ねぇ蒼さん、明日なんだけど……」
由利亜が意を決して言いかけた時だった。
「由利亜、明日朝から時間あるよな? 学校ももう冬休みだろう? それにお前受験勉強もないし」
突然の蒼の言葉に由利亜はすぐにその次を期待した。
(蒼さん、やっぱりわたしの誕生日、覚えていてくれたんだ!)
そう思って。
「時間なら朝からたっぷりありますよ。冬休みの課題も特別出ていないので」
由利亜は嬉しさを押さえきれずに笑顔で答えた。
が、
「深知留がお前に会いたいってさ。明日一日朝からどうしても付き合ってほしいって」
蒼の言葉は由利亜の期待を思い切り裏切るものだった。
普段は嫌なことがあっても極力表には出さない由利亜も、この時ばかりは表情が曇ってしまったのが自分自身でもよく分かった。
しかし、蒼はそんなこともお構いなしに「いいだろう?」と重ねて確認するので、由利亜は特別断る理由も思い浮かばずにそのままなし崩しに了承の意を述べてしまった。
嫌だと言えない自分を、由利亜は恨めしく思った。
「じゃあ後で、深知留にメールを送ってやって」
「……わかりました。今すぐメールします」
すっかり肩を落としてしまった由利亜は、それ以上この場に居るのが嫌で自分の部屋へとつま先を向けようとした。
その時だった。
「由利亜、それどうしたんだ?」
呼び止めた蒼の視線は由利亜の首に向けられていた。
「あぁ、これですか?」
由利亜は徐に自分の首に掛かるネックレスを摘み上げた。
それにはハートの大きなネックレストップがついている。そのハートの縁にはピンクの宝石が控えめに一粒埋め込まれている。
実はコレ、今日の昼間京からプレゼントされた一品である。「一日早いけど、お誕生日おめでとう」と。
由利亜と同じ大学に通うべく現在受験勉強真っ最中の京は、明日は会えないから、と就業式の今日、このプレゼントを渡してくれたのだった。
基と二人で選んだ物だそうで、由利亜は包みを開いた瞬間にとても気に入って早速付けてみたのだ。
「貰ったんですよ。誕生日プレゼントで」
由利亜は素っ気なく答えた。しかし、せめてもの反撃に“誕生日”の所には少しアクセントを付けてみる。
「誰に?」
折り返して投げかけられた蒼の問いかけに由利亜はすぐに答えなかった。
なぜなら、少しばかり心がささくれていた彼女はこの時瞬時にあることを思い立ってしまったのだ。
恐らく誕生日なんて忘れているであろう蒼へのちょっとした仕返しを。
「可愛いでしょう? これ。基さんて毎年毎年センスの良い物選んで送ってくれるんですよね」
女優スイッチの入った由利亜は言った。満面の笑みを添えてできるだけ嬉しそうに。
その時一瞬、蒼の顔が歪んだことなど知りもしないで。
別に由利亜は嘘は吐いていない。確かに毎年、基は京と連名で一緒に何かしらの誕生日プレゼントを贈ってくれる。もちろん、主体は京だが今回はそれを言わないだけのことである。
「今年のプレゼントもすっごく気に入ったから早速つけてみたんです。流石基さん、小さい頃から見てるだけあってわたしの好みもよく知ってるんですよ。似合ってるでしょう?」
女優スイッチ全開の由利亜は大切そうにそのハートのネックレストップを握りしめた。
相変わらずの満面の笑顔で。
その次の瞬間だった。
「似合わない」
「…………」
いきなり飛び込んできた言葉に由利亜は一瞬自分の耳を疑った。
ブレーカーが落ちたかのごとく女優スイッチが一気に切れる。
「大きな飾りは由利亜には似合わない。下品に見えるだけだ。センスがない」
蒼は無表情かつ冷静な口調でそれだけ言うと、ぽかんとした由利亜を残して足早にその場を去っていってしまった。
「蒼様!!」
大股で歩いていく蒼の後を竜臣が慌てた様子で負っていくのを、由利亜は瞬きも忘れて見ていた。
(何……? 何なの………? 蒼さん……怒った??)
もう呆気にとられるしかなかった。
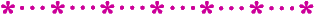
バンッ!!………ボスッ!!
蒼は凄い勢いで部屋の戸を開けると、続けて力任せに鞄をソファに投げつけた。
「蒼様!! はしたないですよ」
「そんなこと知るか!」
蒼はそのまま鞄を投げつけたソファにどかりと腰を下ろした。
相当苛々しているのか、その眉間には皺が寄って不機嫌極まりない顔をしている。
「嫉妬、ですか? 樹月のご子息様への」
竜臣はご機嫌斜めな主人を見ながら、やれやれと心の中でため息を吐いた。
「違う」
――では、ヤキモチですね?
即答した蒼に竜臣は続けて聞こうとしたが、寸前で踏みとどまった。
言ってやりたいのは山々だが、これ以上は火に油……むしろガソリンを注ぐだけである。
恐らく蒼本人も嫉妬だという事くらいは分かっているはずだ。ただそれを認めたくない、というところだろう。
(普段は恐ろしいほど冷静なのに、由利亜様のこととなると本当に手が付けられないほど不安定になるな……)
(まぁ今日の場合は由利亜様も悪いような気はするが……)
「蒼様、もしかして由利亜様は寂しかったんじゃないですか?」
竜臣の言葉に蒼は俯けていた顔を少し上げた。
「蒼様が明日のことを何一つ言葉にされないから、忘れてると思っていらっしゃるのでは?」
「何を馬鹿な……会議を忘れても由利亜の誕生日を忘れるわけが無いだろう」
「そう思っていらっしゃるのは蒼様だけですよ。由利亜様は不安なんだと思いますが? 今日だってそれを確認したくてわざわざお迎えに出ていらしたのでしょう。“明日”と仰っていましたし」
「…………」
蒼は何も答えなかった。
竜臣はそれを確認して再び言葉を続ける。
「覚えている、ということだけでも、今すぐお伝えして差し上げればよろしいのに。それだけでもきっと由利亜様は満足されるでしょう。優しいお方ですから」
「……それは駄目だ」
「なぜです?」
「たぶん……今行ったらまた余計なことで苛つきそうな気がする。それで……八つ当たりするのがオチだ」
やり場のない思いをぶつけるかのように、蒼は拳を作ってそれをクッションにぶつけた。
(感情をコントロールする意志が出てきたのは結構ですが……まだまだのようですね)
(これが財界で“静かなる獅子”と呼ばれる人と同一人物だとは、とても思えませんねぇ……)
竜臣は蒼を見ながらその表情に意味深な笑みを浮かべた。
