翌朝、目が覚めると屋敷にいる多くの人がそれぞれに由利亜に「おめでとう」の声をかけてくれた。しかしそれはただ一人、蒼を除いて、の話だ。
肝心の蒼は居なかった。
由利亜は起きてからずっとその姿を探していたが、どこにも見当たらなかった。
朝食の時に藤乃に尋ねると「恐らくお仕事に行ったのでは……」と曖昧な返事が返ってきた。何しろ朝が早すぎて今日は藤乃も関知していない様子だった。
「氷室さん……今日、蒼さんは?」
深知留との約束に出かける前、由利亜は見送りに出てくれた氷室にも同じように尋ねた。
「蒼様はもう出社されました。まだ夜も明けぬうちにですよ。年末ですからお忙しいのでしょう。私も今朝はお会いしておりません」
氷室の答えに由利亜は「そうですか」と、落胆してため息を零した。
どうせ……と諦めて、蒼にはもう何の期待もしないはずの由利亜であったが、本当に「おめでとう」の一つもないのかと思うと、酷く寂しい気持ちになったのだ。
(何よ……蒼さんの馬鹿!)
由利亜は恨めしそうに着ていたワンピースの裾を握りしめた。それは去年、蒼が送った物だった。
昨日はちょっとした出来心で蒼の気分を害してしまったから、せめてものお詫びに、と由利亜はこのお気に入りのワンピースに袖を通したのだが、それもどうやら無駄骨だったようである。
「由利亜様、本日はいつ頃お戻りですか?」
「今日は……深知留さんのところに泊まるかもしれません。……そう、蒼さんに伝えてください」
由利亜はそれだけ言うと、玄関を出て行った。
◆◆◆
氷室はそんな由利亜をやれやれといった風に見送ると、あるところへ電話をかけるべくその場を後にした。
『もしもし』
「氷室です。たった今、お出かけになられましたよ」
氷室は電話の相手、蒼が出るなり言った。
「蒼様、由利亜様と喧嘩でもなさったのですか?」
『いや……別に………』
「今日は深知留様のところに泊まるかもしれない、とお伝えするよう承りましたが?」
『…………』
「まぁ、それに関してはご心配なさらなくても大丈夫ですよ」
すっかり言葉に詰まった蒼に氷室はクスリと笑みを零した。
「深知留様にお任せしておけば何とかしてくださるでしょう。それより……準備は整っておりますよ。業者も手配済みです。三十分後にはこちらに着くそうです」
『分かった。そのころ着くよう俺も戻る』
「蒼様、お忙しいようでしたらこちらで何とかしますが?」
『いや。それじゃ意味がない』
気遣う氷室に蒼は短く答えるとそのまま電話を切った。
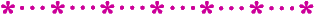
「で、蒼さんなんて言ったと思います!? 即答で『似合ってない』ですよ。信じられます? 普通、本当に似合ってなくても『似合ってるよ』とか言うもんじゃないですか!?」
「まぁ、そうよねぇ……。でも、蒼は口下手だから……」
「そういう問題ですか!? しかも『下品に見える』って。失礼だと思いませんっ!? いくら何だってデリカシーってもんはないんですかっ!?」
由利亜は悠長に構える深知留に声を荒げた。
周囲の視線が一気に由利亜に集まるが、興奮している彼女はそんなのお構いなしである。
「……由利亜ちゃんちょっと落ち着いて。ね?」
深知留が慌てて由利亜を宥める。
ここは街中にあるとあるカフェ。
二人はつい先ほど、午後のティータイムを楽しむためにここに入った。
深知留の用事というのは単にショッピングに付き合って欲しかっただけのことで、二人は開店時から今まで回れるだけのお店を回って楽しんだ。
そして、付き合ってくれた御礼にご馳走するわよ、と深知留がこのカフェに由利亜を連れてきたのだった。
そこで既に小一時間ほど、由利亜は深知留に愚痴っていた。お題はもちろん昨日の蒼の態度について。深知留はそれを嫌な顔ひとつせずに聞いてくれた。
由利亜と深知留はあれから何だかんだで仲良くやっている。
そもそも、ここまで仲良くなったのは由利亜が「帝都大学の理工学部を受けたい!」と言い出したのがキッカケで、それを先輩でもある深知留が進んで面倒を見てくれたのである。深知留のおかげもあって、由利亜は推薦入試の小論文も面接も余裕でパス出来た。
面倒を見て貰う主体はもちろん受験のことであったが、それに付随して由利亜は蒼とのことも深知留に相談していたのだ。流石幼なじみだけあって、彼女のアドバイスはいつだって的確で由利亜は何度も助けられていた。
そんな経緯があって、由利亜は深知留を本当の姉のように慕うようになり、対する深知留も由利亜を妹のように可愛がってくれた。
今日だってこうやって深知留に会って正解だったと由利亜は思っていた。そりゃ最初はあまり乗り気ではなかったが、あのまま家にいたって悶々と思いこむだけだったと考えると、今は連れ出してくれた深知留に感謝さえしていた。
「蒼はね、きっと樹月くんの名前を出されたから嫉妬したのよ。本心でそんなこと言う人間じゃないわ。それに、由利亜ちゃんだってそうなることを多少予測して名前を出したんでしょう?」
「まぁそれは……確かにそうですけど……」
冷静に分析をする深知留に由利亜はしょんぼりとした様子で頷いた。
そんな由利亜を眺めながら、深知留は昨晩さぞかし苛ついたであろう蒼を想像していた。
(蒼……よっぽど頭に来たんだろうなぁ。しかも相手がよりにもよって、だしね……ご愁傷様だわ)
幼なじみの性というべきか、苛つく蒼を容易に想像できてしまう自分に深知留は少し笑えた。おまけに、竜臣なり氷室なり藤乃なりがその宥め役に回ったことも想像がつく。
(結婚して奥さんにしたんだから、多少は独占欲も収まるかと思ったけど、蒼には逆効果みたいね。由利亜ちゃんも苦労するわ……)
深知留は由利亜には分からないよう小さく一つため息を吐いた。
「あのね由利亜ちゃん、蒼は今日の誕生日を忘れてなんていないと思うわよ?むしろ、忘れろって言っても忘れられないわよ。毎年毎年二ヶ月も前には『由利亜の誕生日が』ってうるさいほど騒いでたもの」
一度言葉を止めた深知留は、由利亜を優しい表情で見つめた。
(本当はね、今年もずっと騒いでたわよ。いつもの年以上にね)
それは思うだけで、深知留は言葉にはしなかった。一応、蒼の名誉のために。
由利亜は今まで俯き加減だったその顔をわずかに上げる。
「でも……蒼さん、おめでとうも言ってくれないんですよ? 今朝だって早くから仕事に行ったままだし、メールの一つもありません……」
由利亜は今朝から幾度となく“新着メール問い合わせ”をしていた。
――建物の地下にいたら電波が悪いかも
――最近携帯の調子悪いし、巧く受信できてないかも
――今日に限ってサーバーに不具合が生じてるかも
そんな言い訳を繰り返しながら蒼からメールが来てると期待して何度も何度も問い合わせた。
しかし、いつも表示は同じで『新着メールはありません』だった。
それはもう、携帯電話が本格的に壊れてそれしか表示しないのではないかと思うくらいに。
その表示を見るたびに、由利亜のため息の数は増えていった。
「仕事に関しては急用もあるから、メールを送る余裕もないのかもしれないわ。会議が立て込んでいるのかもしれないし。でもね……蒼のことだから、何があっても今日中には絶対由利亜ちゃんを祝ってくれるわよ」
再び俯きかけてしまった由利亜を深知留は元気づけた。
深知留は深知留で、朝自分と会ってからこまめに携帯電話をチェックしている由利亜に気づいていた。
蒼からの連絡を待っているのだということは、何も聞かなくても由利亜の表情を見ているだけで分かった。
「……本当に? 深知留さんはそう思います?」
「うん。思う。大体、わたしが今まで蒼のことで外したことがあった?」
由利亜はそれに大きくかぶりを振った。
深知留はそれを確認すると、自分の鞄からゴソゴソと何やら小さな包みを取り出した。
それは白いリボンが掛かった小さな箱だった。
「開けてみて?」
深知留に言われたとおり、由利亜はそれを開いた。
すると、中から出てきたのは華奢な造りのストラップだった。それにはシルバーでできた小さな熊のチャームが付いていて、熊のお腹には“y”というアルファベットが彫ってあった。
「今日どうしても会いたかったのはコレを渡したかったからでもあるの。わたしからの誕生日プレゼントよ」
「深知留さんから?」
「一番最初の年、蒼が熊のぬいぐるみを送ったの覚えてる? それと同じ会社が出した物なのよ。誕生日に名前の頭文字が入ったそれを贈られると幸せがやってくるんですって。付けたら蒼からメールが来るかもしれないわよ?」
深知留はニコリと笑ってみせた。
「ありがとうございます!!」
由利亜はさっきまでの表情が嘘のように嬉しそうに笑うと、すぐに鞄から自分の携帯電話を取り出してもらったばかりのストラップを括り付けた。
携帯電話を目線にまで持ち上げると、鎖に繋がった熊がゆらゆらと可愛らしく揺れる。
熊に集中している由利亜を余所に、深知留はちらりと腕時計を見た。
時刻はちょうど五時を過ぎたところである。
「ねぇ由利亜ちゃん、買い物も十分できたし、メールを待つよりもう家に帰ってみたらどう? ……案外、仕事の終わった蒼が先に帰って待ってるかもしれないわよ?」
深知留の言葉に由利亜は期待に胸を膨らませた様子で大きく頷いた。
◆◆◆
由利亜を見送った深知留は、すぐに携帯電話からある場所へ発信した。
「あ、もしもし蒼? 約束の五時を回ったから由利亜ちゃん帰したからね? 準備は無事終わった?」
『なんとか。今日は無理言って悪かったな、深知留』
「良いわよ、別に。わたしも色々と楽しかったし。そうそう、由利亜ちゃんの携帯に見慣れないストラップが付いてると思うけど、わたしからのプレゼントだからね。『似合わない』なんて変な嫉妬しないでよ?」
『……それ、由利亜に聞いたのか?』
「まぁね。可愛い妹の愚痴ってとこかな。それに、造りも小さくて華奢な物にしたから下品じゃないと思うけど」
『…………』
全てを知っているであろう深知留に蒼はもはや返す言葉がない様子だった。
そんな蒼に深知留は笑いながら「健闘を祈ってるわ」と言って電話を切った。
(相変わらず不器用な男よね、あいつは。ところで、今年は胡蝶蘭じゃなくて何の花を贈るのかしらね?)
深知留は毎年毎年胡蝶蘭に自分の思いを込めていた蒼を思い出して、その表情を綻ばせた。
胡蝶蘭の花言葉は『あなたを愛します』。
どちらかと言えば『幸せが飛んでくる』が有名だが、蒼が由利亜に贈り続けたのはあくまで前者だ。「いっそストレートに赤い薔薇を贈ったら?」と深知留は提案したが、それでは直接的すぎると胡蝶蘭を選んだのだった。
(蒼らしいというか……もうちょっとストレートに伝えた方が由利亜ちゃんは喜ぶと思うんだけどなぁ)
深知留は思いながらすっかり冷めてしまったコーヒーに口を付けた。
その時、深知留の携帯電話が鳴った。
画面に表示された名前を見ると深知留の表情が自然と緩む。
(わたしも人のこと心配してる場合じゃないか……)
「もしもし? ……はい、もうすぐ帰りますよ」
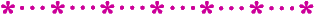
「お帰りなさいませ、由利亜様」
由利亜が屋敷に戻るといつものように藤乃が迎えてくれた。
「ただいま戻りました」
「深知留様はお元気でしたか?」
「はい、元気でしたよ。一緒にたくさん遊んできました。あの……藤乃さん、蒼さんは……その…もう……」
由利亜は途中で口ごもってしまった。
帰ってきているのか聞きたかったが、これでまた帰ってきてないと言われるのが由利亜は少し恐かったのだ。
藤乃はそんな由利亜を優しい表情で見つめながら答える代わりに「どうぞ」と言って手に握っていたあるものを差し出した。
「これは?」
由利亜は差し出されたそれを受け取る。
それはピンクのリボンが付いた鍵だった。
「二階の一番奥の部屋、ご存じですね?」
由利亜は頷く。
確かそこはその昔、早次郎と好江が使っていたという部屋だ。
三つの部屋が横並びになっていて左が早次郎の部屋、右が好江の部屋、そして中央にベッドルームがあるのだと以前聞かされたことがある。
しかしそこには常に鍵がかけられていて、由利亜はその存在を知ってはいたが未だかつて中を見たことは無い。
「奥様のお部屋がこれで開きます。そちらへ行ってみてください」
藤乃はそれ以上は何も言わずに躊躇する由利亜の背をポンと押した。
