「や……はぁ、ん……あお、い…さん……」
組み敷かれた由利亜は潤んだ瞳で蒼を見上げる。
彼女の白い肌は火照って赤みが差しており、至る所には蒼が付けた印が花を咲かせている。
蒼はそれに酷く嗜虐心をそそられ、
「もっと啼いてごらん、由利亜」
笑みさえ浮かべて意地悪を言い、彼女の胸の頂をペロリと舐めた。
「ひぁ……ふ、あぁん………」
由利亜は蒼によって生み出された未知の快感に耐えることができず、嬌声を上げて彼の背中に爪を立てた。
◆◆◆
ガバッ!!
蒼は飛び起きた。
一瞬、前後不覚となり状況を理解することができない。
辺りを見回すと暗闇に浮かぶ情景からここが寝室であるということを少しずつ理解し始める。
(夢……か……)
思って蒼はガシガシっと頭を掻いた。
最近よく見るようになった夢。
快感に濡れ、困ったような表情で見上げる由利亜……それを組み敷くのは蒼自身…………
欲求不満の青少年でもあるまいし……と突っこみたくなるほどに、蒼は同じシチュエーションの夢を見続けていた。おかげで、ここのところ酷い睡眠不足だ。
原因はもちろん……
(よく寝てるな……)
蒼は隣ですやすやと寝息を立てている由利亜を視界に収めた。
二月も半ばに差し掛かった頃、既に寝室を共にして二ヶ月近くが経とうとしている。しかし、二人はまだ最後の一線を越えてはいなかった。
別にワザと越えていないわけではない。蒼だってさっさと越えたかった。だが、今日に至るまで、致し方なく、どうしようもなく、抗うこともできずに、越えられなかったのだ。
全ての始まりは由利亜の誕生日だった。
寸前まで行って寝てしまった自分を、蒼は心底悔やんだ。あれほど自己嫌悪に陥ったことはないと断言できるほどに自らを責めた。
それでも、
『これから嫌だって言われてもずっと一緒ですよ』
なんとも嬉しいことを言ってくれた由利亜に期待して、翌日仕事を驚くほど早くこなして帰ろうとすれば、退社寸前に竜臣が神妙な面持ちで社長室に飛び込んできたのだ。
『蒼様……申し訳ございませんが、明日の朝一番でドイツへ飛んでいただけますか?』
死刑宣告も良いところだった。
申し訳ないと思うなら言ってくれるな……思わず言いそうになったのを、蒼は懸命に堪えた。
しかし、竜臣はそんな蒼に追い打ちをかけた。
『うまくいけば年明け早々には帰国できる予定です』
あの時はもう、蒼は自らの耳を疑いたくて仕方がなかった。
籍を入れて初めて由利亜と過ごすはずだった年末年始を、何が悲しくて別々に迎えなければならないのか……できることなら聞かないふりをしたかった。
それでも、せめてもの救いだったのは、由利亜が『わたしは大人しく留守番してますから、気をつけて行ってきてくださいね?』と優しく送り出してくれたことだ。
結局、仕事に一段落を付けて蒼が帰国したのは年が明けて七日も経った頃で、今度こそ、と喜び勇んでいれば、次は卒業の掛かった論文が大きな壁として蒼の前に立ちはだかった。
もともと、仕事との両立で出席日数も単位もギリギリの蒼が論文に手を抜くことは許されなかった。教授と何度も推敲を重ね、帰宅はいつも深夜。
もちろん由利亜は既に寝息を立てていて、キス位したところで起きる気配もないほどだった。
あまりの欲求不満に蒼は何度も隣で寝ている由利亜を組み敷いてしまおうかと思った。しかし、それでは由利亜があまりに可哀想で蒼は鋼の理性で耐え抜いた。自分で自分を褒めてやりたいほど蒼は頑張った。
そんなことをしているうちに、日付はもう二月十三日を迎えていた。
ふと時計を見やると時刻は五時過ぎを差していた。冬の夜明けはまだやってこない。
蒼は一向に目を覚ます気配のない由利亜の頬を優しく撫でた。
それから一つ溜息を零すと、彼女を起こさないようにそっとベッドを抜けた。書斎のソファーでもう一眠りしようと思ったのだ。起きてしまう手もあるが、蒼は寝られる時に寝ておかないと睡眠不足で倒れそうだ。
できることなら、蒼はこのまま由利亜の隣で彼女のぬくもりを感じながら眠りに落ちたかったが、それはもはや色んな意味で限界だった。
蒼は飛び起きた。
一瞬、前後不覚となり状況を理解することができない。
辺りを見回すと暗闇に浮かぶ情景からここが寝室であるということを少しずつ理解し始める。
(夢……か……)
思って蒼はガシガシっと頭を掻いた。
最近よく見るようになった夢。
快感に濡れ、困ったような表情で見上げる由利亜……それを組み敷くのは蒼自身…………
欲求不満の青少年でもあるまいし……と突っこみたくなるほどに、蒼は同じシチュエーションの夢を見続けていた。おかげで、ここのところ酷い睡眠不足だ。
原因はもちろん……
(よく寝てるな……)
蒼は隣ですやすやと寝息を立てている由利亜を視界に収めた。
二月も半ばに差し掛かった頃、既に寝室を共にして二ヶ月近くが経とうとしている。しかし、二人はまだ最後の一線を越えてはいなかった。
別にワザと越えていないわけではない。蒼だってさっさと越えたかった。だが、今日に至るまで、致し方なく、どうしようもなく、抗うこともできずに、越えられなかったのだ。
全ての始まりは由利亜の誕生日だった。
寸前まで行って寝てしまった自分を、蒼は心底悔やんだ。あれほど自己嫌悪に陥ったことはないと断言できるほどに自らを責めた。
それでも、
『これから嫌だって言われてもずっと一緒ですよ』
なんとも嬉しいことを言ってくれた由利亜に期待して、翌日仕事を驚くほど早くこなして帰ろうとすれば、退社寸前に竜臣が神妙な面持ちで社長室に飛び込んできたのだ。
『蒼様……申し訳ございませんが、明日の朝一番でドイツへ飛んでいただけますか?』
死刑宣告も良いところだった。
申し訳ないと思うなら言ってくれるな……思わず言いそうになったのを、蒼は懸命に堪えた。
しかし、竜臣はそんな蒼に追い打ちをかけた。
『うまくいけば年明け早々には帰国できる予定です』
あの時はもう、蒼は自らの耳を疑いたくて仕方がなかった。
籍を入れて初めて由利亜と過ごすはずだった年末年始を、何が悲しくて別々に迎えなければならないのか……できることなら聞かないふりをしたかった。
それでも、せめてもの救いだったのは、由利亜が『わたしは大人しく留守番してますから、気をつけて行ってきてくださいね?』と優しく送り出してくれたことだ。
結局、仕事に一段落を付けて蒼が帰国したのは年が明けて七日も経った頃で、今度こそ、と喜び勇んでいれば、次は卒業の掛かった論文が大きな壁として蒼の前に立ちはだかった。
もともと、仕事との両立で出席日数も単位もギリギリの蒼が論文に手を抜くことは許されなかった。教授と何度も推敲を重ね、帰宅はいつも深夜。
もちろん由利亜は既に寝息を立てていて、キス位したところで起きる気配もないほどだった。
あまりの欲求不満に蒼は何度も隣で寝ている由利亜を組み敷いてしまおうかと思った。しかし、それでは由利亜があまりに可哀想で蒼は鋼の理性で耐え抜いた。自分で自分を褒めてやりたいほど蒼は頑張った。
そんなことをしているうちに、日付はもう二月十三日を迎えていた。
ふと時計を見やると時刻は五時過ぎを差していた。冬の夜明けはまだやってこない。
蒼は一向に目を覚ます気配のない由利亜の頬を優しく撫でた。
それから一つ溜息を零すと、彼女を起こさないようにそっとベッドを抜けた。書斎のソファーでもう一眠りしようと思ったのだ。起きてしまう手もあるが、蒼は寝られる時に寝ておかないと睡眠不足で倒れそうだ。
できることなら、蒼はこのまま由利亜の隣で彼女のぬくもりを感じながら眠りに落ちたかったが、それはもはや色んな意味で限界だった。
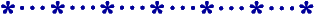
翌朝、蒼は携帯電話のアラーム音で叩き起こされた。しかし、彼がゆっくりと身を起こしたのはベッドの上ではなく書斎の机の上。
蒼は今朝方まで論文の最終チェックをしていたのだ。
アラーム音を消しながら、日付を確認する。
今日は二月十四日――蒼の卒業が掛かった論文の審査がある日だ。
午前に一本会議をこなし、午後一番でこの審査を終えてしまえば、今日の予定はもう終わりだった。そして、何より今日は恋人達が甘い日を過ごすバレンタインデー。蒼は大きな期待に胸を膨らせずにはいられなかった。
着替えを済ませた蒼は書斎を出てベッドルームへ行く。
しかし、
(あれ……?)
そこに由利亜の姿はなかった。いつもならまだスヤスヤと寝息を立てている時間なのに、彼女の姿はどこにもなかった。
先に食事でも摂っているのかと思い、行ってみたがそこにも由利亜の姿は無かった。
食事の支度をしてくれた藤乃を捕まえて聞いてみると「先ほどその辺りでお見かけしましたが……」と言われた。
結局出かける間際まで蒼が由利亜に会うことは叶わなかった。
蒼が玄関前で車を待っていると、庭では華宮家お抱えの庭師、
「源さん、今日は朝からご機嫌ですね」
いつの間にか蒼の傍に控えていた竜臣が同じく佐田を見ながらそう言った。
「浮かれる気持ちも分かりますが、この寒さでは体に応えるでしょうに」
「浮かれる? 何でだ?」
「何でって……コレを貰ったからではないでしょうか?」
竜臣はそう言って鞄のポケットから赤いリボンが付いた包みをひとつ取り出した。
「なんだ、それは」
「あれ……蒼様ご存じないんですか? バレンタインのチョコレートですよ。由利亜様から屋敷の者たちへの」
「由利亜から?」
蒼は訝しそうな顔をする。
「ええ。今朝早くから屋敷中に配っておいででしたよ。私もそれでいただきました。蒼様だけでなく、皆に配るところがお優しい由利亜様らしいですよね。ただ、由利亜様が凄いのはそれだけではないんです。渡す相手によって中身が違うようなんです。甘い物が苦手な私のような者には甘みを抑えた手作りのチョコレートを……屋敷中といったら凄く大変でしたでしょうに、事細かにそれぞれの嗜好をお調べになったようですよ。ちなみに、血糖値が気になる源さんには低カロリーのチョコレート蒸しパンだったみたいですよ。流石ですね、由利亜様は」
竜臣はフフッと笑って大切そうにその包みを再びポケットへと収めた。蒼はそれを瞬きもせず見つめていた。
「それで、蒼様は何を貰ったんですか? 大きなチョコレートですか?」
「え……?」
突然話を振られた蒼は口籠もった。
「もしかして、ハート型のチョコレートとか? 新婚さんはいいですね」
「……てない」
ニコニコと笑みさえ浮かべて尋ねる竜臣に、蒼が呟くように言った時だった。
「蒼様、お出かけですか?」
氷室が冬の寒さに手を摺り合わせながら玄関から出てきた。
「氷室……お前は由利亜に何を貰ったんだ?」
そんな言葉が蒼の口をついて出た。
すると案の定、氷室はすぐに、ジャケットのポケットから竜臣と同じ赤いリボンの付いた包みを取り出した。
「コレステロールを意識したクッキーだそうですよ。ありがたい限りです。由利亜様にはホワイトデーのお返しを今から考えなくてはなりませんね。蒼様は由利亜様から何を? やはり、王道の手作りチョコレートですか?」
氷室もまた、何も考えずに竜臣と同じ様に尋ねた。
次の瞬間だった。
「貰ってない……」
蒼は不機嫌極まりない様子で吐き捨てるように言った。それは辺りが凍り付くような冷気さえ孕んでいた。
そして、蒼はちょうど目の前に車がやってくると、運転手がドアを開けるのも待たずに自分で乱雑に開けて乗り込んだ。
『貰ってない』
まさかそんな答えが来るとは思っていなかった氷室も竜臣も、ただ驚いたような顔をして蒼を見るしかなかった。
