「蒼様、お出かけになりましたよ」
「え!?」
キッチンへやってきた藤乃に、由利亜は思わず小麦粉をふるっていたふるいをガチャンと置いた。
その衝撃で粉が舞い散る。
「……けほッ……蒼さん、もう行っちゃったんですか!? いつもより早いですよね? 今日は論文審査って言ってたから、頑張ってねって言いたかったのに……」
由利亜はがっくりした様子で視線を落とした。
「確か……午前に一つ大切な会議があるとおっしゃっていましたから、それでいつもより早くお出かけになったようですよ。わたくしもうっかりしておりました。今しがた玄関の方で物音がしたので、見に行ったら既に……申し訳ございません」
「良いんですよ。藤乃さんのせいじゃないですから。それに、今日は早く帰ってくるって言ってた気がするから、それまでに仕上げないと」
由利亜はニコリと笑って粉の入ったボールを指差して見せた。
その時、
「……ックション……クシュン」
由利亜は二度ほど続けてくしゃみをした。
「大丈夫ですか?」
「ちょっと寒くて……」
「え? 暖房は入ってますけど……もう少し強くして参りましょうか?」
少し動けば汗ばむほどには温かいこの空間に不思議に思いながらも、藤乃は首を傾げながらキッチンを出て行った。
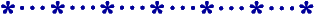
その日の蒼は凄かった。
何が凄かったって、仕事のこなし方が。午前に会議を終え、昼に退社する前までこれでもかと言うほどの決済を出した。
竜臣はそれをただ冷静に見守っていた。
彼は最近気づいたことがある。
蒼が由利亜に関して何かしら機嫌が悪い時、仕事が異常に速いのだということを。そして、容赦もないのだということを。
クリスマスの翌日から行ったドイツ出張の時も凄かった。出張先で生じた不足の事態にも淡々と対応し、双方とも利益を得られるように鮮やかなまでの采配で取りなしたのだ。最初は蒼の若さに難色を示していた相手方も、その腕前には商売敵であることも忘れて大絶賛をしたほどだ。
論文の追い込みと仕事の追い込みが重なり、由利亜とすれ違い生活を送っていた時も然り、である。到底こなせないであろうと思われた仕事量を、まるで油のよく効いた機械のようにサクサクと片づけていった。
単に仕事のことだけを考えるのであれば、これはこれでいいかな、と思わなくもないが、流石にそれでは蒼が可哀想すぎるし、いつか歪みが生じる恐れが大いにある。
それに、反対に由利亜とうまくいっている時も一応仕事は順調である。ただ、一人でにやけたり、やたらと相手に甘かったりでスピードと精細さに欠けるだけだという話だ。
と言っても、その辺りは秘書室でカバーしきれるレベルである。
(まぁ、夫婦円満の方が良いですかね)
竜臣は意外と簡単にそう結論づけた。
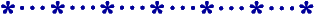
「蒼、ご苦労様」
審査を終え、一息吐いた蒼に声をかけたのは深知留だった。
深知留の学部は数日前に既に審査を終えている。よって彼女は既に卒業を待つだけの悠々自適の身である。
今日は蒼の勇姿を見に来たというところだ。もちろん、自ら望んで、というのもあるが今朝一番で由利亜に「代わりに応援してください」と電話で言われたからだ。
可愛い妹の頼みとあれば聞かないわけにはいかない。
「深知留、お前こんな所にいていいのか? 今日は………」
「バレンタイなのに、って? ……ご心配いただき、すみませんねぇ。でも生憎予定がないんです」
「別れたのか?」
蒼は論文の原稿を揃えながら無表情にシレッと言った。
「失礼ね……」
深知留は一瞬顔を歪めたが、すぐに「ははぁん……」と意味深な笑みを浮かべた。
「蒼、由利亜ちゃんからチョコレート貰ってないのね」
深知留はそれを言い切った。「貰った?」とか「貰ってないの?」とか疑問系ではなく、「貰ってない」という断定系で。
別に由利亜から情報を得たわけではない。深知留は分かったのだ。蒼の様子や機嫌の悪さから。
そして今、一言も答えずに苦虫を噛み潰したような顔をしている蒼が、深知留の予測を何よりも肯定していた。
(やっぱり、当たりね……)
本当にわかりやすい男だと深知留は一人納得する。
「あのねぇ、由利亜ちゃんの事だから、心配しなくても用意はしてあるはずよ」
そう言うと、深知留は蒼の肩をポンポンと叩き、コートのポケットから何かを取り出した。
「はい、わたしから“義理”チョコ。いつもお世話になってるお礼です。きっと由利亜ちゃんは手作りだろうから、わたしからはこれで十分よね」
深知留は蒼に板チョコレートを持たせると、バイバイとその場を後にした。
審査会場を出た後、深知留は携帯電話を開いてすぐに一通のEメールを作成する。内容は任務の完了を伝えるもの。そして、送信先はもちろん由利亜である。
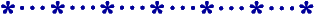
審査後の残務を終え、蒼が屋敷に帰ったのは六時を過ぎた頃だった。
しかし、どうしたわけか由利亜の姿は見えなかった。蒼の予定ではいつものように「おかえりなさい」と由利亜が出迎えてくれるはずだった。そしてあわよくば、その手にはリボンの掛かった可愛い包みか箱でも持って。
藤乃に尋ねると「先ほどまでいらっしゃったんですが……」と今朝同様あてにならない答えが返ってきた。
蒼は自室へ行くとベッドルームを抜けて由利亜の部屋へと向かった。
何度かノックをしたが、中からは全く反応がない。
今朝からずっと会っていないせいか蒼は妙な胸騒ぎを覚えた。
「由利亜……いないのか?」
蒼は部屋の扉を開けて由利亜の部屋へと入った。
中は電気がついていて、少し前まで誰かがいた雰囲気がある。
ふと、蒼の目にあるものが飛び込んできた。
部屋の中央に設置してあるガラスでできたテーブルに水色の箱が置いてあったのだ。その上には何かメッセージカードのようなものが置かれていた。
(駄目だ……)
そんな理性が蒼にわずかな抑制をかけたが、気づいた時にはそのまま誘われるように箱に近づいていた。
その時だった。
ガチャリと廊下側の扉が開き、入ってきたのは冬の寒さのせいか頬を真っ赤に染めた由利亜だった。
「蒼さん……帰ってたんですか!?」
「ゆ、由利亜……」
由利亜はガラスのテーブルに駆け寄るとすぐに箱を手に取り、その背に隠した。
「これ……中、見ました?」
「いや、まだ。お前が見当たらないから、不安になって見つけに来たところだ。……それより、どこに行ってたんだ?」
蒼の問に由利亜は躊躇したが、ジッと見つめる蒼を誤魔化すことはできないと踏み、鞄から包みを一つ出してその中身を見せた。
「これ……買いに行ってました」
それは一本の青いリボンだった。
「準備してたのが短くて、足りなかったんです。それで蒼さんが帰ってくる前に買ってこようと思ったんですけど……」
由利亜は背中に隠していた箱を目の前に持ち出した。箱の上に置かれたメッセージカードには『蒼さんへ』と由利亜の字で書かれている。
不意に、
『由利亜ちゃんの事だから、心配しなくても用意はしてあるわよ』
深知留の言葉が脳裏を過ぎって「もちろん、そんなこと分かってたさ」と蒼は心の内で答えた。
「開けても良いか?」
蒼は嬉しさで逸る気持ちを抑えながら、すっかりしょんぼりしてしまった由利亜に尋ねた。
由利亜がうんと頷いたのを確認して蒼はその箱を開ける。
その瞬間、
(――――)
蒼の顔は一気に綻んだ。
中に見えたのはハート型をした手作りのチョコレートケーキ。
そしてそこには由利亜から蒼へ向けられたメッセージのデコレーション……
『大好きな旦那様』
メッセージが目に飛び込んだ瞬間、蒼は溢れかえらんばかりの嬉しさに支配された。それはもう、嬉しくて嬉しくて……自分がどうにかなってしまうのではないかと思うくらいに。
「由利亜……ありがとう。嬉しいよ」
この時、もはやどう堪えてもふにゃりと崩れゆく表情を蒼は止めることができなかった。
しかし、それを見守る由利亜の表情がどこか冴えていなかったことに蒼はこの時気づかなかった。
