「あーあ……」
由利亜は一人自室のソファーに座って深い溜息を吐いた。
先ほどから睨めっこをしているのはその手に持つ青いリボンである。
「なんでもっと早く気づかなかったんだろう……」
由利亜は深い後悔の念を抱いていた。
蒼の帰宅に合わせてケーキを焼き上げ、デコレーションもし、あとはラッピングするだけ、とそこまでは完璧なほど順調だったのに、いざリボンを掛けようと思ったらそれが足りなかったのだ。
我ながら、情けないと思った。
何で事前にしっかりと確認しておかなかったのだろう、と。
その時には既に深知留から審査終了を告げるメールも届いていて、蒼はもうしばらくすれば帰ってきそうだった。
それでもなんとか間に合うかと思って大急ぎで買い物に出たが、運の悪いことに由利亜の帰宅前に蒼がケーキの箱を見つけてしまったのだ。
「リボン……掛けたかったのにな……」
由利亜は呟くように言った。
別にリボンくらい、と思うかもしれないが、由利亜にすればより完璧な状態で蒼に渡したかったのだ。何より、このバレンタインが二人にとっては初めてであったからこそ。
そして、他の人たちの赤色とは違う青色のリボンを掛けてこそ『蒼さんは特別』という由利亜なりの意味があったのだ。
もちろん、リボンなど掛かっていなくても蒼は十分に喜んでくれた。
ケーキはあの後すぐに半分ほど平らげて、残りはもったいないから明日、とさっさと冷蔵庫に入れてしまった。
それでも……
「あーもう、自分が嫌になる……」
由利亜の自己嫌悪は変わらない。
リボンを握りしめ、何度目か分からない溜息を吐くと由利亜は頭痛を感じた。
自己嫌悪に陥りすぎたのか、先ほどからやけに頭が痛む。だから余計に気分が滅入っていた。
その時だった。
ガチャリ、と音がしてベッドルーム側の扉が開いた。
覗くのはパジャマの上からガウンを羽織った蒼だった。
「由利亜、まだ起きてるのか?」
入浴を済ませてベッドルームに行けば、先に待っているであろう由利亜の姿が無く、蒼は探しに来たのだった。
「蒼さん……」
「どうかしたのか?」
蒼は由利亜の隣に腰掛けた。
風呂から上がったばかりなのか、その髪はわずかに湿っている。
「いえ、別に……なんでもないんです」
「何でも無いって顔じゃないだろう?……それ……」
蒼は由利亜の手にあったリボンに気づいた。
由利亜は慌ててそれを隠そうとしたが、間に合わずに蒼にするりと抜き取られてしまった。
「これ、俺へのプレゼントのために用意してくれたんだろう?」
由利亜は無言でうんと頷く。
「でも……結局間に合わなかったし、使い道、なくなっちゃいました」
「いや、あるよ」
蒼の意外な返答に、由利亜は思わず「え?」と聞き直す。
そんな由利亜に蒼は優しく微笑んだ。
「心配しなくても、使い道ならある。本当は、もう一つ欲しいものがあるんだ。だからそれに使えばいい」
「蒼さんの……欲しいもの、ですか?」
由利亜は考えるように首を傾げた。
以前何度か由利亜は蒼に『欲しいものは?』と聞いたことがあるが、いつでも特にないと言われていた。そんな蒼が欲しいもの……由利亜には皆目見当が付かなかった。
「そう。だから、由利亜はしばらくの間目をつむっててくれないか?」
何が何だかよく分からないが、由利亜はとりあえず蒼の言う通りその目を静かに閉じた。
それからしばらくして「もういいよ」という蒼の声が聞こえるまで。
「蒼……さん……?」
目を開けた由利亜はそれ以上、何も言うことができずに俯くようにして自分のパジャマの襟元を見つめた。
そう、由利亜の首には青いリボンが少し不格好に蝶々結びされていたのだ。
「俺としては、それが欲しいんだけど……」
そんな蒼の言葉をキャッチしてから、たっぷり十数秒の間を空けて……
(――――!!)
由利亜の顔はボンッと火を噴くほどに真っ赤になった。
蒼の意味することを、分かってしまったのだった。そりゃあもう、いくら鈍い由利亜でも……
「駄目……か?」
答えのない由利亜に、蒼は寂しそうな表情で重ねて問う。
(そんな顔……反則だ……)
恥ずかしさで蒼と視線を合わせることなど到底叶わない由利亜は、彼の表情をちらりと垣間見ながら思った。
そして、
「……駄目じゃ……ないです……」
蚊の泣くような声で由利亜は答えた。それが彼女の精一杯だった。
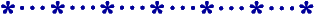
ベッドルームの淡いダウンライトの元、由利亜と蒼は口づけを交わしていた。
その時、由利亜は極度の緊張のせいか頭に血が上っているような、フラフラとした感覚を得ていた。
これから我が身に起こりうることを考えればそれも無理はないことだったが、由利亜は何とか自身を落ち着かせようとした。しかし、緊張は高まる一方なのか、頬は紅潮し、体温までもが上昇しているようだった。
「緊張……してるのか? それとも、興奮してる?」
蒼にもそれは気づかれたようで、キスの合間に悪戯っぽい笑みを浮かべながらそう問われた。
「由利亜の口の中、凄く熱い………」
ダイレクトに言われた恥ずかしさに、由利亜は潤んだ瞳で蒼を睨み付ける。
しかしそれは蒼を煽る要素でしかないために、彼は再び由利亜の唇に自分のそれを重ねた。
「ふ、ぁ……んぁ…あ……」
由利亜の唇から可愛い声が零れる。
それは夢の中の声とは違い、より可愛らしく潤いのあるものだった。
蒼はそれがもっと聞きたくて、由利亜の口内を激しく責め立てた。
やがて、蒼の大きな手が由利亜の首をなぞったその時だった。
(…………?)
由利亜の肌に触れた蒼は、それがあまりに熱いことに気がついた。
いくら興奮しているにせよ、それはどう考えても尋常ではない体感だ。
「由利亜……?」
蒼は思わず由利亜を自分の体から引き離した。
虚ろな表情を見せ、その瞳を潤ませる由利亜。それは、普通に考えれば快楽に濡れはじめた扇情的な姿であるのだが……
明らかな異変を感じた蒼は迷わず由利亜の額に手を当てた。
「お前……もしかして……」
やはり尋常ではない熱さに、蒼が顔を顰める。
「……熱があるんじゃないのか?」
そう尋ねた蒼に、由利亜は、
「え? 別に……大丈夫で、す……よ……」
答えたが、なぜか目の前にいるはずの蒼の顔がぐにゃりと歪んだ。
「お、おい! 由利亜っっ!!」
何だか凄く遠くで、蒼が呼ぶ声が聞こえた気がした。
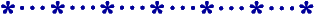
「インフルエンザですね」
華宮家が好意にしている医師は、由利亜を診てそう診断した。
蒼はすっかり寝込んでしまった由利亜の枕元で「今、流行ってますからねぇ」と言った医師の言葉を思い出していた。せっかくやってきた一世一代のチャンスを流行りのインフルエンザに持って行かれるとは……全く、とことんツイていない。
「……んン……あ、おい……さん」
熱が高いせいか由利亜の額には玉のような汗が浮かんでいる。
「大丈夫。そばにいるよ……」
蒼は冷やしたタオルで汗をそっと拭ってやる。
「だ、め……そばに、いたら……うつっちゃい…ます」
そっぽを向こうとする由利亜の頬に蒼はそっと手を寄せる。
「キスしたからもう無理。うつってるよ」
そう言ってフッと笑って見せた蒼に、由利亜は一瞬困ったような顔をしたが、そのまますぅっと眠りに落ちてしまった。
それからしばらく、蒼は飽きもせずに由利亜の寝顔を見つめていた。そして、その手には由利亜の手がしっかりと握られている。
(俺の欲しいもの……決して手に入れられないと思ったのに、今はこんなに近くにいる。別に焦ることはないんだよな)
「治ったら期待してるよ、俺の奥さん」
蒼は由利亜を起こさないようそっと囁いた。
−おわり−
