乞巧奠──別名、星の祭、七夕──
五節句の一つであり、七月七日の晩に盛大に行われる。
儀式そのものはもちろん、管弦や漢詩の催しを行うために殿上人を初めとする貴族たちは毎年数日前からその準備に追われる。
この日は牽牛星と織女星が天の川を渡り、年に一度の逢瀬を楽しむという古い言い伝えがある。そして、人々はこの日に織物・詩歌・裁縫・書道の上達や恋愛の成就を祈る。
その日、大内裏は朝早くからごった返していた。皆が皆、夜に向けての準備に追われていたのだ。
中でも朝廷の儀式を取り扱う
日は既にその姿を半分ほど山に隠している。
之仁は親王席で心を弾ませながら夕闇がかった空を見上げていた。
「何を見ているのだい?」
東宮、之親は弟に優しく尋ねる。
「んー? あのねぇ、あまのがわをみているの」
「まだ星は見えないだろう。もう少し空が暗くならなければ……」
「違いますよ、東宮」
そばにいた之義が之親の言葉を遮った。
之親が之義の顔を不思議そうに見る。
「之仁はたぶん星ではなく空から降ってくる結依を待っているのです。ほら、今日は乞巧奠でしょう? 結依との約束の日ですから」
「そうだよ。ぼくがケンギュウで、結依がショクジョなんだ」
之仁は兄たちに対し、楽しそうに笑いかける。彼は結依が来るのを今か今かと心待ちにしていたのだ。
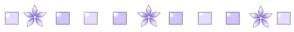
依沙の琴演奏は大盛況のうちに幕を閉じた。十数名いる奏者のうちでも、依沙は独奏を任されて一際輝いていた。
結依は演奏を終えた依沙が自分のところに来るのを待ちながら、先程の琴の音を思い出していた。
「結依、どうだった? 今の演奏。完璧でしょう?」
依沙はやや小走りに結依の元へやってきた。
「もちろん。誰にも劣らない澄んだ音色だったわ」
「あったりまえでしょ!」
完璧、とさらっと言えて、褒められたら謙遜せず素直に喜ぶところが依沙らしい。
「では義姉様、早いところ引き上げましょうか」
結依は満足そうに微笑んでいる依沙に間髪入れずに詰め寄った。
実は驚くことにこの琴演奏の行われていた舞台は、すぐ傍が親王席だったのだ。約束を守るつもりのない結依にとって、偶然会ってしまったなどという状況だけは御免である。
親王たちに会ってしまったら今度こそ絶対に、こんばんはさようなら、では済まないことを結依は前回の経験で嫌という程学習している。
というわけで、この場合は帰るが勝ちである。
が、
「馬鹿なこと言わないで、結依ちゃん」
依沙はにっこりと笑って結依の手を取った。
結依は一瞬にして嫌な予感を覚える。
「奏者は管弦の宴を最後まで楽しむことができること、結依ちゃんは知っているわよね? しかも控えの間まで用意されているの。一応顔を出さなければ体裁が整わないわ。それに、これは妻の立場も育児も全部忘れられる夢の様なひとときなのよ……素敵だわぁ。さぁ、サクッと行きましょう、サクッとね」
結依は後半部にやや納得がいかなかったが、あえて突っ込まず瞳を潤ませる依沙を冷ややかな目で見ていた。
そしてそのまま、結依は抵抗さえ許してもらえず引きずられるように依沙に連行されたのだ。
依沙との勝負、連戦連敗。……未だ記録更新中。
半強制的に連行される結依の中にはもはや抵抗という言葉はなかった。
◆◆◆
不幸中の幸いとはまさにこのこと。
たまたま依沙に与えられた控えの間が親王席から遠かったのだ。
同じところには大納言の姫や式部卿宮 の姫、右京大夫 の姫など琴の弾き手として都でも有名な姫君たちが勢揃いである。どの姫君も皆、依沙と同じように姉妹を連れての参加だ。
きらびやかな十二単にその衣に焚きしめられた品の良い香の香り。時折聞こえる衣擦れの音と扇の内から漏れる高貴な笑い声……
結依はこういったものがあまり得意ではなかった。
といっても、結依もこの日のために依沙とお揃いの十二単を新調し――といっても、依沙が予め勝手に用意していたのだが――香も依沙に指導してもらって合わせ直した。その結果、今は気品溢れる内大臣家の二の姫としてこの場にいる。
見た目は一緒にいる姫君たちと何ら変わりはないが、結依は確実にこの場を窮屈な空間として感じていたのだ。
そしてもうひとつ、結依にとっては居心地の悪い用件があった。
「きゃっ……今、こちらを向いたわ」
式部卿宮の姫が妹姫に向かって言う。
「あら、それは姉様に気があるのではなくて?」
妹姫が姉を構うように言うと、式部卿宮の姫はその頬をポッと可愛らしく染める。
結依は今までその姉妹に向けていた視線を別の場所に移した。
すると今度は、右京大夫の姫が御簾越しのある人物に賢明に熱い視線を送っているのが目に入る。
いや、正確に言えばそれは彼女に限ったことではなく、その場にいる多くの姫たちが似たような行動を取って御簾越しに立つ人物に自分の魅力を余すところなく表現しようとしている。
「……相変わらずね」
「え?」
結依は不意に聞こえた隣の依沙の言葉を聞き返す。
「あなたの恋人は、相変わらず人気があるのねって言ったのよ」
依沙は自らの口元を檜扇で覆い、極力絞った声で話す。そしてその視線を御簾越しの人物にやった。
そう、御簾越しに立つのはあの顕貢だ。
顕貢は今夜の宴のため近衛府(このえふ)に借り出されて警護をする予定であると結依は事前に本人から聞いていた。しかし、それがここだとは今日この場所に来るまで結依も知らなかったのだ。
結依にとってそれは不都合なこと――その一方で、他の姫君達にとっては都でも群を抜いてイイ男である顕貢が目の前にいるのだから、それは何よりの喜びであり楽しみなのだ。彼女たちはあわよくばここで彼に目をかけて貰い、いずれは文を貰い通ってもらえれば……と甘美な夢を見ているに違いない。
「それにしても、いい男って何を着てもいい男なのね」
依沙はフッと鼻で笑うように言い放った。
今宵もいつも通り、顕貢の容姿は作り物のように美しい。しかし、今日は仕事中のために弓矢をその背に負ってとても勇ましい格好をしている。
依沙の言う通り、元々顔のいい男がこういう支度をするといつもの三割増しにいい男度が上がるのは当たり前のことで……結果、姫君たちの視線も三割から五割増しに釘付けというわけである。
それはもう、飽きないの? と思わず聞いてやりたくなるくらいに。
しかし、結依がこの場の居心地を良しとしない本当の理由はそれではない。
「……なんで、あの方なのかしら」
どの姫からかポツリとこぼれた台詞が結依と依沙の耳に飛び込んでくる。
「あら、でもそれは噂にしか過ぎないでしょう?」
先ほどとは別の姫が答えるように言う。
そして、
「顔だけしか取り柄のない様な姫に、あの顕貢様が夢中になるわけありませんわ」
また別の姫が言った台詞が静まりかえったその場に響く。
その後、痛いほどに自分に向けられてくる視線を結依は何とも言えない気分で受けていた。
顔だけしか取り柄のない姫――それは、紛れもなく結依のこと。
才色兼備の義姉の後ろについ隠れてしまいがちの結依だが、その容姿は都でもちょっとした噂になるくらいだった。
姫君たちがあまり外に出歩かない現代においてそのような噂は全くの嘘や誇大表現であることも多かったが、少なくとも結依のそれは紛れもない真実。こうやって実際に結依を目にした同世代の姫君たちが嫉妬心を剥き出しにするくらいには。
しかし、顔以外に取り柄がないというのは大げさで、結依だって琴や書道、縫物など人並みにはできる。むしろ、人並み程度でやめていると言った方が妥当かもしれない。
普通の姫と違って賊の仕事をこなす結依にとっては、琴や書道などの鍛錬に費やす時間などあまりないのが本音だ。それでも、人並み程度にこなすのだから十分な及第点といえるだろう。
これを義妹贔屓の依沙に言わせれば、
『うちの結依が人並み程度で手加減しているだけありがたいと思いなさい』
だそうだ。
たまたま依沙に与えられた控えの間が親王席から遠かったのだ。
同じところには大納言の姫や
きらびやかな十二単にその衣に焚きしめられた品の良い香の香り。時折聞こえる衣擦れの音と扇の内から漏れる高貴な笑い声……
結依はこういったものがあまり得意ではなかった。
といっても、結依もこの日のために依沙とお揃いの十二単を新調し――といっても、依沙が予め勝手に用意していたのだが――香も依沙に指導してもらって合わせ直した。その結果、今は気品溢れる内大臣家の二の姫としてこの場にいる。
見た目は一緒にいる姫君たちと何ら変わりはないが、結依は確実にこの場を窮屈な空間として感じていたのだ。
そしてもうひとつ、結依にとっては居心地の悪い用件があった。
「きゃっ……今、こちらを向いたわ」
式部卿宮の姫が妹姫に向かって言う。
「あら、それは姉様に気があるのではなくて?」
妹姫が姉を構うように言うと、式部卿宮の姫はその頬をポッと可愛らしく染める。
結依は今までその姉妹に向けていた視線を別の場所に移した。
すると今度は、右京大夫の姫が御簾越しのある人物に賢明に熱い視線を送っているのが目に入る。
いや、正確に言えばそれは彼女に限ったことではなく、その場にいる多くの姫たちが似たような行動を取って御簾越しに立つ人物に自分の魅力を余すところなく表現しようとしている。
「……相変わらずね」
「え?」
結依は不意に聞こえた隣の依沙の言葉を聞き返す。
「あなたの恋人は、相変わらず人気があるのねって言ったのよ」
依沙は自らの口元を檜扇で覆い、極力絞った声で話す。そしてその視線を御簾越しの人物にやった。
そう、御簾越しに立つのはあの顕貢だ。
顕貢は今夜の宴のため近衛府(このえふ)に借り出されて警護をする予定であると結依は事前に本人から聞いていた。しかし、それがここだとは今日この場所に来るまで結依も知らなかったのだ。
結依にとってそれは不都合なこと――その一方で、他の姫君達にとっては都でも群を抜いてイイ男である顕貢が目の前にいるのだから、それは何よりの喜びであり楽しみなのだ。彼女たちはあわよくばここで彼に目をかけて貰い、いずれは文を貰い通ってもらえれば……と甘美な夢を見ているに違いない。
「それにしても、いい男って何を着てもいい男なのね」
依沙はフッと鼻で笑うように言い放った。
今宵もいつも通り、顕貢の容姿は作り物のように美しい。しかし、今日は仕事中のために弓矢をその背に負ってとても勇ましい格好をしている。
依沙の言う通り、元々顔のいい男がこういう支度をするといつもの三割増しにいい男度が上がるのは当たり前のことで……結果、姫君たちの視線も三割から五割増しに釘付けというわけである。
それはもう、飽きないの? と思わず聞いてやりたくなるくらいに。
しかし、結依がこの場の居心地を良しとしない本当の理由はそれではない。
「……なんで、あの方なのかしら」
どの姫からかポツリとこぼれた台詞が結依と依沙の耳に飛び込んでくる。
「あら、でもそれは噂にしか過ぎないでしょう?」
先ほどとは別の姫が答えるように言う。
そして、
「顔だけしか取り柄のない様な姫に、あの顕貢様が夢中になるわけありませんわ」
また別の姫が言った台詞が静まりかえったその場に響く。
その後、痛いほどに自分に向けられてくる視線を結依は何とも言えない気分で受けていた。
顔だけしか取り柄のない姫――それは、紛れもなく結依のこと。
才色兼備の義姉の後ろについ隠れてしまいがちの結依だが、その容姿は都でもちょっとした噂になるくらいだった。
姫君たちがあまり外に出歩かない現代においてそのような噂は全くの嘘や誇大表現であることも多かったが、少なくとも結依のそれは紛れもない真実。こうやって実際に結依を目にした同世代の姫君たちが嫉妬心を剥き出しにするくらいには。
しかし、顔以外に取り柄がないというのは大げさで、結依だって琴や書道、縫物など人並みにはできる。むしろ、人並み程度でやめていると言った方が妥当かもしれない。
普通の姫と違って賊の仕事をこなす結依にとっては、琴や書道などの鍛錬に費やす時間などあまりないのが本音だ。それでも、人並み程度にこなすのだから十分な及第点といえるだろう。
これを義妹贔屓の依沙に言わせれば、
『うちの結依が人並み程度で手加減しているだけありがたいと思いなさい』
だそうだ。
