「実は約束なんて守る気はなかったでしょう?」
之義は初めから分かっていたよ、とでも言いたげにさらっと言った。
「そ、そんなことありませんよ?」
結依の声は思わず上擦る。
結依がお忍びで通されたのは東宮御所。
之親が宴席に戻ったために、ここには結依と之義の二人だけがいる。
「そう? なんか不服って顔をしているけど」
之義が疑いの眼差しを向けている。
(そうです、不服です。とっても。最大級に不服です)
結依は思うだけでそれらを言葉にはしない。……というより、言葉にできない、である。不服を顔に出さぬよう、営業用の笑顔を作るのに精一杯なのだ。
しかしそんな努力もむなしく、結依の周りを漂う雰囲気が『不服』を表現してしまう。
「結依!」
顔の筋肉が徐々に疲れ始めた頃、嬉しそうに笑った之仁と由之がやってきた。
「東宮がおっしゃった通りだな。それだけ着飾っていれば空から来るのは無理だ。結依、十二単もきちんと似合うじゃないか。之仁、お前の織女はとても綺麗だよ」
由之は感心した様子で結依を上から下までじっくり眺める。
「結依、かわいいね」
「ありがとうございます」
結依は自分の隣にちょこんと座った之仁に優しく笑いかけた。
そして、
「さて、約束は果たしましたからもう失礼してもよろしいですね? 二度とお会いすることはないと思いますけれど、東宮様にもよろしくお伝えください」
由之と之仁が座って一息吐く間もなく、結依はすっと立ち上がってその場から一歩踏み出した。
(これで何の文句もないでしょう)
結依はそう思った。
が、
一歩踏み出したとたんに結依は顔面から転びそうになった。後ろで何かが裳を引っ張ったせいで。
鍛え上げられた反射神経と運動神経でかろうじてその場に踏みとどまった結依は、体勢を立て直して何事かと振り返る。
するとそこには、小さな手で結依の裳をしっかりと掴む之仁の姿があった。
「なんで……なんでかえるのぉ……。結依はぼくのこと……きらいなの? きらいなら、ぼくいいこになるから……だからかえるなんてゆわないでぇ……」
先ほどまでの笑顔が嘘のように之仁はその瞳に溢れんばかりの涙を溜めている。
そんな之仁を愛おしく感じた結依は、腰をかがめて涙を優しく拭ってやった。
「嫌いではありませんよ。でも、わたしの姉が待っているんです。きっと心配しているはずですから、もう戻らないと……」
「あぁ、それなら……」
由之がふと何かに気づいたように直衣の袂を探る。
「先程、東宮に頼まれてあなたの姉君のところに挨拶に行ったんだ。妹君に大切な用事があるのでしばらくお借りします、とね。そうしたら、これを渡してくれと頼まれたよ」
由之は袂から小さく折った紙切れを取り出して結依に差し出す。
それを受け取って中に書いてある文字を読んだ瞬間、結依はその場に卒倒しそうになった。むしろ、できることなら卒倒してしまいたかった。
(……唯一の逃げ口上がこれでは、話にならないじゃない!!)
「姉君はなんと?」
「……中務卿宮様。一体、義姉に何を吹き込んだんです?」
結依は反対に尋ね返しながらその紙を由之に渡す。
「別に特には…………」
由之は一拍おいて綺麗な顔を見事に歪めた。そして随分と面白そうに笑ってくれる。
しかし、それも無理はない。
“既成事実さえあれば東宮妃も夢じゃないわよ。先に帰っているからゆっくりしていらっしゃい。 依沙”
問題の文にはそう書いてあったのだから。
「おもしろい方だな。内大臣家の依沙姫と言ったら、東宮妃の座を辞退したことで一時期都中を騒がせた姫だろう? 何だかそれも分かる気がするよ。私はただ、東宮から妹君に大切なお話がありますと言っただけだ。まぁ……誤解を招かなくもないか。とりあえず姉君もこう言っていることだし、ゆっくりしていきなさい」
(義姉様は……まさかわたしを中務卿宮様に売ったの?)
結依は深い溜息をついて元のようにその場に座り込んだ。
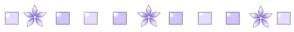
あれから一刻ほど経ったが之親は未だに戻らない。
彼さえ戻れば今度こそ結依は帰れると思っていたのに、思っているうちに時刻は既に子の刻を少し過ぎた。
どう考えても宴席は終わっているはずだが、どうしたわけか彼が戻る気配はない。
之仁は結依の膝枕で眠い目をこすっていた。幼い彼でなくとも、寝入る時間はとっくに過ぎている。
その時、結依は之仁を見ながら無意識のうちにあることを思い出していた。
それは、
(この頃、わたしは何をしていたのだろうか……)
幼い頃の自分のこと。
今にも眠りに落ちそうな之仁の姿が、なぜか昔の自分に重なったのだ。
六歳――それは結依が自らの意思とは逆に様々なことを覚え始めた頃、そしてまだ何も知らずに幸せに暮らしていた頃のこと……
途切れ途切れではあるが残っている記憶を、結依はゆっくりと思い出していた。
(六歳の時……わたしは……まだ“結依”ではなかった)
(あの時、わたしはまだ……)
「ねぇ、結依」
之仁の声で結依は現実に引き戻される。
「……なんでしょう?」
「結依はさぁ、どうしてやねのうえをぴょーんってとべるようになったの?」
「それは聞かない約束でしょう?」
結依は小さな質問者に優しく答える。
「だってぼくはさ……ゆいみたいになりたいから。だから……」
之仁は徐に起きあがり、結依の目の前でぴょんっと飛んで見せた。
(わたしのように……?)
結依は心の中で復唱する。
そして、
(……いけない)
(わたしのようにだけは……なってはいけない)
答えは考えずともすぐに出た。
自らの意志で身につけたわけではない数々の技術。それらは全て、好きや嫌いを言う前に生き延びるためにやらざるを得なかっただけのこと。
(なってよいわけがない。わたしのようにだけは……)
「……い、結依!」
結依は之義の呼ぶ声にハッと我に返り、慌てて顔を上げる。
「怖い顔。……どうかした?」
その時の之義の目は恐ろしくまっすぐで、まるで何もかもを見透かしているようだった。
「お前のその顔の裏には何が隠れているんだ?」
由之がそんな言葉を口にしながら、ゆっくりとその身を脇息から乗り出す。
「……別に何も。一介の貴族の姫に、宮様方は何をお望みです?」
結依は思い出しかけた記憶を払拭するように冷静さを取り戻す。
「そうだな……結依の過去なんてどうだ? 何かしら秘密がありそうで興味があるな。普通の貴族の姫ならば、そんなに身が軽いのはおかしいだろう」
「中務卿宮様、それは先日聞かないとお約束したではないですか」
「聞かないといったのはこの間の話。今日の約束まではしてないよ。ねぇ? 宮?」
之義が由之に便乗する。
(…………っ)
結依は奥歯をギュッと噛みしめた。
とその時だった。
「すまない。ずいぶんと待たせてしまったね」
姿を現したのは之親だった。
すぐに一同が彼に視線を傾ける。
だが、その時の之親の顔にはいつものような柔らかさはなかった。
月の光のせいではなく、彼の顔は何かがあったことを指し示すように明らかに青ざめている。
結依と由之はそんな之親の表情を見逃さなかった。
