数拍の間を経て、
ダンッ!
と、辺りに鈍い音が響き渡った。
結依が握りこぶしで勢いよく床を殴りつけたのだ。
結依はそうすることで高まった気持ちを消化しようとした。
真っ赤になった結依の右手の甲にわずかに血が滲む。しかし痛みは感じない。
力の入れ過ぎでその手が小刻みに震える。
(……やられた。……間違いない)
(……アイツだ。奴がまた……)
(あの時と……同じ…………)
結依は堅く目を閉じてその眉間に皺を寄せる。
(また……また、助けられないの……? わたしはまた、あの時と同じことを……繰り返すの?)
自問しながら結依は唇をガリッと噛みしめる。
(息が詰まる……苦しい…………)
(わたしはまた同じ……過ちを……)
『陽月サマ……』
記憶の中の女性――
柔らかく、けれど芯の通った優しい声。
もう二度とは聞くことのできない、記憶の中だけの彼女の声。
その声に結依が徐々に力を緩めると、口内でわずかに鉄の味がした。
(……違う……今度は……今度こそは…………)
「結依、一体どういうことなんだ?」
之親は俯く結依の両肩を強く掴む。
「……わたしの記憶に、間違いがなければ……主上は…………」
「主上が? ……父上が何だ!?」
やや冷静さを欠いた之親は結依の肩をそのまま揺さぶる。結依はその目をゆっくりと開き、目の前にいる之親の視線と自分のそれを合わせる。
「確実に殺されます。……事と次第によっては、一生意識を失ったまま目覚めることはないでしょう」
「父上が……死ぬ?」
結依の言葉を復唱した之義の顔からは完全に血の気が失せていた。
「毒を盛られたのは今日だけではないということか?」
そう問いかけたのは由之だった。
結依はそれにしっかりと頷く。
「長期にわたる服毒。……体が徐々に蝕まれた結果です」
張り詰めた空気が辺りを包む。
もう、誰も何も言えない。
「でも……助けてみせます。わたしが……絶対に」
結依はその場に静かに立ち上がる。
「東宮様……わたしを主上のところに連れて行ってください」
「え……?」
「率直に言います。主上をお救いするにはもう一刻の猶予もないのです。残念ながら、主上はお休みになっているのではありません。もう目も開けられないほど衰弱しているんですよ」
結依の提示した現実に空気が今まで以上に張り詰める。
結依は構わず続ける。
「之義親王様、今お召しになっている直衣をわたしに貸してください」
「……え? ちょっと待ってよ。結依、あなた何を言って……」
「時間は無いと……そう申し上げたはずです。十二単では無理だとしても、直衣を着れば女のわたしでも暗闇に紛れて何とか参内できるはずです。ですから、今すぐその直衣を貸してください」
之義は一拍おいて了承の代わりに今まで着ていた直衣と指貫をすぐに脱ぎ始める。同時に、結依はすぐさま几帳の後ろに回り、十二単を脱ぎ捨てて髪を高く結い上げた後、受け取った直衣と指貫を手際よく身に着けていく。
(絶対に、救ってみせる……今度こそ、奴の思い通りにはさせない)
(悪夢は……あの時に終わったのよ…………)
「中務卿宮様は一緒に参内していただけますね?」
「一体、主上に会ってどうするつもりだ? 参内の前に私たちには聞く権利があるはずだが」
結依は手を休めることなく支度をしながら由之と向き合うように立つ。
「解毒に行きます。今ならまだ間に合うかもしれません。いえ……間に合わせます」
「でも、解毒ならもう既に……」
「できていないんです」
結依は由之の言葉を止める。
解毒はできていない――結依にはそう断言できた。
「もし主上に盛られた毒がわたしの思うものであるならば……この国で解毒ができるのはおそらく数名だけです。……痺れがなくなったのは、解毒されたからじゃなく、感覚がもうないということなんですよ」
結依は脱ぎ捨てた十二単から御守り袋を抜き取って直衣の懐に収めた。
(まさかこれが役立つ時がくるとは……)
「さぁ、行きましょう。早い方がいいです」
「結依……お前は一体……」
その時、自分を不思議そうに見つめる之親に、結依は無意識のうちに悲しそうな微笑を見せた。
「昔、同じ毒で……大切な人を失いました。……ただ、それだけですよ」
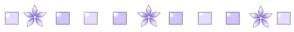
之親の手回しで清涼殿には難なく入り込めた。
黎明帝は静かに寝息を立てている。正確には、静かに死への道を歩み始めているのである。
結依が黎明帝の呼吸を確かめると穏やかで単調な呼吸が続き、それはまだしっかりとしている。
部屋の隅で待機している之親と由之は険しい顔で結依の様子を見つめている。之親の計らいですべての者を退がらせたため、ここには結依と之親、それに由之の三人しかいない。
結依は黎明帝の状態をざっと把握し、侍医が残していった調剤用の薬草に目をやった。
結依は灯台を手元に寄せると懐から先程の御守り袋を取り出し、その中から小さく折りたたまれた紙切れを出した。
灯台のわずかな光に紙の字がぼやっと映し出される。
結依はそこに書かれる薬草の名と量を順に確かめながら、再びある人物の顔を思い出していた。
(深幸……あなたの二の舞だけには…………)
◆◆◆
調剤はそれから半刻ほど後に終わった。
結依は自分の額に滲み出る汗を手の甲で拭う。そして、焦りに震える手で薬を湯に溶かし込む。
黎明帝を静かに抱き起こし、彼の上体を抱くように背中を左腕で支える。
力のない体は結依の肩に嫌な重みを感じさせる。
「主上、薬ですよ」
黎明帝の口を開けてゆっくりと薬を流し込む。
(間に合って……お願い……間に合って……)
…………コクン
結依の悲痛な願いに、黎明帝の喉がその音で答えた。
(よし、飲んだ)
再び黎明帝の体を横たえてた結依は、それから脇目も振らずに彼の様子を見ていた。
(お願い……どうか助かって……)
何度も何度もそう祈って。
それからどのくらい時が経っただろうか――時刻は寅の刻になろうとしていた。夏の夜は思っているより早い。
もうそろそろ東の空が白み始める頃である。
空気の重さに耐え切れなくなった之親と由之が黎明帝の枕元に寄って来る。
「主上は……助からないのか……?」
之親の声は低く、何かを覚悟しているような重みがあった。
「……まだなんとも…………」
結依は再び自分の額の汗を拭う。
(暑い…………)
体中がじっとりとした汗に包まれて肌に着物が張り付いている。
(まだ夜明け前だというのに……なんでこんなに暑いのかしら……)
結依は焦りを隠せなかった。嫌な結末が頭の中を何度も駆け巡る。
(駄目……なの……?)
(わたしはまた、目の前で人が死んでゆくのを見なければならないの? ……わたしはまた……救うことができないの?)
結依は床についていた手をギュッと握りしめる。
先程できた傷がズキリとわずかに痛む。
(もう死に行く人を見るのは嫌……。あの時と……同じ毒で……同じ者のせいで……)
(……もうたくさんよ…………)
結依が拳を更に握りしめたせいで、一度塞がった傷からは再び血が滲み始めた。血の色が濃くなればなるほど、結依は諦めの色を濃くせざるを得なかった。
