再び時は経過し……
それは、結依の拳で開いた傷がすっかり乾いた頃のこと。
「主……上?」
視界の隅で一瞬何かが動いたのを結依は見逃さなかった。
動いたと思われる箇所に視線を集中すれば、そこでは再び黎明帝の指先が僅かに動く。
「……主上? 分かりますか? 主上!?」
結依は黎明帝の肩や頬を軽く叩いて必死に呼びかける。
「…………ん…………」
少しの反応がある。
(間に合った……?)
しかし、意識が完全に戻らないままでは結依の心にはまだ不安が残る。
結依は黎明帝を再び抱き起こして冷めた湯をゆっくりと飲ませる。
「……之……ち……か?」
帝は結依のことを之親と誤解しているようだったが、その目を微かに開いている。
「父上! 私はここにいます。ここにいますよ、父上!」
之親は身を乗り出しす。
御簾からわずかに差し込む光が眩しいのか、黎明帝は完全にその目を見開こうとはしない。
「体は痺れますか?」
結依は黎明帝の耳元で静かに尋ねた。
「あぁ……手と足……それに背中が……少し…………」
途切れ途切れではあるがしっかりとした口調である。
「之、親……」
黎明帝はまるで縋るように結依の手を掴んだ。
意識が戻ったものの、まだ朦朧としている様子だ。
「主上……失礼します」
結依は自らの手をしっかりと握る黎明帝の手を少し強めに抓る。
すると、黎明帝は僅かに眉根を寄せ「痛い」と言葉を零し、一瞬結依からその手を放そうとした。
結依はそれを確認すると黎明帝を横たえて、未だ自分の手を握ったままの彼の手を之親に渡す。之親はそれを両手で受け取ると、黎明帝に寄り添いその顔を心配そうに見つめた。
結依はそのまま由之の方へと向き直る。
「意識も感覚も戻ったようです。痺れはまだ少し残っているようですが、これでもう命の心配はありません」
今まで険しい顔を崩さなかった由之が結依の言葉に安堵の溜息を漏らした。肩の力がすっと抜けたのが見て取れる。
結依は小さく一つ息を吐くと何も言わずその場に静かに立ち上がった。
「どこへ?」
由之がすぐに気づく。
「人目につかないうちに退散します。もうすぐ夜が明けきれば、ここへも人が来るでしょう。その時に正体不明の女がここにいると変な騒ぎを起こしますから……」
そして、結依は御簾に手をかけようとした。
が、
バッタ―ン!!
踏み出そうとしたとたん、結依の視界は一気に歪んで足が宙を舞う。
「結依っ!?」
結依は遠のく意識の中、之親と由之の声を聞いた気がした。
結依の体力と気力はこの時既に限界を迎えていた。
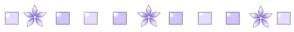
カタン……
「…………?」
今まで死んだように眠っていた結依は枕元の小さな物音にゆっくりと目を開く。すると、よく見慣れた顔が視界に入る。
(あれ……? わたし……屋敷に戻ったんだっけ?)
結依の頭はまだきちんと機能しない。
「結依様!? お目覚めですか? よかったぁ……」
結依はガバッと飛びついてきた千波を抱きとめながら、眠い目をこすってゆっくりと身を起こした。そして、ここが内大臣邸ではないことを認識する。
「お体は大丈夫ですか?」
声のした方を見ると、すぐそばにはやはり見慣れた千春の姿があった。
「千春……。ここは一体どこなの?」
「結依様、何も覚えていらっしゃらないのですか?」
結依は千春の言葉に自分の記憶を辿ってみたが、清涼殿で黎明帝の解毒を終え退出しようとしたところから今起きたところまで、すっぽりと見事なまでに記憶がない。
「結依はここがどこだか知らないよ。気絶しているうちにここに運び込んだからな」
突然御簾の内に入ってきたのは、昨晩とは異なって狩衣に身を包んだ由之だった。
「目が覚めたようだな。安心したよ」
「中務卿宮様? ……どうして?」
「ここは私の屋敷だ。今朝、倒れた結依をここまで運んだ。……それより、その子たちはお前からどういう教育を受けているんだ? もしもの時にと思って、一応内の大臣のところから呼んでおいたのだが、何かを誤解しているようなんだ」
由之に言われて結依が千波と千春に目をやると、二人は警戒心たっぷりの目で彼を睨み付けている。
「二人とも……宮様に失礼でしょう?」
「ですが……」
千波は今にも泣きそうな顔で反論しようとしたがすぐにやめた。
結依は千波や千春がどういう経緯でここに呼ばれたのかは分からなかったが、彼女たちが勘違いしている内容は何となく理解できた。
大方、結依が仕事中に中務卿宮に見つかって捕まってその上仕事がばれてしまい……このままじゃ役人に突き出されちゃったりするかも……というところだろう。
もしくは、結依が乞巧奠で由之に見初められて手込めにされて、もう逃げられない……とか。
結依は二人の様子から適当な予測を立ててみる。後者はさておき、前者の予測にほとんど間違いはないだろう。
「恐れながら、中務卿宮様におうかがいいたします。我らが主人、結依様とはどのようなご関係ですか?」
千春は床に手をつき、由之に敬意を示す形をとった。
そして、単刀直入に疑問を投げつける。
数拍の沈黙を置いて、由之は無言のまま曰くのありそうな笑みを浮かべた。その表情は何だか楽しそうでさえある。
「恋人、と言いたいところだけど貴女方には冗談では済まなそうだからやめておくよ。……そうだな、ただ私は、彼女が普通の姫君とは違うということ、そのくらいしか知らない関係だよ」
千春は、そうですか、と言って警戒しつつも少し安心したような顔を見せる。
「でもね千春、千波。……おそらく中務卿宮様には何もかもを話さなければならないわ」
「わたしたちの……すべてを……ですか?」
千波がポツリと言った。
結依は返事の代わりに深く頷く。
(そう……この人にはもう何もかもを知ってもらう必要がある。わたしたちの秘密や過去……すべてを)
もはや、由之は結依の隠し持つ全てを知らなくてはならない状況にあった。それは由之だけでなく、之親にも、そして黎明帝にも言えることだ。
結依は乱れた着物を整えて由之の前に姿勢良く座る。
「彼女たちはわたしと同様、解毒が行える者。中務卿宮様、昨夜の一件を彼女たちに話してもよろしいですか?」
由之は結依の顔をじっと見つめる。
「どうしても、話す必要が……あるのだろう?」
結依はゆっくりと頷く。
それから結依は、千春と千波に分かりやすく簡潔に今までの経緯を話していった。
先日仕事からの帰りが遅かった晩に、之親や由之たちと出会ったこと。昨晩、黎明帝に毒が盛られたということ。そして、その毒が何だったのかということ。
千春と千波は結依の顔から目を離さず、じっと話に耳を傾けていた。
