それは話がひと段落着いた時のこと。
「主上の解毒、まだ不完全ではないかと思われます。それにつきましては宇治の
いくらか険しい表情をした千春が静かに口を開いた。
「総源様?」
その時、由之は一人の人物の名を聞き逃さなかった。
「宮様は前典薬頭、
反応した由之に、結依は一人の人物の名を挙げた。
「前典薬頭といえば……確か十年前、成安の変の直後に突然辞職を申し出されたはずだが? それから宇治で出家をされたという話を噂で聞いたこともあるが……まさか……」
「そのまさかです。横堀……いえ、総源様は典薬頭だった頃、医術に精通し、この世に調合できない薬はないと謳われていたお方。今回、主上に盛られた毒の解毒剤を作り出したのはあのお方です。主上は今のままではまだ命に保障があるとは言えません。ですから、総源様を主上のそばにお呼びするべきかと」
由之は結依の話を聞きながら、ある考え事をしていた。
「それから主上付きの毒見係、親玉がいて操られているはずです。そうでなければ毒見係はもう死んでいるでしょう。あの毒は量を調節するだけで、殺すことも意識だけを無くすこともできるのです」
それはその昔、総源が解毒剤の調合法と共に結依達に教えてくれたこと。
今の状況とそれを照らし併せて導き出される答えは……
「つまり今回の親玉は、主上がどちらの状態になっても得をする者……その解釈が一番正しいでしょう」
結依が静かに言葉を止めた後、長い沈黙が辺りを包み込んだ。その間、結依の目配せで千春が静かに退出して行った。
千春の退出後、沈黙を破ったのは由之だった。
「主上が病に倒れて実権を握れなくなった時、政を操作することができるのは中宮の父。主上が御薨去なされて新帝が立った後、裏で実権を握れるのは今の政権で強大な力を持っている者。どちらに転んでも今の朝廷の全実権を手に入れることが可能なのは……」
由之は一度言葉を切って結依の顔を見る。
結依の視線もまた、由之に向けられている。
その時、今まで爽やかにそよいでいた風が一際大きく吹き、中庭の木々がザァッと葉をこすり合わせた。あまりの静けさに、その音は不気味なほど大きく響く。
その直後だった。
「左の大臣……か」
由之の低く抑えた声が辺りに響いた。
「…………」
結依はあえて何も答えない。
由之はそれを肯定として解釈する。
「それを……結依はいつから分かっていたんだ?」
「昨夜、東宮様から主上の様子を聞いた時から大体は。実際に主上の様子を見て、毒の種を同定した時には確信しました。……言いましたよね? 昔、同じ毒で大切な人を亡くした、と」
「それも……彼が?」
由之は少し躊躇いがちに尋ねる。
それに対して結依は一瞬、悲しそうな微笑みを浮かべた。
「殺された……その表現の方が正しいでしょう」
結依がゆっくりと紡いだ言葉に、千波はその両手を白くなるほど握りしめる。
「……それも秘密のひとつか? お前は……その細い腕に、一体どんな大きなものを抱えているんだ?」
「そうですね……宮様は何だと思いますか? わたしが何を抱えていると思いますか?」
質問に対して結依から逆に問い返されてしまった由之はクスリと笑みを零す。
「さぁ……何だろうな。ただ、何かとてつもなく重要なことだという確信はあるよ」
今、目の前にいる一介の貴族の姫……――
ある日突然現れた結依に、由之は恐ろしいほど危険な香りを感じていた。しかし同時に、彼は初めて会った時から結依には得体の知れない懐かしさも感じていた。
(恐ろしく危険で、懐かしくもある……この両極端とも言える感覚は一体何を知らせているのだろうな?)
由之は瞬きもせずに結依をジッと見つめていた。
(結依と出会ったのは単なる偶然か、それとも仕組まれた運命か……いずれにせよ、まだ分からぬことが多すぎる)
結依の後ろに隠された過去と秘密を、由之は未だ想像しきれずにいた。
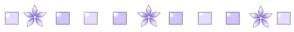
「主上に毒、か……。最近体調がよろしくなかったのはそのせいだったのか」
時峯は腰元でゆったりと手を組み、御簾越しに庭を眺めながら呟くように言った。
その傍に控えるのは千波である。
「その件につきましては、既に総源様を都にお呼びする手はずは整えましてございます。今、姉が宇治へ馬を走らせていますので数日中には」
千波は由之の屋敷から引き上げてすぐ、時峯の元へ状況の報告をしに来ていた。
「総源殿をお呼びするほどに主上の状態は芳しくないのか?」
「いえ、結依様の処置で既に意識を取り戻され、状態も安定しているとのことです。ただ、万一のためにと。今回は毒味係が関係しているようで、今後も毒が盛られる可能性は否定できませんので」
「そうか……」
時峯は答えながら小さく溜息を吐いた。
辺りに短い沈黙が流れる。
「……して、中務卿宮様は現状で結依のことをどの程度まで気づいている様子だ? ……今上帝の懐刀と謳われるだけのお人だ、それなりに感づいてはいるだろう」
「それは……まだ何とも判断致しかねます。ご本人は、結依様が普通の姫とは違うということ、その程度しか分からないと仰っていましたが、侮れないお方であるとわたくしも思います」
千波はふと由之の顔を思い出す。
由之という人間を千波はまだ浅くしか知らない。話としてそんな親王がいるということは知っていたが、会うのは今日が初めてだった。
そんな彼は、甘やかされて育てられた親王という印象は微塵も持っておらず、少なくとも千波は彼から何かもっと別の研ぎ澄まされたものを感じ取った。
「結依はこれからどうすると?」
時峯は一度振り返り、視線を千波に合わせる。
「全てを……中務卿宮様にはお話しする必要があると仰っていました。もはや、知っていただかなくてはならない、と」
「だろうな。宮様とて、もはや渦中の人物だ。……千波、ご苦労だった。もう下がって良いぞ。それから、結依をゆっくりと休ませてやってくれ。あれも突然のことで疲れただろう。それと、依沙が心配している様だから一声掛けてやってくれ」
千波は時峯に深々と一礼すると、衣擦れの音をさせながらその場を去っていった。
時峯は再び、焦点を合わせるわけではなく御簾越しの庭を眺める。
(いよいよ……動き始めたか……。十年経ってようやく…………)
その脳裏に思い出されるのは、自らの元へ引き取った頃の義娘の姿……今とは随分かけ離れたあの時の結依。
(時代も再び、動くだろうか……)
期待と不安の入り交じった複雑な感情が、その時の時峯を支配していた。
