内裏――
「左大臣殿」
朝議を終えて退出しようとした左大臣槌屋元恒を呼び止めたのは、右大臣の
「おや、これは右大臣殿。どうかなされましたかな?」
槌屋はゆっくりと後ろを振り返る。
田代は太った体を重そうに揺すりながら小走りに槌屋に近づいた。そして、その隣に立つと十分に潜めた声で話し始めた。
「左大臣殿に少々お聞きしたいことがありましてな。まぁ、あくまで噂なのですが……。宇治の横堀殿、今は総源殿でしたか? 彼が主上の元に呼ばれている、という話をある筋から耳にしまして」
「……ほぅ、総源殿が。それで?」
槌屋は一瞬、総源の名に顔をしかめたがすぐに何食わぬ顔に戻した。
「なんでも、総源殿は数日前より中務卿宮様のところに滞在しているご様子で、人目に付かぬよう日に何度も参内されているとか。主上は疲労で体調を崩された、とのことですが、あの総源殿を宇治から呼ぶほどにお悪いのでしょうか。中宮様のお父上であるあなた様の事ですから、何かご存じかと思いまして」
「中務卿宮様が総源殿をねぇ……。それは初耳ですなぁ」
槌屋が返したのは全く以て手応えのない答えだった。田代はそれに少しがっかりした様子を見せる。
「そうですか。左大臣殿がご存じないなら根も葉もない噂ですね。わざわざ足を止めさせてしまい、申し訳ございませんでした」
田代は、それでは、と言ってその場を後にした。
立ち去る田代を槌屋は険しい表情でじっと見つめていた。
(……やはり、単なる噂ではないのか)
先ほど田代には初耳だと答えたが、槌屋も似たような噂をここ数日で何度も耳にしていた。
しかし“中務卿”という名は槌屋にとって本当に初耳であった。
「そうか、中務の宮様が動いたか……」
槌屋は誰にも聞こえないほど小さな声で呟き、その視線を頭上に広がる空へと移した。
眩しさで一瞬目を細める。
(もう少しで主上も意のままに操れたのに……中務め、邪魔をしおって)
その時、槌屋の視界を一羽の鳥が横切った。
槌屋はその鳥を凍てつくような視線で見つめる。
(……片羽をもいでしまった方が、すぐに落ちるやもしれんな)
槌屋は深い皺が刻まれたその顔をわずかに歪め、クツクツと不敵な笑みを漏らした
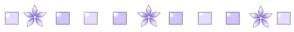
結依はなかなか寝付くことができなかった。
今宵は由之の屋敷で床を用意してもらい、之親も之義も之仁も今夜はここに泊まっている。結依の隣では「結依といっしょにねるんだ」と譲らなかった之仁が気持ちよさそうに寝息を立てている。
久しぶりに昔の話をしたせいで気持ちが高ぶっているのか、結依は眠りにつくような気分ではなかった。しばらく床の中で寝返りを繰り返したが寝付ける気配はない。
やがて、結依は小袖姿に袿を一枚羽織って高欄まで出て行った。
外は辺り一面、月の光で明るく照らされている。
結依は高欄に寄り掛かるように腰掛けた。
とても静かで物音ひとつしない。雲のない空を見上げると、この世のすべてを支配しているかのように月が堂々と輝いている。
深幸が息を引き取った日も今宵のように月の美しい夜だった。
嘉月たちが亡くなった日も同じ……怖いほど静かな夜だった。
結依は目を閉じた。
(あれからもう……十年も経つのね……)
ふと、陽子の顔が結依の脳裏に浮かぶ。
(……母上、あなたは今どこにいらっしゃるのですか? 娘がこんなに成長したこと……ご存じですか?)
(……生きて、どうか生きていて……母上。……あなたに会いたい)
結依は祈りを込めるように手を組んで握りしめた。
その時だった。
「眠れないのか?」
突然聞こえた声に、結依はゆっくりと振り返った。
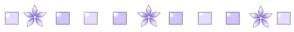
「今宵も月が美しく輝いていますね」
由之は高欄のそばに立つ総源に話しかけた。
「宮様ですか……。陽月……結依殿から、聞いたのでしょう?」
「ええ……十年前のすべてを」
「そうですか……」
総源は溜息のような深い息をついた。
「あの日も、今宵のように月の美しい静かな夜でした」
「え……?」
「嘉月……前左大臣が捕らえられた晩です。事の次第を知って私が駆けつけた時には、嘉月は既に連れて行かれた後でした。髪を振り乱した陽子殿がただ呆然と立ち尽くしていたのをよく覚えています。その傍にぴたりと寄り添っていた幼い結依殿も」
「…………」
由之は黙っていた。
「宮様はずいぶん嘉月を恨んだでしょう? ……実の兄を突然奪われたのですから」
「そうですね。ただ……最初は、彼がやったなんて思いもしませんでしたよ」
総源は由之に視線を移した。
「しかし……噂や刀の物証で恨まずにはいられませんでした。冷静に考えれば、そんなものはいくらでも偽造できたのに……。兄は兄弟内でも母が同じだった分、私を特別かわいがってくれていました。だから余計に……兄を奪った者が憎かった。憎くて憎くてたまらなくて、あんなに自分たちに尽くしてくれた彼を……憎んだのです。彼を信じて疑わなかった先帝や今上帝さえも憎みました。馬鹿な話です。それでも……私は誰かを憎まずにはいられませんでした」
由之は一度話を切って月を見上げた。そして当時の自分を静かに思い出していた。
(私は……兄の死を認めたくなかった……)
由之はただそれだけで嘉月を憎んだ。憎む、という行為を持たねば、その時の由之は兄が亡くなったことを納得できなかったし、彼の死により空いてしまった心の穴を埋めることができなかったから。
(……単に弱かったんだ。一時の感情にのみ、左右されてしまった脆く弱い自分……)
(馬鹿らしい……)
由之は自らを叱責するように溜息をひとつ吐いた。
「実は、今宵結依に聞くより先に私は全ての首謀者を知っていました。……初めてそのことを知った時には、無実の嘉月を憎んだ自分に怒りがこみ上げました。そして……後悔をしました。今日、結依の話を聞いて再び後悔の念を覚えましたよ」
すっかり俯いてしまい、酷く悲しげな表情を見せる由之を総源は優しい目で見ていた。
「宮様……あまり気に病んではなりませんよ」
由之は総源の声に少しだけ頭を上げる。
「嘉月はね、我々の仲間内でも一等心の広い男でした。そのくらい許してくれるでしょう。それにね、そんなに気に病むとかえって嘉月を悲しませてしまいますよ」
総源の言葉に、由之の胸には不意に熱いものがこみ上げてきた。
――分かっていた
嘉月が心の広い優しい男だということくらい、由之も初めから分かりきっていたのだ。
いくら自分が憎んだとしても、嘉月はそれを笑って許してくれる男だ。
『誤解が解ければ、それでいいんですよ』
そんな台詞さえ聞こえてきそうな程に、由之は嘉月を分かっていた。
だからこそ、由之は嘉月を憎んでしまった自分を許せなかった。彼を信じ抜くことができなかった自分を悔やんだ。そして、なんて愚かな人間だ、と何度も自らを罵ったのだ。
奥歯を噛みしめて涙を必死に堪えようとしている由之を、総源は穏やかな表情で見つめていた。
「成安の変から十年、嘉月が亡くなって十年、先帝が退かれて今上帝の御世になって十年……。十年前は色々なことがすべて動いた年でした。私も仏門に入り、陽月殿も“結依”になった……」
「総源殿は……なぜ仏門に?」
「…………」
由之が投げかけた問いに、総源は黙っていた。ただ月を見上げ、静寂にすべてを任せるかのように。
由之もまた、答えを急くことはなかった。
「すべてに……何もかもに疲れてしまったのですよ」
しばらくの沈黙を経て、総源はゆっくりと話し出した。
「十年前、私は友を救うことができませんでした。自分の無力さを悔やみ、彼を失った悲しみに苦しんで……逃げ場がなかったんです。典薬頭という地位も名声も無意味に感じ、何もかもを捨てて出家をしました。すべてを捨ててしまえばもう一度やり直せるような、そんな気がしたのです。……嘉月の菩提を弔うため……そう言ったら聞こえはいいでしょう。でも、実際はそんな綺麗事ではありません。私は逃げたのですよ。世を舞台とした人と人との醜い争いからね。逃げずには……いられなかった……」
ある日突然、親友が目の前から姿を消した。
親友はとても理不尽な理由でその命を奪われたのだ。
総源はあの時の喪失感と彼を守りきれなかった無力さを、十年たった今でも鮮明に思い出すことができる。すべてを捨てたはずの今でも、それはしっかりと刻み込まれている。
(決して忘れることのできない出来事、忘れることを許されない出来事……だな)
総源は静かに目を閉じた。
二人の間に再び沈黙が走る。
静けさだけが辺りを支配していた。
