「じゃあ、深知留……お母さん行くわよ? 本ッ当に独りで大丈夫なのね!?」
「今更何言ってるの? 何とかなるって」
深知留はフッと笑みを零しながら答える。
「今更でも、もし駄目ならお母さん今からでも上司に説明して……」
「大丈夫。三ヶ月くらいどうとでもなるから」
「そりゃ確かに三ヶ月だけど、ちょうど深知留の誕生日が……」
「だから? 心配しなくても大丈夫。それに、せっかくお母さんが掴んだチャンスでしょ? イギリスでも精一杯自分の能力を発揮してきて」
深知留は多英子の言葉を遮るように言った。
「深知留……」
「そんな泣きそうな顔しないの。湿っぽいのは嫌。何かあったら教えて貰った電話番号に掛けるからそんなに心配しないで。メールだって毎日送るから」
場所は都内近郊にある国際空港。
深知留は平日の午後、学校を早退してこの空港まで来ていた。母、多英子を見送るために。
多英子は今日から三ヶ月間イギリスへ長期出張に出かける。一人娘の深知留を日本に残して。
深知留の父はいない。
彼女ががまだ多英子のお腹にいる時に事故で亡くなったのだ。
多英子は結婚前から外資系の会社に勤めるバリバリのキャリアウーマンで、深知留を産んでからも再婚をすることもなく、女手一つで子育てをしながらその実力でのし上がっていった。
元々語学が堪能だった多英子は昔から短期での海外出張によく行っていた。しかし、長期のものは深知留の子育てを理由に断り続けていたのだ。
もちろん、多英子は深知留には嘘をついていた。『長く行くと疲れるのよ』そんな適当な理由を付けて。
やがて、多英子の元には長期出張のオファーも来なくなったが、今回は数年ぶりに部長直々に頼まれたらしい。この仕事が成功すれば多英子は昇進が約束されていた。女性では希な部長職への就任だ。
だから深知留は多英子が悩む前に言った。『ねぇ、行っておいでよ』と。
深知留も今年でもう二十三歳の大学院生、ちょっとやそっとでのたれ死ぬような子供ではない。
『学歴はあっても困らない』という多英子の教育方針から、深知留は未だ学生という身分である。しかし、同じ歳で考えれば多くの人は働いているし、結婚をして子供がいる人たちだっている。
それらは多英子も十分理解しているはずなのだが、これまで親子二人でやってきて、どちらとも親離れ子離れができていないせいか多英子はどうも深知留を子供扱いしているところがある。
「本当に大丈夫だから。ほら、遅れるからもう行って」
「うん。じゃあ……お母さん、行くわね。メール待ってるから」
「がんばって、お母さん!!」
深知留は精一杯の笑顔を見せながらイギリスに旅立つ多英子の背中にいつまでも手を振っていた。
やがて、多英子の背中が見えなくなった頃、深知留の中ではどこからともなく寂しさがこみ上げてくる。
よくよく考えれば三ヶ月という長い間、多英子と深知留が離ればなれになるのは初めての経験である。
人に話せば二十三にもなって……と笑われるかもしれないが、それは深知留に何とも言えない寂しさを感じさせていた。
「たったの九十日でしょ……。お母さんの好きなこと……させてあげられるんだもの、いいじゃない」
そう自分に言い聞かせながら、深知留はこみ上げる寂しさを振り払おうとする。
お母さん、多英子の好きなこと……それは他でもない仕事である。
多くの人は、母子二人が生活していくためには多英子が仕事をしなければならなかった、という見方をするが、それだけではなく多英子は心から仕事が好きで誇りをもって取り組んでいた。
深知留はそんな多英子が大好きで自慢だ。だから、今回も何とかイギリスに行かせてあげたかった。
何より、もう自分を理由に多英子から仕事のチャンスを取り上げたくはなかったから。
「三ヶ月なんて、すぐだよ、すぐ。あっという間なんだから」
深知留は再び自分に言い聞かせながら、母の背中が消えた方向をもう一度だけ見て踵を返した。
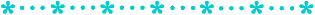
今日の空港はやたらと混み合っている。
季節はまだ十月初旬で海外旅行シーズンでもないのに、大きなスーツケースを持った人たちでフロアは溢れかえっている。
そんな中深知留は、すみません、と言いながら様々な方向に進む荷物と人の間をよろよろと歩いて行った。
ここが国際空港であるためか、深知留が見上げるほどに大きい外国人も多く歩いている。一六五センチで平均よりは大きいはずの深知留でも、人と荷物に押しつぶされないようにするのが精一杯だ。
一端、途切れた人の波に深知留は思わず溜息を零す。
そして、再びやってくる人の波に備えて深知留は鞄を胸の前で抱えて体を小さくまとめた。
人混みに呑まれそうになりながら、深知留は先ほどと同じようにゆっくりと足を進めていく。気分は差詰め朝の満員電車だ。
と、その時、
ブブブブ……ブブブブ………
深知留は鞄の中でマナーモードにしてあった携帯電話がいつの間にか震えていたことに気づく。
「もしもし?」
『あ、深知留さん!? 』
電話の相手は研究室の後輩、
『今どこにいます? 空港? それとも家? 』
電話の向こうの真尋は随分と焦っている様子だ。
「まだ空港。真尋ちゃん、一体どうしたの?」
『お願いです。深知留さん。最速で研究室に戻ってください!! 機械が壊れちゃったんですよぉぉ!! このままじゃわたしの培養細胞が死んじゃうぅぅぅ』
真尋は半分パニック状態らしく、でそれだけ言うとそのまま電話を切ってしまったのだ。
電話が切れた後、深知留は研究室に誰か人はいないのか、と考えてみるが、教授・准教授・それに先輩たちは揃って学会に出かけている真っ最中。おまけに講師の先生は風邪で病欠中だったことを思い出した。確か教授秘書のお姉さんはいたはずだが、彼女に機械を直せと言うのは無理な話である。
(そうか……研究室、今真尋ちゃん一人なんだ。どうりで焦るはずね)
深知留は携帯電話を鞄にしまい、家ではなく研究室に向かうべく方向転換をする。
そして足を踏み出そうとした時だった。
「痛ッ……」
深知留は何かに髪を引っ張られ、その衝撃で同時に頭全体がクッと引かれたのだ。
引かれた方向に目をやると、深知留の長く伸びた黒髪の一房が何かに絡んでいた。
「……申し訳ない」
突然頭の上から振ってきたバリトンの声色に深知留は顔を上げる。
(――――)
一瞬にして、深知留はその視線を奪われる。
(日本人……?)
視界に収めたものに対し、何より先に深知留の頭を支配したのはその疑問だった。
