「とりあえず、電話してみたらどうです? 御曹司かもしれない人がご丁寧に携帯番号まで書いてくれちゃってるんですから、ね?」
あまり乗り気でない様子の深知留を促すように真尋は身を乗り出す。
「しかもこれ、個人持ちの番号じゃないですか? 会社用のは別に印刷されてるし」
「あ、ホントだ」
深知留は真尋の指摘を受けて改めて名刺を見る。
そこには、真尋の言うように昨日環が走り書いた番号とは別の物が、活字として既に印刷されていた。
「あ、そうだ……そう言えば、龍菱さんコレ落としたんだよね」
深知留は思い出したように鞄のポケットからピンバッチを取り出す。
昨日、深知留が家に帰って鞄を開くと、見た覚えのあるピンバッチが目に入った。
いつの間に鞄に入ったのかは気づかなかったが、恐らく髪を切る時にでも鞄の中に零れ落ちたのだろうと想像した。
「それ、社員バッチですよ!」
真尋はすぐに反応した。
「社員バッチ、なの?」
「はい。系列会社も含め菱屋グループの社員はみんな支給されるみたいですよ。彼氏も持ってます。ただ、コレと色は違いますけど。彼のはこのHが青色だったかな。菱屋のHらしいですよ」
真尋はピンバッチの中央に描かれたHの文字を指差す。
「へぇ。じゃあ色んな色があるのかな」
「さぁ。階級別とかですかね? 確かに、偉くなるに連れて色が変わる、って可能性はあるかもしれませんよ。いずれにしても、これも返さなきゃですし、連絡取ってみたらどうです? ね? 深知留さん」
いつになく浮き浮きする真尋を見ながら、深知留はうーんと否定でも肯定でもない返事をした。
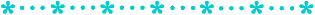
「終わったー」
セミナーを終えた深知留は腕を一杯に伸ばして背伸びをした。
深知留のいる研究室では教員や配属学生により、定期的にセミナーが開催されている。それは一年に数回ずつそれぞれに振り分けられており、今日は深知留がみんなの前でプレゼンをする当番だったのだ。
研究室のセミナーくらい、と侮る事なかれ、深知留の教授は完璧主義者で妥協を許さない。そのため、いかなる質問が来ても耐えきれるように、順番のあたった者は念入りに準備に当たるのである。特に学生に限ってはそれが単位に関わるとくれば手抜きなどできるはずもない。
おかげで深知留はここ数日睡眠不足だ。しかしそれも今日でようやくおさらば。これを終えた深知留は年内は大きな学会も急ぎの実験もないため、あとは卒業に向けての論文に打ち込むだけである。
「お疲れ様です、深知留さん」
セミナーの後かたづけを手伝っていた真尋が労いの言葉をかけた。
「お手伝いありがとう、真尋ちゃん。今日この後は? 良かったらご飯でも食べに行かない?」
「あー、あと一時間ほどで実験データが出るんで、その後は
真尋は少し照れくさそうに彼氏の名を呼んだ。
「相変わらずラブラブだね。ごちそうさまです」
「へへ、もうすぐ二年記念なんです。そうだ、もし良かったら深知留さんも一緒に食事でも行きません? 涼も一度くらい深知留さんに会ってみたいって言ってましたし」
真尋は良いこと考えた、とばかりにその手をポンと叩く。
深知留は真尋の彼氏、
「駄目よ。わたし、恋人達の邪魔をしたくはないし」
深知留は片づけた資料やらパソコンやらを真尋から受け取り、自分の机の上に置く。
「邪魔なんてとんでもない。深知留さんなら大歓迎ですよ。ね? 遠慮しないで。それに、そのうち涼の同僚も紹介したいんです。深知留さん、確か今フリーですよね? 深知留さんのこと前にチラッと話したら、凄い興味を示した人がいたんですよぉ」
「フリーだけど……遠慮しておく。それに久しぶりのデートなら二人で仲良くする方がいいじゃない。わたし、やっぱり今日は帰って寝るから。セミナーのおかげで夕べは貫徹だしね」
断る深知留に真尋はいくらか残念そうな顔をしたが、じゃあまた今度、と言って実験用白衣を羽織って部屋を出て行った。
深知留は真尋を見送ってから、持ち帰るべきモノを揃えて鞄に詰め込もうとした。
そして、鞄のファスナーを閉じようとしたちょうどその時、深知留の目にあるものが飛び込んできた。
「あ、忘れてた……」
深知留は目に入ったそれ、あの例の社員バッチを手に取る。
今の今まで深知留はその存在を完全に忘れ去っていた。
お詫びをさせるのはともかく、その社員バッチだけは返さなきゃいけないと深知留は思っていたのに……。あの時、彼が一週間後で無ければ帰国しないと言っていたので、後で連絡すればいいと放っておいたのだ。
そうこうするうちにセミナーの準備に追われてしまい、深知留はすっかりその存在を忘れ去った。
「あーあ、どうしよう。すっかり忘れてた……」
今日は既に、あの出会った日から数えると二週間近くは経っている。
「送ればいいか……」
深知留は一緒にしまってあった名刺を取り出して独り呟いた。
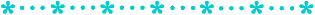
「寒くなったな〜」
深知留は学校の玄関を出ると、吹きすさぶ北風の寒さにその身をブルッと震わせる。
あっという間に十月も下旬に突入してしまい、季節はすっかり秋真っ盛りとなって最近朝晩はすっかり冷え込むようになった。
結局、深知留はいつもより早めに学校を切り上げてその途中で郵便局に寄ることにした。もらった名刺にある会社の住所に社員バッチを送ろうと決めたのだ。
書いてもらった番号に電話をしても良かったが、それでは婉曲的にお詫びを要求しているようで深知留は嫌だった。かといって、社員バッチをこのまま持っているというのも変な話である。
と言うわけで、手っ取り早く郵送することにしたのだ。
本当はあれだけのイイ男なら、もう一度くらい環に会っても損はないかも、と深知留は思ったが、仮に蒼が言ったように彼があの菱屋グループの一族であるならば、所詮生きる世界が違う人だ。
深知留は着ていた薄手のコートの前をしっかりと合わせて足早に歩き始める。
やがて校門に近づくと、数名の学生がある一方向を注視している事に気づいた。
深知留が彼らの視線と同じ方向を見ると、そこには一台の車が止まっている。それはどこからどう見ても高級外車で、車に関してド素人の深知留でもそれが相当良い車だということが感じ取れた。
(誰かの彼氏? 随分お坊ちゃんな彼氏だこと)
深知留はそう思いつつも、特に気にもとめず足を進めた。
そして、ちょうどその高級外車の真横を通り過ぎた時、
「君!」
深知留の背中に振りかっかった声は、耳に心地よく響く男性のものだった。
しかし、深知留はまさか自分が呼びかけられたとは思わず歩み続ける。
彼女が止まらないことを悟った車中の男性は、車の窓から身を乗り出す。
「ちょっと待って!」
再度の呼びかけにもかかわらず、深知留は止まらない。
男性はチッと小さく舌打ちすると、すぐに車のエンジンをかけて発進させた。
深知留は相変わらず歩みを進めている。
しかし、車のエンジン音が真横で聞こえたのはそれからすぐのことだった。
「…………?」
自分の隣に横付けされた高級外車に深知留は意味を解せない。
しかし、さすがにその歩みは止める。
(わたしに……用なの?)
(……何か、悪いことしたっけ……?)
深知留の脳裏に一瞬にして嫌な予感が走る。
そうこうするうちにウイィンというパワーウィンドの音がして車の窓が開く。
「良かった、やっと止まってくれた」
聞こえたのは深知留が予測していた怒声ではなく、優しく落ち着いたものだった。
そして、その声は聞き覚えがあるもので。
「あ……」
声に続いて窓から出された顔に深知留は小さく声を漏らす。
「やっぱり。君、この前空港で会ったね?」
男性はようやく止まってくれた深知留ににっこりと笑いかけた。
