深知留がそれに気づいたのは翌日朝の事だった。
朝の寒さにコートのポケットに手を入れたところ、それはあった。
「うーん。何で忘れるかなぁ、わたし」
深知留は何故かポケットに入っていた社員バッチを目の前で摘んで見つめる。
昨日、環を待っている間、鞄のポケットから取り出して手に持ったところまでは記憶に残っていた。しかし、その後何を思ってポケットに入れたのかまでは覚えていなかったのだ。
(まぁ、無くさなくて良かったけど……)
深知留がそう自分に言い聞かせた時だった。
「あれ、深知留さんまだそれ返してなかったんですか?」
「あ、真尋ちゃん。おかえり」
昼休憩中、窓辺の自分の席でひなたぼっこをしていた深知留の元に、食事を終えて戻ってきた真尋が声をかけた。
「深知留さん、もしかしてソレ、昨日彼からもらったんですか? 『俺の代わりにそばに置いて欲しい』とか何とか言われちゃって?」
「ないから。違うから。返し忘れただけだから」
少女マンガよろしくの台詞を言ってキャーと頬を紅潮させる真尋を、深知留はバッサリと切る。
真尋は昨日深知留が環と会ったことを既に知っている。
むしろ、深知留が報告する前に知っていたと言っても過言ではない。
今朝の段階で、昨日深知留が高級外車に乗る男とどこかに行った、という噂は研究室中を駆けめぐっていたのだから。
どうやら、深知留が車に乗った所を研究室の先輩が見ていたらしかった。
おかげで噂を聞きつけた先輩たちに深知留は今朝一番で『彼氏、お坊ちゃんか?』と聞かれた始末である。
まぁ『お坊ちゃん』の部分は間違えてはないが、深知留は面倒だったので『親戚のお兄ちゃんです』を貫いた。
もちろん、環を知っている真尋にそんな嘘は吐いていない。誰にも言わないでよ、と口止めをした後で深知留は真尋に昨日の出来事を話して聞かせた。
ブランドショップに連れて行かれたことも、チョコレートを買ってもらったことも、車の中で寝てしまったという失態も……。
「深知留さん、やっぱりもう一回龍菱さんに会うしかないですって! 絶対運命ですよ」
「それ、朝も聞いたけど……」
今朝、深知留の話を聞き終えるなり真尋は言った。
『これはもう運命です。もう龍菱さんに的を絞りましょう!! とにかくもう一度会わないと!!』
と、興奮気味に。
「ねぇ、深知留さんあの名刺まだ持ってます? もう一回見せてもらえませんか?」
「いいけど……」
深知留は突然の真尋の願いを不思議に思いながら鞄から名刺を出して渡す。
「そうそう、これ今度始める実験のプロトコールなんですけど、変なところがないか確認してもらえません? この分野、深知留さん専門でしたよね?」
真尋は突然思い出したように机のファイルから一枚の紙を取り出し、名刺と交換に深知留に渡す。
この時の深知留は、真尋の考えているとんでもない事など知るよしもなかった。
真尋は名刺を受け取り、深知留が自分の渡した紙に見入るのを確認すると、彼女の机に無造作に置かれていた携帯電話を音を立てずに持ち上げる。
そして、名刺に乱雑に書かれた番号を確認しながら深知留の携帯電話でそこへ発信する。
一応、深知留に悟られないよう真尋は俯き加減に彼女とは逆方向を向く。
受話器から何回か呼び出し音が聞こえた後、
『もしもし』
とバリトンの心地よい声が真尋の耳に響いた。
真尋は心の中でガッツポーズをする。
「もしもし? 龍菱環さん、ですよね?」
『はい、そうです。失礼ですが、どちら様でしょう?』
「深知留です。天音深知留。……ごめんなさい、電波が安定しないのでちょっと待っててもらえます?」
『え? 深知留ちゃん?』
真尋はそう言って、環の返答も聞かずに携帯電話の通話口を押さえたまま深知留を突く。
「なに?」
深知留が実験のプロトコールから目を上げると、真尋は何故か自分の携帯電話を持ってにんまり笑っていた。
「はい。龍菱さん。次の約束取りつけてください」
(――――!?)
真尋の口から出た言葉に、深知留はその手から紙をはらりと落とした。
「ちょ、ちょっと真尋ちゃん!? 一体何を……」
「ほらほら。待ってますよ?」
深知留は真尋に文句を言いたいのを堪えて携帯電話を受け取る。
「も、もしもし!? 龍菱さん? すみません。お待たせしました」
深知留は通話口で早口に謝り、一緒に頭を下げながら部屋を出た。
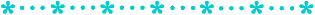
「義姉さん!」
環はリビングの扉を荒々しく開いた。
「あら、環さん。今日はお早いのね」
環の義姉、
鈴はこうして環が自分を訪ねてくることを既に予測済みだったのか、特に動じることもなくニコニコと笑みさえ浮かべている。
鈴の合図で彼女のすぐそばに控えていたメイドが一礼をしてスッとその場から下がる。
「どういう事ですか?」
環はコーデュロイの生地で品良く表装された本を一冊鈴に差し出す。
「
「そうではなくて。俺はどうしてそういうことになっているのか、と聞いているんです」
バン!
声を荒げた環はコーデュロイ地の本、お見合い写真を鈴の目の前にあるテーブルに乱雑に置く。
「この話は兄さんに直接断ったはずです」
「えぇ。その旨は主人から聞いてるわ。無理強いするなとも言われてる。だから、わたしも環さんの意見を尊重して一度は蓮条さんにお断りしたわよ。でも、」
鈴は一度言葉を止めて、今まで持っていたティーカップをテーブルの上のソーサーに置く。
「先方が一度会うだけでも、とおっしゃっていて譲らないんですもの。瑞穂さんは綺麗な顔をしてる方だし、会ってみる価値はあると思うけれど。それに、彼女は環さんが随分お気に入りのようよ?」
「会ったところで返事は変わりません。そもそも、俺はまだ結婚する気はありませんから」
環は無表情のまま言った。
「別にわたしは今すぐ結婚しろとは言っていません。でも、どうせ断るにしても、一度会ってから断ってもいいのでは無い? このまま、会わないの一点張りでは相手も納得しないでしょうし、何より
「それは……」
突然出された兄の名前に、環は言葉に詰まる。
自分の勝手で雅に迷惑を掛けることになるのよ、と言われてしまうと環が強く出られないことを鈴は全て計算済みなのだ。
外見は驚くほどふわふわほよほよしているにも関わらず、鈴は要所は確実に押さえる賢い女だ。掴み所のなさは外見通りでもあるが。
環はこの義姉、鈴がどうも苦手だった。
悪い人ではない……ということは分かっているのだが、とにかく鈴は自分の夫である雅至上主義であり、それがなんとも厄介なのだ。
今回に限らず、鈴にとっては端から環の感情なんて関係ない。全ては雅の幸せのために、それだけが彼女の目的なのだ。
先にも言った通り、今回は、環に無理強いをするな、と雅が言ったから鈴はそれに従っているだけで、もしも環の結婚により雅が利益を得られるならば、鈴は勝手に婚姻届を出すくらいのことは平気でする女だ。もちろん、外見からは考えられないが。
それも全て雅への愛、と言えば聞こえはいいが、巻き込まれる方はたまったもんじゃない。まぁ、大概は鈴の特性を知っている当の雅が、今回のように鈴の暴走を抑制すべく布石を打っておいてくれるのだが。
しかしある意味、そのくらい愛されるのも悪くはないかも、と環は最近になって思うようになった。まぁあくまで余談であるが。
「とにかく、今度の土曜日に会っていただければ、その後はわたしが丁重にお断りするわ」
鈴は、もう話は済んだ、とでも言いたげに再びティーカップを取り口を付ける。
「本当にお断りしていただけるんですね?」
「もちろん。何とか適当に理由を付けて、角を立てず尚かつ諦めていただけるよう善処するわ。でも、環さん、あなたももう三十一なのだから、いつまでも独身主義が通用するとは思わないことね」
環は鈴の言葉の後ろ半分は背中で聞きながらリビングを後にした。
