凄まじい音と共に、深知留は瑞穂を庇って池にその身を落とした。
すぐに深知留の全身を刺すような冷気が包み込む。
一瞬、何が起こったのか、本人はもちろんその場にいた誰もが理解できない。
深知留が驚きで息を吸うと、口と鼻からは何とも言い難い生臭い水が入り込んできた。
(苦……しい…………)
叫びたいが、深知留の声は出ない。
「深知留!!!!」
遠くの方で誰かが自分を呼ぶ声を深知留は既にうつろな意識で聞いていた。
(……環……さん?)
深知留は声の主を判断しながら、苦しさに水中で藻掻く。しかし、水を含んだ着物は重みをまして彼女の体力を奪い、その身体を次第に水底へと誘う。
(あー、着物駄目になる……高いのに……)
やがて深知留はどうでもいいことを考えながら、苦しさと寒さにその意識を手放した。
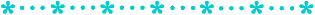
(頭が朦朧とする……)
深知留は重い瞼を押し上げようとしながら思った。
おまけに体が鉛のように重い。
一体何なんだ、と思うが今の深知留にはそれを考える思考能力すらない。
「深知留? ……深知留!?」
自分を呼ぶ声の主を捜そうとするが、深知留の視界は曇っていて周りがよく見えない。
深知留がやっとの事で重い右手を伸ばして空中を探ると、ひんやりとした誰かの手が彼女のそれを優しく包んでくれる。
深知留はなぜだかとても安心して再び意識を手放した。
◆◆◆
環は深知留の眠るベッドサイドで、深知留を見つめていた。
点滴のルートをつながれた深知留の腕が何とも痛々しい。
深知留は頬を上気させ、荒々しい呼吸を続けている。
熱が高くて苦しいのだろうが、環にはどうしてやることもできない。
「深知留……」
環は自分の両手を組み、祈るように力を込める。
深知留はもう二日ほど目を覚まさなかった。正確に言えば、何度か目を開けるようなそぶりを見せたがすぐに眠りに落ちてしまう。
寒さが身に染みるようになったこの季節に、池に落ちたということは自殺行為に近い物があった。しかもあの日は、この秋一番の冷え込みだったのだ。
氷の張るような真冬でなかったのがせめてもの救いだったが、着物を着せていたために深知留を池から引き上げるのには時間が掛かり、それから救急車で病院に運ぶのにも更に時間がかかった。
幸いにも深知留は特に外傷はなかったが肺炎を起こしたようだった。
『下手をすれば心臓麻痺で死んでいましたよ……』
深知留を見た医師は開口一番にそう言った。それを考えれば、深知留は運が良かったのだと思う。
環は仕事を全てキャンセルして深知留のそばに付いていた。その時の環は、それでどれだけ今後の仕事に支障が出るのか、そんなことを考える暇がないほどに彼女を心配していたのだ。
(俺があんな事を頼まなければ……)
そうやってここ数日、環は何度も自分を責めたことだろうか。
しかし、今更責めたところで取り返しの付くものではない。
「深知留……ごめん」
環は深知留の苦しそうな寝顔に何度目か分からない謝罪をする。
その時だった。
深知留の瞼がわずかに上がったのを環は見逃さなかった。
「深知留? ……深知留!?」
環は深知留の耳元で繰り返し名を呼ぶ。
やがて、深知留は力なく右手を伸ばして何かを探るような仕草を見せた。
(悪い夢でも見ているのか……?)
そう思うよりも先に、環は深知留の手を握っていた。
温かい、というより熱い深知留の体温が環に伝わる。
それに安心したのか、彼女は再び固く目を閉じた。
コンコン……
それからすぐに、扉をノックする音が聞こえた。
「失礼致します。深知留さんはまだお目覚めになりませんか?」
病室に入ってきたのは政宗だ。
「まだ……時々うっすらと意識は取り戻すが、完全にはな」
「環様、お屋敷にお戻りになって少しお休みください。深知留さんには誰か別の者を付けましょう」
政宗の申し出に環は無言で首を横に振る。
「そんな調子で環様はもう二日もここにいらっしゃるんですよ? このままでは環様が……」
「政宗、お前は俺に小言を言うためにここに来たのか?」
環は深知留から視線を逸らさずに遮った。
「いえ……今また、蓮条様がご夫妻でお見えになりました。深知留さんへ謝罪とお見舞いをしたい、と」
「帰ってもらえ」
環は短く答える。
「大体、年端もいかない子供でもないのに、当事者の瑞穂さんを差し置いて両親が謝りに来るのはどうかと思うが?」
怒りを抑えたような環の低い声が静かな病室に響く。
「ですが、昨日からもう二度もお引き取りいただいて……」
「何度でも関係ない。俺は彼らに会う気もないし、そもそもこんな状態の深知留に会わせる気もない」
環は深知留の手を握りしめながら、消え入りそうな声で言った。
政宗はそんな環にそれ以上何も言うことができなくてそのまま病室を出て行った。
◆◆◆
再び深知留が覚醒しそうになったのは翌日の明け方だった。
「……ん」
深知留の掠れた声で、うとうととしていた環は一気に目を覚ました。
「深知留!?」
環が深知留の顔をのぞき込むと、彼女はその眉根に皺を寄せている。
「……ず……たい…………」
「何?」
深知留が言葉を発したが、環はそれを聞き取れない。
「どうした?」
「……お……ず……たい……の……」
環は歯痒さに深知留の頬に手を当てる。
「わからない……。深知留、もう一度言ってごらん?」
「お……み、ず……飲み……た……い」
懸命に絞り出した深知留の声を聞き取りながら環はすぐさま床頭台へと目をやる。数分前に見回りに来た看護師が『目が覚めたら少し飲ませてください』と言って置いていった吸い飲みが視界に入った。
深知留の頬に手を添えた環は、吸い飲みの飲み口を彼女の唇に当ててゆっくりと傾ける。
やがて、深知留の口内に水が到達する。
が、
「……ン……ケホ……」
巧く飲み込めないのか、深知留は苦しそうに咳き込み、口角からは水が零れ落ちる。
環は驚いて、深知留の口から吸い飲みを外す。
しばらくして収まったのを見計らった環は、再度吸い飲みを深知留の唇に当て傾けた。
「……ク、ケホ……ケホ……」
やはりうまくいかない。手慣れない環はどうしてやっていいのかも分からない。
深知留は終いに嫌がって、吸い飲みから顔を背けてしまった。
咳き込み、苦しんだ深知留の目から一筋の涙がこぼれ落ちる。
それを目にした環に、もう何かを考えている余裕は無かった。
環はすぐさま吸い飲みの水を自分の口に含み、すっかりカサカサに荒れてしまった深知留の唇に自分のそれを重ねる。
「……ん…………」
唇の重なりから深知留の吐息が漏れる。
環がゆっくりと水を流し入れてやると、深知留はコクンと喉を鳴らしてそれを上手に飲み込んだ。
環は静かに唇を離し、汗ばんで額に張り付いてしまった深知留の髪を優しく指で梳いてやる。
「いい子だ、深知留」
深知留は未だ目を閉じたままであるが、環の呼びかけにわずかに微笑んだようにも見えた。
それを見て安堵感に包まれた環は小さくひとつため息を吐いた。
と、その時、
「……もっと……」
目を閉じたままの深知留は何とも物欲しそうな表情で環の袖をクイッと引いた。
(――――!)
深知留の仕草と表情に環は一瞬、ゾクリとした。
病人相手に不謹慎だとは思ったが、深知留のその表情は男を誘うのに十分な色香を持っていたのだ。
もちろん環はこんな病に伏せったような、しかも小娘を相手にしなくても、女には苦労していない。それでも、環を十分に欲情させる程今の深知留は艶めかしい。
言うなれば、深知留が病人だからこそ、熱で上気した頬や汗ばむ首筋が相乗効果となったのかもしれない。
「お、みず……もっと…………」
深知留は掠れた声で呼びかける。
環はもちろん聞こえていたが、先ほどのようにすぐに応えてやることはできなかった。
一度意識してしまったがために、口移しで水を与えることに罪悪感を覚えていたのだ。
しかし、深知留はそんな事情を知るはずもなくお水が飲みたいとねだり続ける。
彼女の掠れた声さえ、環にとっては扇情的に聞こえる。
「おみ、ず……おね、がい……」
何度目かのお願いに環はチッと舌打ちをした。
「分かったよ……」
環は再び水を口に含み、深知留に飲ませてやった。
それから深知留が満足するまで、環は数回に渡って深知留に水を与えた。
