深知留は朧気な意識の中、酷い口渇を感じていた。
「……ん」
口の中が粘つく気持ち悪さに深知留は顔をしかめる。
目を開けようとするが、そこまで力が入らない。
「深知留!?」
誰かが自分を呼ぶ声を聞いた気がした。
それは最近よく耳にする声で、何度も何度も呼ばれている気がする。
「……ず……たい…………」
――お水が飲みたい
深知留は名を呼んでくれる人にそう訴えかけたかったつもりだった。
「――――」
何かが聞こえるが深知留は巧く聞き取れない。しかし、自分の意志が伝わっていないことだけは感じ取れる。
「……お……ず……たい……の……」
――お水が飲みたいの
深知留はもとらない口で一生懸命言葉を紡ぐ。
すると、今度は返答の変わりにひんやりと冷たい何かが深知留の頬に触れる。
(気持ちがいい……)
深知留は素直にそう思った。
しかしそれで喉の渇きが満たされるわけではない。
「わからない……。深知留、もう一度言ってごらん?」
今度は聞こえる。
深知留はありったけの力を振り絞り、その誰かに向かってもう一度言った。
「お……み、ず……飲み……た……い」
それからすぐだった。
深知留の口元には無機質で固い何かが当てられ、押しつけられるままにそれを口に含む。そうすれば水にありつけるのだろうと本能的に感じ取って。
やがて、口内に水が到達する。
が、
「……ン……ケホ……」
突然口内に入り込んできた水分に、深知留はむせた。
ピクリという振動と共に、深知留の口から無機質な固い何かが外される。
咳が収まると再び深知留の唇に固い物が当てられる。
先ほどの経験で、確かにこの固い物から水が流し込まれるのを理解した深知留は、嫌がりもせず再びそれを口に含んだ。
しかし、
「……ク、ケホ……ケホ……」
深知留は今度も入ってきた水を巧く飲み込めずにむせた。
先ほどよりも咳き込んだ深知留は思わず顔を背ける。そして、息苦しさに自然と目頭が熱くなった。
水は与えられているのにそれは口渇を癒してくれない……咳き込む苦しさと同時にもどかしさが深知留の中でこみ上げる。
それからすぐのことだった。
今までとは違う柔らかい何かが深知留の唇を覆う。
そして、
「……ん…………」
ゆっくりと、心地よい温度の水が口内に入り込んでくる。
今度の水は深知留が嚥下するタイミングに合わせるように流し込まれ、彼女はそれを上手に飲み下すことができた。
やがて唇に触れた柔らかい何かは離れ、その代わりに、汗で額に張り付いた髪の毛を誰かが酷く優しい手つきで撫でてくれるのを深知留は夢うつつで感じていた。
「いい子だ、深知留」
そんな子供に語りかけるような声が耳に響いた瞬間、深知留は無性に甘えたい衝動に駆られた。
だから、本能の思うままに強請ってしまったのだ。
「……もっと……」
一瞬潤いを得たものの、再び口渇を感じていた深知留は傍にいる誰か欲望をそのままぶつける。
この時の深知留は、自分がどこにいるとか、何をしているとかそんなこと少しも理解できていなかった。それでも、今傍にいる誰か、なら自分の願いを聞いてくれると信じていたから。
だが、今度はいつまで待っても渇きは癒されなかった。
だから深知留はだだっ子のように訴え続けたのだ。
「お、みず……もっと…………」
「おみ、ず……おね、がい……」
何度も何度も続けると、やがて願いは届いたのか、
「分かったよ……」
そんな声が聞こえてすぐに、誰か、は深知留が満足するまで水を与えてくれた。
その後、渇きが癒された深知留は再び誘われるように眠りに落ちた。
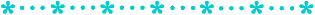
深知留はぱちりと目を開ける。
延々と白い天井がその視界に飛び込む。
(……朝? ここ、どこ……?)
すぐにそんな疑問が深知留の脳裏に浮かぶが、そこで初めて自分の体が鉛のように重いことに気づく。
(確か、わたし池に落ちて……)
深知留は徐々に冴え渡る意識で、自分の身に起こった出来事を思い出し始める。
とにかく一度、何とかして起きあがろうと思うと、深知留はなぜか両の手が動かないことに気が付いた。
深知留はまず自分の左側を見る。
すると、左の腕には点滴のルートが繋げられて固定板に括られていた。
これでは動かないはずだ、と納得して次に右側を見る。
瞬間、
(――――!?)
そこで深知留は息を呑んだ。
右手に繋がれたのは点滴のルートではなく誰かの手だった。
それは繋ぐと言うより、その誰かが深知留の手を握っている。
(環さん……?)
深知留はすぐに、誰か、を認識した。
環は深知留の手を握ったまま、椅子に座って深知留の横たわるベッドに突っ伏すようにして寝ている。
(……ずっと傍にいてくれたんだ……)
深知留は確認しなくてもすぐにそれが分かった。
池に落ちてから今まで、深知留に何も記憶はなかったが、それでも霞掛かった意識の中で誰かが何度も何度も『深知留』と名前を呼び続けてくれたことだけは覚えていた。そして、酷く口渇を覚えた時も、その誰かが満足行くまで水を飲ませてくれた事を深知留は朧気に覚えていたのだ。
(環さんだったんですね……)
深知留はぐっすりと寝込んでいる環を優しい表情で見つめていた。
ずっとそばにいてくれた……たったそれだけのことが、この時の深知留の心をとても温かくしたのだ。
幼い時から、深知留は熱を出して苦しい時やどうしても誰かに傍にいて欲しい時、一人で過ごすことが多かった。
そんな時、多英子はなんとか仕事をやりくりして深知留の傍にいられるよう努めてはくれたが、それでも明らかに深知留が我慢をすることが大半を占めた。
熱が出たからママが一緒にいてくれた……そんな友達を羨ましいと思いながら、深知留はずっと我慢して過ごしてきたのだ。
しかしながら、そんなことを何度も繰り返す内に、いつの間にか『仕方のないこと』と割り切れるようになり、平気になったはずだった。それなのに、誰かが今こんな風に傍にいてくれたことが、深知留はたまらなく嬉しい。
(環さん……ありがとう)
無意識のうちに深知留は右手に力を込めていた。
環はそれに気づいたのかゆっくりとその身を起こす。
「おはようございます」
深知留は視線が合った環に、嬉しさのあまりニコリと微笑みかける。
環はそんな彼女の笑顔を見た瞬間、何を言うでもなく勢いよくガバッと勢いよく深知留を抱きしめた。
「た、環さん!?」
驚いたのは深知留だ。
環は何も言わずただ深知留を抱きしめ続けた。それはまるで、抱きついたまま脱力してしまったかのように。
「環さん? どうしたんです? ねぇ……」
「よかった……目が覚めて、本当に良かった……」
安堵のため息が混じった消え入りそうな声が深知留の耳元で穏やかに響く。
耳に感じた吐息に深知留は一瞬恥ずかしさでその頬を赤らめたが、それよりも環の体温がとても心地良かった。
「大丈夫、生きてますよ」
深知留は環の背中を右手でポンポンと優しく叩く。
それに応えるかのように、環は深知留を抱きしめる腕に力を込める。
いつもは冷静な環が、このように取り乱すほどに心配したことを考えれば不謹慎であると思ったが、その時、深知留は素直に嬉しいと感じていた。そして、今まであまり感じたことのないふんわりとした温かさが、深知留の心を優しく包み込んでいた。
