昼間、鈴の元からリビングへと引き上げた後、雅は深知留に鈴のことを話してくれた。
生まれた時からそれなりの上流家庭で育った鈴。
彼女は中学生の時に身代金を目的に誘拐され、犯人に乱暴をされ掛けたのだという。寸前のところで警察が発見し未遂には済んだものの、鈴の心はその時に深く傷ついた。
その出来事による心の負担が大きかったのか、彼女はその時の記憶をほとんど留めていないらしい。しかしそれ以降、男性を必要以上に拒否するようになったという。
男性と接することで、その時の忌まわしい記憶が戻ろうとするのだろうと雅は話してくれた。
そんな雅の話を聞いて、深知留は今までの鈴の様子を彼女を取り巻く状況と照らし合わせて考えた。
身の回りを世話する者たちはもちろん、通常は男性であることが多い運転手でさえ女性であるのも、そのためなのだ、と理解した。また、鈴が行く先々で接待をしてくれる者たちは皆女性ばかりであった。今日のレストランも、最後の最後で男性が出てきただけで、全ての給仕は女性のスタッフだった。それも、全ては鈴を配慮してのことなのだろう。
そして、鈴自身が相手に踏み込まず、踏み込ませずというスタンスを取っているのも、この事情が理由の一つなのだろうと深知留は察していた。
「最近は……落ち着いていたんだ。前は兄さん以外の男性が近づくだけで駄目だったけどね」
すっかりと冷静さを取り戻したらしい環は呟くように言った。
その時、環の言葉を聞きながら雅の話を思い起こしていた深知留は、いつの間にかその表情に陰を落としていた。
そして、
「心の問題は難しいですからね。良くなったと思っても思い出したように急激に悪化する。本人でさえどうしようもなくて、解決策が見つからないから余計に辛いんですよ」
静かに話し始めた深知留を、環は思わずジッと見つめた。その時の深知留の顔は、今まで見たこともないほどに真剣で、そしてなぜか底知れぬ陰を纏っていたから。
「深知留……?」
「……え? ……あ、その……知り合いが、鈴さんと……ちょっと似てるんですよ。それより、今日はもうこのままここにいて良いんですか?」
怖ず怖ずと様子を窺う様な環に対し、ハッと我に返った深知留はまるで何かをごまかすかのようにすぐさま話をすり替えた。
環も、それ以上は何かを追求しようとはしなかった。
「いや、そうも行かないんだ。急な帰国だったから色々と残務整理がね。義姉さんのこともあるから兄さんにもフォローが必要だし、深知留が元気ならすぐに社に戻るよ。十四日まではまだ時間があるから、体調には十分気をつけるんだよ」
環はそれからすぐ、いつものように深知留を置いて部屋を後にした。
(なんだ……わたしじゃなくて、“恋人”が心配で帰ってきただけなんだ……)
深知留は環の残していった台詞に言いようもない寂しさを感じながら、その背を静かに見送った。
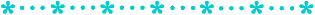
翌日、自室で実験データの整理をしていた深知留はそれを適当に切り上げると鈴の部屋を訪ねた。
「おかげんいかがですか? 少しは、落ち着かれました?」
深知留は部屋の窓辺に立つ鈴の隣に歩み寄る。
「……もうだいぶ良いのよ。ありがとう」
「良かった。血色も随分良くなってますし、安心しました」
鈴の微笑みは力が無かったが、それでも昨日倒れた直後よりは幾分血色は戻っていた。
「あの……深知留ちゃん。気を遣わなくても……いいのよ? 主人からわたしの事情は聞いているのよね?」
「はい。昨日聞きました」
「だったら……無理すること、ないのよ。昨日あんな姿を見せてしまって、驚かせたし、怖い思いもさせてしまったでしょう? だから……もうわたしの傍にはいない方が良いわ。それに……嫌でしょう?」
鈴は言葉が終わらぬうちにスッと深知留から視線を逸らす。
それは、他者の深入りを規制する鈴の“線引き”をいつも以上に感じさせるものだった。
深知留はそんな鈴をジッと見つめていた。
「鈴さんは、嫌ですか?」
「…………?」
突然投げかけられた質問に、鈴はわずかばかり視線を上げる。
「鈴さんはわたしが傍にいるの、嫌ですか? 嫌ならわたしはここから出て行きます。でも、こんな時だからこそ……誰かに傍にいて欲しいんじゃないですか?」
「…………」
あまりに予想外な深知留の言葉に鈴は何も答えられなかった。そして、ただ深知留の顔を不思議そうに見ていた。
そんな鈴を安心させるかのように、深知留はニコリと微笑んで見せる。
「実はね、知り合いが、鈴さんとは少し違うんですけど、似てるんです。その人はこんな時、誰かに傍にいて欲しいって言ってました。一人だと不安で、余分なこともたくさん考えてしまうから……って」
「でも、深知留ちゃん……」
「無理もしてませんし、嫌々でもないです。わたしが鈴さんの傍にいたいんですよ。だって鈴さんはわたしが退院してきてから、毎日一緒にいて遊んでくれたじゃないですか。だから、お返しですよ。鶴の恩返しじゃなくて、深知留の恩返しです。ね?」
深知留は一端言葉を止め、再びニコリと笑って見せた。
それにつられるように、固かった鈴の表情もいくらか和らぐ。
「本当は、雅さんに傍にいて欲しいかもしれませんが、雅さんもお忙しいようですから日中はわたしで我慢してください。それで……鈴さんはわたしが傍にいるの嫌ですか? 一人がいいですか?」
優しい笑顔で問いかける深知留の顔を、この時、鈴はただジッと視界に納めていた。
鈴は今、これまでに経験したことのない初めての感覚を心の内に得ていたのだ。
薬で治すこともできない心の問題を抱えてから、鈴は相手に避けられることは多くあっても、受け止めてもらえる経験は確実に少なかった。友人だと思っていた者たちは次第に離れていき、親兄弟でさえ、鈴がパニックを起こすたびにどうして良いのか分からない様子だった。
最初は、それが寂しくて仕方がなかった。世界中でたった一人残されたような気分で、怖かった。
しかし、そんな経験を重ねるうちに鈴は諦めることを覚えた。と言っても、避ける相手に対しての恨み言はない。そうするのも無理はないことだし、仕方のないことだと納得していたから。
一度諦めることを覚えた鈴は、それから殻に閉じこもるようになった。縋っても受け止めてもらえないことは分かっていたので、初めから相手には踏み込まないし、踏み込ませないようにもした。それが、鈴にとって自分を守る方法だったから。
それでも、唯一、夫となった雅は鈴を理解してくれ、辛抱強く支えてくれた。だから鈴はそれだけでもう満足で、それ以上は望まないようにしていた。望んだところで、そんな人は後にも先にも雅だけだと思っていたから。
それなのに、今目の前にいる深知留は、鈴に対して両手を広げてくれた。自分の状態を目の当たりにしても、避けることさえせずに。
しかしそれは偽善者のするようなものではなかった。そう、それはまるで、おいで、と母親が無償の愛情で子供を抱き留めるかのようであり、その優しい笑みが印象的だった。
自分より年若い深知留に母親という表現は相応しくない気もしたが、彼女はそんなことも忘れさせるほどに包容力を感じさせたのだ。
鈴はそれを不思議に思いながらも、それ以上に、どうしようも無いほどの嬉しさを覚えていた。
それは、そう……遠く昔、もう諦めたはずの嬉しさ……
「あの……鈴さん、わたしじゃなくてお友達とか、メイドさんとか、他にいて欲しい人がいるなら言ってくださいね? そしたら、わたし、その方を呼んできますから……」
いつまで待っても返事のない鈴に対し、不安になった深知留は言葉を重ねた。
鈴はそんな深知留に対してゆっくりとかぶりを振る。
「傍に……いてくれる? わたし、深知留ちゃんが良いわ」
そう言った鈴の瞳は、いつの間にか込み上げてきた涙で潤んでいた。
◆◆◆
それから、深知留は時間の許す限り鈴と一緒に過ごすようにした。平日もできるだけ早く実験を片付けるようにし、帰宅すればすぐに鈴の元へと行った。鈴もそれを首を長くして待っているようだった。
そんな深知留の努力の甲斐があってか、数日もすると鈴は元のように外出もできるようになり、笑顔も自然と見せるようになっていた。
それに一番驚いたのは他でもない雅だ。
今まででは考えられないほどの妻の早い回復ぶりに、雅は本当に喜んだ。
そして、
「深知留ちゃんがこの屋敷に来てくれて良かった」
と、何度も何度も心から感謝の意を述べた。
しかし、深知留はそれを素直に受けることはできなかった。
自分がここにいるのはあくまでも環の偽恋人だからであり、根本的に雅や鈴を騙しているという事実は消せなかったから。
だから深知留は、雅から感謝を伝えられるたびに罪悪感を覚えざるを得なかった。
