「……ごめんなさいね? 疲れてしまった?」
出先で夕食を摂った帰りの車中、窓の外を見ていた深知留の様子を鈴はすまなそうな顔で伺った。
「いえ、大丈夫ですよ。太ったかな、って窓に映る自分の顔見てたんです」
あはは、と笑いながら深知留は自分のほっぺたを摘んで見せる。
当たり前なのだが、龍菱家で暮らすようになってから先、深知留は栄養と睡眠が十分すぎて確実に体重増加していた。
「あら、そんなこと。肺炎起こして痩せてしまったんだから少しくらい太った方が良いわ。深知留ちゃん元々細いんだし。でも……本当に大丈夫? 毎日わたしに付き合わせてしまって……」
「楽しいですよ。お姉ちゃんができたみたいで。わたし一人っ子ですから」
まだ心配そうな表情を見せる鈴に、深知留は優しく微笑み返す。
「本当に!?」
鈴は子供のように声を嬉しそうに声を上げた。
深知留はそれに大きく頷く。
別にお世辞を言ったわけではなかった。深知留は本心からそう思っていたのだ。
正直、確かに初めは深知留も困惑した。鈴が行く場所は、どこも高尚で一般庶民の深知留には経験がないところばかりだったから。
それでも深知留は鈴と一緒にいて楽しかった。深知留は多英子以外で年の離れた女性とこうして出かけることなど無かったから新鮮だったのだ。その多英子も、仕事の忙しい人間であるため、一緒に出かけることなど滅多になかった。
「わたしね、男兄弟しかいないから、深知留ちゃんを本当の妹のように思っているのよ? だから深知留ちゃんといられるとつい嬉しくて、どこに行こうとか何しようとかたくさん考えてしまうの」
鈴は楽しそうに話した。
しかし次の瞬間、鈴はその表情に影を落とす。
「……本当はね、最初、深知留ちゃんを連れ出したのは、あなたを退屈させてはいけない、っていう主人からの言いつけだったの。でも、あんな事があって、深知留ちゃんにすっかりお世話になって……それでもっと深知留ちゃんと一緒にいてみたい、って思うようになったのよね。妹がいたらこんな感じなのかな? って。毎日何して遊ぼうか、どこに行こうか、凄く楽しみでね」
鈴は本当に嬉しそうにその顔をクシャクシャにしながら話した。
深知留はその顔に少しばかり罪悪感を感じていた。
(この人を……わたしは騙しているんだよね)
そう思うと辛かった。
「ねぇ、深知留ちゃん。卒業とかそんなの待ってないで、このまま環さんと結婚しちゃったら?」
「……え?」
深知留は鈴の突拍子もない発言に思わず声を漏らしてしまった。
「だって、環さんだっていい年だし、いずれは結婚するつもりでしょう? だったら学生結婚でもいいから早くしちゃうって手もあるじゃない。そしたら深知留ちゃんはお母様が帰国されてもずっとあの家にいればいいわけだし。わたし、それがいいと思うわ? どう?」
「…………」
目をランランと輝かせる鈴に、深知留は返す言葉がなかった。
(わたしは……環さんの本当の恋人じゃないのに……)
そんな深知留の思いなどつゆ知らず、鈴は続けて言った。
「龍菱深知留……いいと思うけれど?」
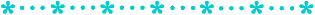
その日の晩、深知留はソファーの向かいに座って難しそうな英字新聞を読む環を眺めていた。
珍しく、今日は環がこの部屋にいる。なので、深知留は今日一番の出来事を環に話すことにしたのだ。
「環さん……」
「ん?」
環はコーヒーを飲みながら返事をした。しかし新聞からは顔を上げない。
だから深知留は呟くように言ってみた。
「龍菱深知留って……どうですか?」
「ブッ……ゲホォッ……ゲホゲホ………」
環は勢いよくコーヒーを吹き出し、苦しそうに咳き込んむ。
読んでいた英字新聞に所々茶色いシミができる。
(あーあ。苦しそ……)
深知留はやってしまったという顔をしながら涙目で咳き込む環を見ていた。
「深知留……どうかしたのか?」
環が掠れた声でそう言ったのは何度も咳き込んだ後だった。
「すみません、冗談が過ぎました。今日……鈴さんに言われましたんですよ。もう結婚したら? って」
「義姉さんが?」
「わたしのこと、妹ができたみたいで嬉しいって。だから結婚してもうずっとこの家にいたらいいと……」
深知留は言いながら、その時の鈴の顔を思い出して俯いた。
心の内で罪悪感が疼いたのだ。
「兄さんも似たようなこと言ってるよ」
「雅さんが?」
深知留はその顔をわずかに上げる。
「義姉さんも妹ができたみたいだって喜んでいるし、さっさと結婚してしまえばいいって。見てたら分かるかもしれないけど、彼女は男女問わずあまり人と接したがらないんだ。その義姉さんが深知留だけは進んで受け入れてるからね。天変地異の前触れも良いところだよ」
環は今まで読んでいた英字新聞を静かに畳む。
二人の間に沈黙が支配する。
深知留は再び俯くように視線を落としていた。彼女の中では先ほどよりも大きな罪悪感が生まれてきていたのだ。
「ところで……深知留」
環がそう口を開いたのはしばらくしてからだった。
深知留はふと視線を上げる。
「その手に持ってるの……一体なんだい?」
気づけば環は深知留が手に持つ小冊子を見ていた。
「あ、これですか?」
深知留は環と同じように小冊子に視線を向ける。
「これは、その……バイトを探してるんですよ」
「アルバイトを?」
深知留の返答に環は解せないという顔を見せる。
「十四日のパーティーが終わったら、環さんとの約束も終わりでしょう? だから、その後何かバイトをしようと思ってるんです」
「ねぇ深知留、失礼は承知の上だが……金額的に一体どのくらい必要なんだ? 君には随分迷惑もかけたし……全てのことが済めば深知留の所望する額を支払うつもりだ。それは前にも話したろう?」
環は至極真面目な表情を見せる。
(一体……どれほど必要だというんだ?)
当初から十分な額を支払うと言っているのに、それでもまだアルバイトをするという深知留を環が深刻に心配するのも無理はない。
「いえ。以前も言いましたけど、今回の件で環さんからお金をいただくつもりはありませんよ。それに……バイトも、お金のためでは……ないですから」
深知留は途切れ途切れに言葉を終えた。
すると、
「だったら、なんで?」
すぐに環は問い直す。
納得のいかない彼は不安ばかりが増してしまい、尋ねずにはいられなかったのだ。
深知留はそれに少しだけ困った顔をする。
「……俺には、言えないことか?」
深知留は重ねられた問いかけにすぐには答えず、何かを考えるように少しの間環を見つめた。
それから、彼女は決意をした様に大きく一つ息を吐いた。
「あの……実は、わたし……何というか……ある時期だけ、独りじゃ過ごせないんですよ」
「え……?」
深知留の意外な言葉に、環は零れるように声を漏らした。
「うちが母子家庭だってお話しましたか?」
「確か前にお母さんと二人暮らしだって」
環は記憶の糸を辿る。出会って間もない頃、そんなことを言っていた覚えがある。
「父はわたしが母のお腹にいる時に亡くなったそうです。元々妊娠するまで仕事一直線のキャリアウーマンだった母は、そのまま再婚することもなくわたしを女手一つで育ててくれました……」
こうして深知留はポツリポツリと自分の昔話を始めた。
