ある日の夕方、深知留は華宮家にいた。
ここ数ヶ月、深知留はこの華宮の屋敷に定期的に通っている。と言っても、訪ねる相手は蒼ではなくその妻である由利亜。深知留は彼女の勉強を見るためにここに来ている。
そもそも未だ現役女子高生である由利亜が『帝都大学の理工学部を受けたい』と言ったのが事の発端で、その推薦入試を受けることになった彼女を、元々知り合いであり尚かつ先輩でもある深知留が面倒を見ることになったのだ。
決められた時間の勉強を終えると、深知留と由利亜はお茶を飲みながら雑談を楽しむ。年齢差はあるものの、二人の馬はよく合って姉妹のように仲良くなるのにも大して時間はいらなかった。
何を隠そう、深知留が池に落ちた時も、約束の時間に現れない彼女を心配して由利亜が騒ぎ立てて蒼に伝えたのだ。
「それで龍菱さんて方とはどうなんですか?」
ひとしきり雑談を終えて、由利亜が突然切り出した。
深知留は一瞬目を見張る。
「蒼さんにちょっとだけ聞きました。色々あって今一緒に住んでるんですって?」
「詳しいのねぇ。蒼もお喋りだこと」
興味津々、という感じの由利亜を深知留はやれやれと言った表情で見る。
「その龍菱さんて、どんな人なんですか?」
「優しい人ね。相手の気持ちを常に考えてくれて、すごく居心地のいい人」
深知留は環を思い出しながら言葉を紡いでいく。
その言葉の通り、環は深知留にとって本当に居心地の良い相手である。これまで、彼女の中では付き合ってきた期間の長い蒼が最上位で居心地の良い相手であったが、環はそれとはまた異なった居心地の良さを深知留に与えてくれる。
「それで、好きになりそうとかないんですか?」
「え? ……さぁ……どうかな……」
突然飛躍した質問を投げかけた由利亜に深知留は一瞬驚いたが、すぐに否定とも肯定とも付かない返答をする。
「もぉ〜。はぐらかさないでくださいよ。すぐに否定しないって事は、深知留さん少しはその気があるんでしょう?」
鋭い質問を繰り出す由利亜に、深知留は思わずフッと笑みを零してしまう。
(かなわないなぁ、由利亜ちゃんには……)
「正直なところ……分からない。改めてそんな風に考えたこと無いからね」
深知留は出された紅茶を飲みながら、答えた。
「また誤魔化そうとしてません?」
「してません」
「本当に?」
疑いの眼差しを向け続ける由利亜に、深知留は「嘘じゃないってば」と改めて答える。
すると、由利亜は何だかとても意味深な笑みを浮かべて見せた。
「だったら、これを機に是非とも“改めてそんな風に”考えてみてください。あのね深知留さん、そういう時って、自覚が無いだけで案外もう好きだったりするもんですよ? 単なる好意が何物にも代え難い愛情に変わる……とか?」
「……由利亜ちゃんてば……随分と大人っぽい愛を語ること。とても十七歳とは思えない台詞ね」
「ふふ、これでもわたし、人妻ですから……なんてね。やっぱりバレちゃいますね。最近、そんなラブロマンスの映画を蒼さんと見たんですよ。そのストーリーが深知留さんと龍菱さんの出会い方によく似てたから、つい。でも、それだけじゃないですよ? ……わたし、深知留さんには幸せになって欲しいんです」
由利亜は言ってニコリと微笑んだ。その笑みは先ほどまでのものとは異なり、とても優しく思い遣りに満ちたものだった。
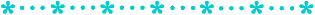
「難しい顔してるね、深知留」
そんな声が頭上から降りかかってきたのは、深知留が部屋でパソコン上のデータと格闘している時のことだった。
「あ、環さん。お帰りなさい……全然気づきませんでした」
聞こえた声に慌てて振り返るとそこには環の姿があった。
「集中していたみたいだね。はいこれ、おみやげだよ」
そう言って環が差し出したのは、板チョコレートだ。そう、それは深知留が環に初めてねだったあのチョコレート。
「ホワイトが新しく出たんだって。深知留これ好きだろう? 最近煮詰まってるみたいだから少し糖分でも摂って休んだらどうだい? 今も眉間に皺を寄せて難しそうな顔をしていたしね」
環はそのままチョコレートのパッケージを開き、一欠片割ると深知留の口に入れてくれる。
口内に甘みが広がると同時に深知留の顔も綻ぶ。
深知留は環のこんな小さな気遣いが好きだ。自分の事を常に見ていてくれて、気に掛けていてくれて……些細なことだが、それは深知留に居心地の良さと幸福感を与えていた。
チョコレートを美味しそうに頬張る深知留を、環は穏やかな顔で見つめている。
「少し手伝おうか? 今日は急ぎの仕事もないし、これでも俺は君の先輩だからね」
「本当ですか? じゃあ少しだけ……ここのデータなんですけど、どうしても計算が合わなくて」
深知留がパソコンの傍から資料を拾い集めると、環が少しかがむように深知留の首元から顔を出した。
「これか……そうだな……」
ふと顔を横向けると、環の綺麗な横顔が深知留の視界を占める。
今ではもうすっかり見慣れてしまった顔だ。最初は卒倒するか鼻血を吹くほどだったその顔も、今の深知留にとっては見るだけで安心する顔となった。
長いまつげの奥から、パソコンの画面と深知留の手にある資料を交互に見る環……深知留はそのまましばらく考え込む彼に見とれてしまった。
別に何か理由があって見ていたわけではなかった。ただ見ていた、それだけだった。
ふと、数時間前に由利亜が言った台詞が深知留の脳裏をよぎる。
『そういう時って、案外もう好きだったりするもんですよ?』
その瞬間、深知留の心臓がトクンと高鳴る。
「……深知留、どうかした? 俺の顔に何か付いてる?」
「え!? …あ……べ、別に、何でもないです…よ?」
突然掛けられた言葉に、深知留は慌てすぎて明らかに挙動不審になる。
「顔……赤いぞ? 熱でもあるんじゃないのか?」
環はそっと深知留の額に手を当てる。
それは環にとっては何気ない行為であったが、深知留の心拍数は一気に跳ね上がる。
「だ、大丈夫ですよ。ちょっと暑いだけです。暖房……強いの、か、な?」
あまりの恥ずかしさに深知留の声は上擦り、思わず環の手を振り払ってしまった。
そして、その恥ずかしさを何とか紛らわそうと、手元に撒き散らかされていた書類をガサガサとまとめ始める。
その時だった。
ピッという微細な音と同時に深知留の指先に痛みが走る。
「痛っ……」
深知留の左人差し指の指先からすぐに真っ赤な血が滲む。
「切ったのか?」
「ちょっとだけ……」
深知留が止血をしようと傍にあるティッシュボックスに手を伸ばそうとした瞬間、
「貸してごらん」
そんな言葉と共に、深知留の左手首が引かれ、続いて指先に慣れない感覚が走った。
「た、た、環さん!?」
突然傷口に口づけた環に、深知留は一気にパニックを起こす。
「血……汚いですから……」
「汚くない。良いから……」
環が喋る通りに彼の息が深知留の指先にかかる。
伏し目がちに指先に口付ける環……そんな彼の顔があまりに艶めかしくて、無意識のうちに深知留の全神経は指先へと集まってしまう。
額に手を当てられた時の比ではない、ドキン、ドキン、という自分の心音だけが、深知留の耳を支配していた。
ただ止血をしているだけ……そう懸命に自分に言い聞かせるのに、深知留の心音は収まる気配がない。
そして、環が傷口をペロッと舐めた時だった。
ザラリ、という舌独特の感触に深知留はゾクリと背中を震わせた。
「た、環さん。もう大丈夫ですから!! わたし……絆創膏貰ってきます!!」
限界を迎えた深知留はそれだけ言うと、環の唇を振り切るように自分の指を引き寄せる。
そのまま、深知留は環の顔を一度も見ることができずに部屋を飛び出した。
バタン、とドアを閉めた後、深知留は気が抜けたのか崩れるようにその場に座り込んでしまった。
(ビックリ……した……)
ふと指先を見れば、わずかに血が滲んでいる程度でもうほとんど止まっていた。
深知留は傷口を見ながら環の表情を思い出していた。
そして、
「環さん……」
呟くようにその名を呼びながら、深知留は傷口にそっと口づけた。
一方、部屋の中では環が深知留の出て行ったドアを見つめ、小さく一つ溜息を吐いていた。
