深知留が帰宅するとリビングでは鈴が何冊もの本を広げて首を捻っていた。
そのまま深知留は鈴の後ろまで歩み寄ったが、よほど集中しているのか全く気づく様子はない。
「鈴さん、何してるんですか?」
「あら、深知留ちゃんお帰りなさい。今日は遅かったのね」
深知留は鈴の手元を覗き込む。
そこにあるのはお菓子の本だった。開かれたページにはチョコレートケーキの作り方が出ている。
「うわ、美味しそう。もしかして、鈴さんコレ作るんですか?」
「うん。作ってみようかな、と思ったの。でも、少し確認したいところがあって調べてたところ」
「もしかして鈴さん、よく作るんですか?」
深知留は広げられた本を見ながら尋ねた。
それらの本は新しいものもあったが、多くは年季の入ったものだったのだ。
「最近はしてなかったけど、多少ね。恥ずかしながら、こういうのが趣味なのよ」
鈴は言ってフフッと笑って見せた。
そんな彼女を見て、深知留は「鈴らしいな」と思っていた。
見た目そのまま、と言おうか、可愛らしい外見で尚かつお菓子作りが趣味とはなるほど納得である。
「ねぇ、良かったら深知留ちゃんも一緒にどう?」
「あ……わたしお菓子作りはちょっと……」
鈴の誘いに深知留は少しばかり躊躇った。
別にお菓子作りが嫌いなわけではない。しかし、そういう才能が自分にはないことを深知留はよく分かっていた。
育った家庭環境のおかげか、普通の食事であれば深知留も困らない程度には作れる。しかし、手の込んだものやお菓子といわれるとそれは無理だ。というか、学校の調理実習でクッキーを作ったのが唯一の経験だ。
「嫌いじゃないんですよ。でも、苦手なんですよね……そういうの作れたらいいな、とか憧れはあるんですけど」
「それなら、わたしで良ければ教えるわよ。深知留ちゃん一緒にしましょう? わたしね、一度誰かと一緒に作ってみたかったのよ。だから、ね?」
鈴の表情があまりに嬉しそうで、深知留は思わず「じゃあ、一緒に」と気づいた時には首を縦に振っていた。期待されるとつい応じてしまうのが深知留の癖だ。鈴はと言えば、その返答に更に喜んだ。
「明後日なら早く帰れると思いますけど、それでもいいですか?」
「うん。明後日ね。楽しみにしてるわ」
二人の間で話が纏まったその時だった。
「お話中失礼致します。深知留様、環様がご帰宅されましたので、お部屋にいらっしゃるように、と」
メイドが一人、リビングへとやってきた。
「あ、はい。ありがとうございます」
メイドはそれだけ伝えるとすぐに退室していった。
時計を確認すると、もうすぐ午後八時というところだった。
「環さん、もう帰ってきたのね」
鈴も深知留同様時計を確認する。
「深知留ちゃんのこと、本当に可愛いくて仕方がないんでしょうね」
「え?」
鈴から掛けられた言葉を深知留は思わず聞き直してしまった。
「だって彼、今までならこんなに早く帰ってこなかったわよ? 少なくとも、わたしが雅さんと結婚してからはいつも十時は過ぎていたわ。食事だって朝食以外、この家で摂ることもあまりなかったし……。深知留ちゃんが来てから、よく家にいるのよね」
鈴は微笑みながら「いい傾向だわ」と言い添える。
「それは……たぶん、わたしが論文を見て欲しいって我が侭言ってるからですよ」
そんな鈴に答える深知留の表情は少し浮かなかった。なぜなら、環が家に長くいてくれる本当の理由は、恐らく自分が弱音を吐いてしまったせいだからだと分かっていたから。傍にいて欲しい、と環の優しさに甘えて縋ってしまったからだ。
その時深知留は、やっぱり言わなければよかったかな、と少しの後悔をしていた。
「環さん、優しいから……わたしの我が侭聞いてくれるんですよ」
「あら、それは違うわよ」
鈴は深知留に対して即答した。
そのあまりの早さに、深知留は思わず鈴の顔を見てしまう。
「わたしが見ている限り、環さんはいくら恋人といえども、単なる我が侭を簡単に聞く人じゃないわよ? どちらかと言えば、我が侭を言われたところで仕事があれば、仕事を優先してしまうタイプよね」
鈴は一度言葉を切った。そして、徐に深知留の耳元へ顔を寄せる。
「つまりね……」
鈴がそのまま囁くと、深知留の頬は化学反応のように赤らんだ。
それを見て鈴はクスリと笑みを零す。
「あらあら、深知留ちゃん照れちゃって……頬が真っ赤よ。可愛いわね」
「す、鈴さん!! 何言ってるんですか!」
「そうだ、夕食はせっかくだから二人きりで摂ったら? 部屋に運ぶよう伝えておくわ。……じゃあね、ごゆっくり」
鈴はそう言うと、テーブルに広げていた本を手早くまとめてリビングを出て行った。
そんな鈴を見送る深知留の耳には、彼女の囁きが消えずに残っていた。
『つまりね……それは、深知留ちゃんが環さんにすごーく愛されてる証拠よ』
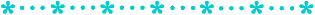
部屋に行くとメイドの言った通り環はそこにいた。そして、既に机のパソコンに向かっている。
彼が読んでいるのはそう、深知留の論文だ。
環は一度深知留が頼って以来、暇を見ては毎晩論文作成を手伝ってくれていた。彼の教え方は丁寧で分かりやすく、深知留はこの時間が楽しみで仕方がない。
もちろん深知留は環の負担になるつもりはないので「お仕事を優先してくださいね」と言ってある。しかし、環は「好きでやってるんだから気にしなくていい」と言ってくれた。
「ごめんなさい、環さん。お待たせしました」
「大丈夫。義姉さんと話してたんだろう?」
「はい。鈴さんが、今度ケーキ作りを教えてくれるって。可愛い趣味ですよね。わたしも将来のために習っておこうと思って」
「将来のために?」
環は論文から視線を上げ、気になった一部だけを反復する。
「はい。誰かにプレゼントする時、手作りって素敵じゃないですか」
「例えば誰に?」
尋ねられた詳細に、深知留は一瞬うーんと唸った。
由利亜の誕生日も近いことだし、それまでにマスターできれば彼女にプレゼントしても良い。それが駄目ならバレンタインデーに研究室の人たちに渡すという手もある……深知留は考えを巡らせる。
「そうですねぇ、友達とか? いずれは恋人とか? まぁ……いつかは、っていう希望ですよ」
「そう。義姉さんの得意分野だから、きっとうまく教えてくれるよ」
この時、環が小さな溜息を漏らしていたことに深知留は気づいていなかった。
「そうだ、環さん。わたし、お願いがあるんです」
深知留はそう言いながらゆっくりと移動すると壁際に設置してある本棚を指差す。
「読みたい本でも?」
環も席を立って深知留の元へと行く。
「あれ、読みたいんです」
「あれって……」
深知留が指差す先にあるのは、本棚の最上段に並ぶ一冊の冊子だった。
それは、環が在学当時に書いた卒業論文だ。
「構わないけど……テーマも違うし、参考になるかは分からないよ?」
「それでもいいんです。この前見つけて、読んでみたいなって思ったので。見ても良いですか?」
深知留は問いかけに環が頷いたのを見届けて、本棚の前に置いてあった踏み台に登る。
そのまま手を伸ばしたが深知留の身長では少し足りない。
「届く? 俺が取ろうか?」
「大丈夫、です……もうちょっと…………」
深知留が踏み台の上でできる限りの背伸びをし、冊子の背表紙に手を掛けたその時だった。
「キャァッ!!」
「危ない!」
つま先立ち状態となった深知留は環の案じた通り、踏み台の上でグラッとバランスを崩した。
気づいた時にはもうどうすることもできず、深知留は床に転ぶ痛みに耐えるべく体に力を込め、目もギュッと閉じる。
ドスン、という大きな音がすぐに響く。
しかし……
どうしたことか、深知留は体のどこにも痛みを感じない。
深知留は恐る恐るゆっくりと目を開く。
(――――!)
「……大丈夫か? 深知留」
鼻先数センチに見えたのは、環の顔だった。
環が落ちてくる深知留を抱き留めたまま一緒に転んでくれたのだ。
ちょうど、深知留の体は横抱きにされるように環に抱き留められており、環は転んだ衝撃で床に座っている。
「どこも打ってない?」
「…………」
環の問に、深知留は無反応だった。
別にどこが痛いわけでも、打ったわけでもない。
ただ、深知留は鼻先数センチの環の顔に見入っていたのだ。
よく考えてみれば、深知留はこれまでこんなにも近くで環の顔を見たことはなかった。つい数日前、横顔を至近距離で見とれてしまったが、今の状況はそれよりもまだ近い。
深知留は瞬きひとつせず環の顔を見上げていた。
そして自分の置かれた状況も忘れ、無意識のうちに考え事をしていたのだ。
(なんだかこの距離って……)
「……深知留? どこか痛むのか?」
「え……、あ、大丈夫です」
環の言葉で深知留はふと我に返る。
「それなら良かった。瞬きもしないからどうかしたのかと思ったよ」
「す、すみません……。ちょっとビックリしちゃって」
「いや、いいんだ。ただ、こんなに至近距離で見つめられると照れくさくてね」
環は冗談めかしながら深知留に優しく微笑みかけた。
トクン……と一つ、深知留の心拍がその笑みに呼応する。
すると環は徐に深知留の頬に手を寄せた。環の温かさが深知留に伝わる。
「でも、この距離だったら……」
環はそのまま親指で深知留の唇をフニっと押した。
そして……
「キスするのに丁度いい」
そんな台詞が聞こえた瞬間、環の顔が深知留にグッと近づいた。
(え…………?)
深知留の思考回路は完全に止まった。
