「フッフーン、フフフ〜ン……」
深知留は鼻歌交じりに実験室で手を動かしていた。
同時に頭では考え事をしている。
今日の夕方は鈴と一緒にケーキを焼く約束がしてあった。
今朝出がけに鈴は深知留を呼び止め、チョコレートケーキかチーズケーキどちらか好きな方を帰ってくるまでに考えておいて、と言った。
「やっぱりチョコレート? でもチーズケーキも捨てがたいよねぇ……」
深知留はいつの間にか独り言を口にしていたのを気づかずにいた。
「今日はチョコレートにして、近々チーズも習うって手もあるし……どうしようかなぁ」
深知留が考え倦ねたその時だった。
「チョコレートケーキとチーズケーキがどうかしたんですか?」
「!?」
突然背中から降りかかった声に驚いて、深知留は危うく持っていた実験器具を落としそうになる。
「鼻歌なんて歌っちゃって、ご機嫌ですねぇ深知留さん」
深知留が振り返った後ろに立っていたのは真尋だった。
「わたし結構前から居たんですけど全然気づいてなかったでしょ?」
真尋は恨めしそうな顔をしていた。
「あ、え……? そうなの!? ごめんね。それで……何か用事?」
「教授が深知留さんの机に論文に使う資料を置いておいたから読むように伝えてくれってことです」
「わかった。わざわざありがとう」
深知留は、再び休めていた手を動かし始める。
真尋はそのまま用事を終えて実験室を出て行くかと思われたが、伝言をした後もその場を動く様子はない。
「……真尋ちゃん? まだ何か用事?」
深知留は再び実験の手を止めて、振り返る。
「ねぇ、深知留さん。結局、環さんとは恋人同士になったんですか?」
「な、何言ってるの! そんなことあるわけないじゃない」
突拍子もない真尋の質問に、深知留は慌てて否定する。
そんな深知留を真尋は訝しそうに見つめる。
「だって、少しは進展あったかなぁと思って」
言われて、深知留は自然と環のことを思い出していた。同時に脳裏を過ぎったのは、例の未遂に終わったキス……
あの時は、わずかばかりの理性が勝って止めてしまった深知留だが、きっとあのまま唇を重ねていても決して嫌ではなかった。でも、成り行きだけで環とそんなことはしたくなかったのだ。
もし、環とキスをするなら、もっと、そう……深知留は考えながら自然と頬を赤らめる。
「……良いこと、あったんですね?」
「へ?」
すっかり物思いに耽っていた深知留は慌てて返事をした。
「顔、弛んでますよ? それに少し赤くないですか?」
真尋はにんまりと意味深な笑みを見せる。
「べ、別に何もないから……」
深知留はそれ以上真尋と顔を合わせていられなくて、実験台へと向き直る。
「じゃあ、チョコレートケーキとチーズケーキって何ですか?」
真尋はそんな深知留を逃すまいとすぐ隣に移動する。
「それは……ちょっと焼いてみようかなぁ、って思っただけで……」
「もしかして、環さんへのプレゼント!?」
「違う違う。単に焼くだけ。そんな特別な物じゃないの」
そう言って再び実験に集中し始めてしまった深知留に、真尋はそれ以上何も聞かなかった。
しばらくして諦めたのか、真尋は実験室の出入り口へと向かっていった。
だが、
「そうそう、深知留さん……一つだけ」
真尋はドアを開きながら振り返って言った。
「男の人って、案外女の子からのベタなプレゼントに喜んだりするもんなんですよ? 例えば、手作りのケーキ、とかね」
真尋は意味深な言い方をして、そのまま実験室を出て行った。
「だから、そんなんじゃないってば!」
深知留は真尋の出て行った扉へ声を放った。
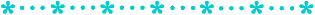
「ねぇ鈴さん……雅さんて甘い物食べるんですか?」
深知留はスポンジケーキがオーブンで焼き上がるのを待ちながら、思い立ったように鈴に尋ねた。
「そうね、結構好きみたいよ。わたしが作る物も、比較的何でも食べてくれるし……。前はケーキを半ホール一人で食べたこともあったわよ?」
「それって、甘い物が好きなんじゃなくて、鈴さんが作るからじゃないですか?」
深知留は鈴を構うように言った。
「やぁねぇ、深知留ちゃん……新婚でもない夫婦をからかうもんじゃないわよ。そういう深知留ちゃんこそ、環さんに何か作ってあげたことはないの? お菓子じゃなくても普通の手料理とか」
問い返した鈴に、深知留は無言でかぶりを振った。
それに対して、鈴は意外という顔をする。
意外もなにも、偽恋人なのだから当たり前と言えば当たり前なのだが……そんな事情は鈴には関係ない。
「だったら今度、何か作ってプレゼントしてみたら? 環さん、深知留ちゃんが作ってくれたものならきっと喜ぶわよ?」
それが良いわ、とばかりに嬉しそうに提案する鈴とは裏腹に、どうとも返事をし難い深知留は「そうですねぇ……」と否定でも肯定でもない答えを返した。
(プレゼント……真尋ちゃんも言ってたっけ……)
深知留はふと、先ほど真尋が言っていた言葉を思い出す。
(最近お世話になりっぱなしだし……それもいいかもしれないな)
そうこうするうちにケーキは焼き上がり、鈴はチョコレートクリームで綺麗にデコレートし始めた。
その手つきは慣れた物で、プロ顔負けのウェーブをクリームで作り上げていく。見ている限り、それはとても趣味の範囲ではないレベルである。
そんな鈴の顔は真剣で、でも、見方によっては柔らかくも感じた。
深知留は鈴を見ながら、雅が美味しそうに頬張る姿でも想像しながらクリームを絞っているのだろうか、と想像を膨らませていた。
(やっぱり、誰かのために何かを作るって……いいな)
「好きな人のために、こうしてお菓子を作るなんて……素敵ですね」
深知留は思うのとほぼ同時にそう言葉を紡いでいた。
「どうしたの? 突然」
「いえ……ただ、鈴さん見てたら、良いなぁ、と思ったんですよ。好きな人を思いながら、好きな人のために……なんて、素敵ですよね。羨ましいな、鈴さんが」
「羨ましい? どうして?」
鈴は深知留の言うことが解せない様子で尋ね返した。
「わたしも……鈴さんみたいに好きな人にお菓子作ってみたいなって思ったからですよ。まぁあてにならない、いつかそのうち、ですけどね」
深知留はそんな鈴に正直な気持ちをぶつけた。
すると、鈴は突然フフッと面白そうに笑った。
「何か……可笑しいですか?」
「ううん。深知留ちゃんが、何だか恋する乙女みたいな事言うからよ。相変わらず可愛いな、と思ったの」
鈴は、今までクリームを絞っていた手を止めると、その絞り袋を深知留へ差し出した。
「だったら……練習しましょう? 深知留ちゃん。コツさえ覚えればすぐにできるから、ね?」
やる気満々の鈴に対して、深知留はそれを受け取るのを少しばかり躊躇った。
「わたしがやったらデコレーション崩れますよ……?」
鈴のプロ並みの腕前を見せつけられた後では流石に気が引ける。
「大丈夫よ。見た目が多少崩れても味は変わらないから。それに練習あるのみよ! わたしだって最初からできた訳じゃないもの」
深知留は怖ず怖ずと絞り袋を手にする。
「そうだ深知留ちゃん、このケーキ、環さんに食べて貰ったら? 好きな人にプレゼント、早速してみたらいいじゃない?」
「環さんは……ダメですよ」
深知留はゆっくりとクリームを絞りながら呟くように答え、同時に考え事をしていた。
(環さんは……たぶん、甘い物は好きじゃないんだよね……)
環はしばしば例のチョコレートを買ってきてくれるが、専ら深知留が食べるだけで彼は勧めてもあまり口にしなかった。
その様子からして、環が甘い物を好まないという事を深知留は察していた。だからもしも環にプレゼントするなら、何か甘くない物、が良いだろうと思ったのだ。
そういうことならば、今日はチーズケーキにすれば良かったと深知留は少し後悔をしていた。
その時、キッチンの外で小さな物音がしたことに深知留も鈴も気づいていなかった。
