「ねぇ深知留ちゃん、何で環さんはダメなの?」
不思議に思ったのか、鈴は深知留に尋ねた。
「環さん、たぶん甘い物好きじゃないんですよ。だからです」
深知留の返答に鈴は納得したような顔を見せる。
「そうね、確かに。言われてみれば彼はそうかもしれないわね。でも、それなら心配ないの。今日のは少し砂糖を控えたレシピにしてあるから、環さんでも食べられるわよ。大丈夫」
ほら、と鈴はスポンジの切れ端に少しのクリームを乗せて深知留に食べさせてくれた。
鈴の言うように、それは本当に甘さ控えめだった。しつこくない甘みとチョコレートの芳醇な香りが口の中に広がって深知留は思わず「おいしい」と言葉を漏らした。
「環さん……食べてくれますかね?」
「食べなかったらただじゃおかないわ」
鈴の言い方が可笑しくて深知留は思わずフフッと声を上げて笑ってしまった。
(今日も論文見てもらう約束してるし……早く帰ってくるといいな。それにケーキも、食べてくれるかな? またお日様みたいな笑顔……見られるといいけど)
深知留はそう思いながらクリーム搾りに集中し始めた。
その時の深知留は期待と少しの不安にワクワクするような懐かしい気分だった。それは昔、好きな人にバレンタインデーのチョコレートを手作りした感覚とどこか似ているような気がした。
鈴はそんな深知留の様子を温かい目で見守っていた。
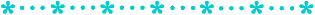
時は少々遡る――――
環は会社での仕事を一段落付け、一度忘れ物を取りに屋敷へ帰っていた。
本当であれば、今日はこのまま家にいて深知留の論文を見てやる約束をしていたのだが、今朝緊急で接待の予定が入ったのである。
環はそれを伝えるついでもあってわざわざ屋敷に戻ってきたのだが、居るはずの深知留はどこにも見あたらなかった。
まだ帰っていないのかとも思いメイドに聞くと『若奥様と一緒にケーキを焼いていらっしゃいますよ』と言われ、環はそのまま離れにある鈴専用のキッチンへと向かった。
言われてみれば数日前に深知留がそんな話をしていたことを思い出す。
キッチンに近づくと、中から深知留と鈴の声が聞こえた。
どうやらメイドが言ったことは確からしく、そこには二人がいるようだった。
「深知……」
「好きな人のために…………作るなんて…………憧れますね」
突然、途切れ途切れに聞こえた深知留の声に、環はキッチンへ踏み入れようとした足を止めてしまった。
「どうしたの? 突然」
続けて鈴の声が聞こえる。
そのまま、二人は環が傍にいることなど知る由もなく恋の話に花を咲かせ始めてしまい、環は出て行くにいけなくなってしまった。
腕時計を見ると、時間は差し迫っている。
環は仕方ないと思い、メールか書き置きをしようとそのまま踵を返そうとした。
その時だった。
「そうだ深知留ちゃん、このケーキ、環さんに食べて貰ったら? 好きな人にプレゼント、早速してみたらいいじゃない?」
鈴のそんな言葉が環の耳に飛び込んできた。
その瞬間、環の心を何とも言いようがない物が掠めていく。
深知留がそれに一体どんな回答を出すのか……それだけが無性に気になった。そして、盗み聞くなどいけないことだと思いながらも、環は一度止めた足を動かせなかったのだ。
そして……
「環さんは……ダメですよ」
それからすぐに、深知留の言葉からこぼれたのはそんな言葉だった。
それは一瞬の出来事。
困ったような深知留の声と、空けた間……
別に、環は何を期待していたわけでもない。
それなのに、彼女の言葉を聞いた瞬間になんだか言いようのない思いが心を支配した。まるでそれは期待を大きく裏切られたような……そんな気分だった。
環は込み上げた溜息を堪えきれずに吐き出すと、そのままその場から静かに去った。
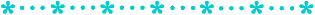
その晩、深知留は初めてソファーで夜を明かした。
環が帰らなかったのである。
ケーキ作りを終えた後、できたそれを持って深知留が部屋に戻ると環の書き置きが残されていた。
急な仕事で遅くなるから今夜は論文を見てやれない、明日は時間を空けるから……そこにはそんな内容の文面が環の名前と共に走り書かれていた。
深知留はまた忙しくなったのかな、と思いながらケーキと一緒に環を待っていた。どんなに遅くても必ず帰って来るはずだと信じて。
しかし、環は帰らなかった。
いつの間にか眠ってしまった深知留は、朝、小鳥のさえずりでその目を覚ました。
自分はいつもと違って眠りに落ちたままのソファーの上、部屋の照明は付けたまま、そしてテーブルにはラップのかかったケーキが昨日眠りに落ちる前に見た状態のままで置かれていた。
そこで初めて、深知留は環が帰らなかった事を理解した。
どうしたんだろう……もちろん、そんな心配が一番に生まれた。しかし、すぐ次には……
(傍にいてくれるって言ったのに……)
言いようのない寂しさが、深知留の気持ちを支配した。
でも深知留は、すぐにかぶりを振ってその気持ちを否定しようとした。
だって……
(恋人じゃないんだから……そんな我が侭言ったら駄目だよね)
そう納得するよりなかったから。
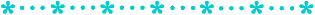
深知留は学校で機械に向かいながら、ボーッとしていた。
夕べソファーで寝入ったせいか、少し体が痛む。
(環さん……何かあったのかな?)
そんな疑問ばかりが、深知留の頭に浮かんでは消えていく。
「……さん。……知留さん……ねぇ、深知留さんてば!! 機械、プログラム終わってますよ?」
「は、はい!?」
突然我に返った深知留は慌てて機械の画面を覗き込む。そこには確かに『完了』の字が出ていた。
「もー深知留さん、どうかしたんですか? らしくないなぁ」
「ちょっと……考え事してたの」
「環さん、のことですか? 今度こそ恋人になりました? 今日は朝から眠そうですけど……もしかして、さっそく朝帰り!?」
「……違う、違う」
深知留は真尋の詮索を逃れるように機械の操作を始める。
真尋はそんな深知留を興味深そうに見ている。
「ねぇ、深知留さん。違うんだったら、わたしのお願い聞いてくれません?」
「…………」
ふと顔を上げれば、爛々と目を輝かせている真尋に、深知留は訝しそうな顔をした。
「一応、聞くだけなら……」
「んーまぁ、それでも良いです。……十二月十六日の土曜日、深知留さんの誕生日でしたよね? その日の夜、空いてません?」
「もし空いてたら?」
最初から核心には触れない真尋に、深知留は窺うように聞く。
「合コン、行きましょ?」
「嫌です」
即答した深知留に真尋はぷぅっとその頬を膨らませる。
「まだ続きますから、聞くだけ聞いてくださいよぉ」
「えー。でも、本当に聞くだけね? それでもいいの?」
深知留は渋々返事をする。
「相手は菱屋銀行の人です。龍菱さんと付き合ってないなら、別に良いでしょう? 主催はわたしと涼。さぁ深知留さん、クリスマスまでに彼氏を作ろう計画ですよ!!」
「真尋ちゃん、わたしそういうのは……」
鼻息荒く意気込む真尋に、深知留は明らかに引いてしまう。
「とりあえず行ってみる、ってのもダメですか? 今すぐ答えないで少し考えてみてください。別に当日まで考えてもらっても良いですよ! 深知留さんなら飛び入り参加でもオッケーですし」
「いや、でも……」
「強制はしませんから。考えてるうちに気分が変わるかもしれないでしょ? ね?」
「…………」
深知留は貝のように口を噤んだまま答えない。
真尋も今はそれ以上無理強いをする気はなかった。
「そうだ、深知留さん。検体を培養機の中に入れたままじゃないですか?」
「あ!!」
真尋の言葉を聞くなり深知留はガチャンと音がするほどに今まで座っていた椅子から立ち上がった。
「真尋ちゃん。それ早く言って!!」
「あ、でも……」
深知留はそのまま白衣を翻し、凄い勢いで部屋を飛び出していった。
「わたし、さっき取り出しておいたんですけど……ってもう聞いてないかぁ」
真尋は既に見えなくなった深知留の背中に付け足した。
(実験に身は入ってないし、ボーッとしてるし……深知留さんらしくないなぁ。やっぱり、絶対龍菱さんと何かあったのね)
その時真尋はある種の確信を得ていた。
