「吉里さん……何の話ですか?」
訳の分からない深知留は説明を求めるように政宗に尋ね直す。
「言い逃れしたい気持ちも分かりますが……昨晩、恋人とご一緒だったでしょう?」
「すみません、何を仰っているのか……意味が分かりません」
(夕べ……? 恋人と? ……夕べは由利亜ちゃんと蒼と一緒で……何の話?)
深知留は政宗の言っていることが本当に理解できない。
政宗はそんな深知留に呆れたとでも言いたげに溜息をひとつ吐いた。
「まだ白を切りますか? 華宮プリンスホテルの前で、公衆の面前で堂々と仲睦まじそうにキスまでしておいて?」
「あ…………」
政宗のその一言で、ようやく深知留の中で話の辻褄があった。
彼が言っているのは恐らく、ずれたコンタクトレンズを見てくれた蒼のことだ。深知留はすぐにそれを理解した。
「あれは……違います。ただの友人です。あの時はわたしのコンタクトがずれて……」
「コンタクトね……。咄嗟にしては随分とうまい言い訳を思いつきましたね。それとも、よく使うんですか? そういう理由。しかし、私に言い訳をしていただく必要はございませんよ」
慌てて釈明をしかけた深知留を政宗は静かに冷たく遮った。
「そんな、言い訳だなんて……あの時は本当に……」
深知留はそれでも何とか聞いてもらおうと話を続ける。
が、
「分かりました。仮にそうだとしましょう。でも、今は環様からお金をもらって契約しているのでしょう? 違反になるようなこと、疑われるようなことは慎むのが義務だと思います。お優しい環様は何も仰らないでしょうから、僭越ながら私から忠告させていただきますよ」
深知留は今度こそ、その目を見開いた。
「環さんも……見てたんですか!?」
政宗が頷くのを見届ける間も惜しんで、深知留はその場を駆け出した。
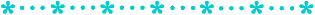
バタン、と勢いよく部屋に入れば、そこには政宗の言うように環がいた。
「なんだ、深知留……帰ってたのか」
環はパソコンに向けていた顔を一度だけ上げたがすぐに戻す。
その時、深知留の頭は、とにかく誤解を解かなければ……という思いでいっぱいだった。
「環さん、昨日わたしを見たんですよね!? 華宮プリンスホテルの前で、その……男性と一緒の所を」
深知留は環の元まで歩み寄りながら言った。
「あぁ……昨日の晩。確かに見たよ」
環はパソコンに向かい、データをUSBメモリーに移しながら深知留の方は一切見ずに答える。
「環さん……違うんです!! あれは……」
深知留が言いかけた時だった。
「恋人がいるなら最初から言えばいいだろう」
環は相変わらずパソコン画面に集中したまま素っ気なく言った。
「俺が恋人の振りをして欲しいと無理強いしたから、言い出せなかったか? それならすまないことをした。よく考えれば深知留だってそんな存在の一人や二人いるだろうし、そもそも最初からその存在を聞くべきだった。俺のミスだよ」
深知留は環が見ていないと思いながらも、そうじゃないとばかりにその首を大きく横に振る。
そして、誤解を解きたい、その一心で深知留は必死に言葉を紡ぎ始めた。
「環さん、違うんです。彼は恋人とかそんなんじゃなくて……あの時はわたしのコンタクトがずれて、それを彼が見てくれて……別に、キスしてた訳でも何でも無くて……」
端的に分かりやすく説明しようと思うのに深知留の口は思うように回らない。
さらに、話を聞いている様子を微塵も見せない環に、何とか聞いてもらわなければ、と変な焦りばかりが彼女を支配する。
「あの……とにかくあれは誤解で……その……恋人もキスも…………」
「もういい、深知留」
一生懸命に説明しようとする深知留を、環の冷めた声が遮った。
「言い訳は必要ないよ、深知留。俺に取り繕う必要なんてどこにもない。君に彼氏がいようがキスをしようが、悪いけど俺には関係ないんだ。だって、俺たちは恋人同士でも何でもない。所詮、仮初めの関係、だろう? 君も以前そう言ってたじゃないか」
環はそう言うと、眉間に皺を寄せて面倒くさそうに溜息を吐いた。
「…………」
酷く冷たい声と煩わしそうな環の仕草に、深知留はもう何も言えなかった。
(環さん……すごく、迷惑そう……)
それを感じ取ったら、もはや何かを言うことなどできなかった。
押し黙ってしまった深知留に、環は続ける。
「それから、急な仕事が入ったからしばらく家には帰れなくなった。心細ければ夜は義姉さんに傍にいてもらうと良い。恋人といたいだろうが、十四日までは自粛してくれないか。本当は恋人役も解放してやりたいけど、ここまで来たことだし務めてくれるね? 今投げ出されても俺も困るんだ」
環は深知留の反応を確認する風でもなく、パソコンの電源を落とし、必要な書類を整えると席を立つ。
深知留は呆然としたまま、環のそれを見ていることしかできなかった。
つい先ほどまでどうやって誤解を解こうとそればかりが頭を支配して興奮していたのに、今の深知留は嘘のように意気消沈していた。
環は部屋の戸口まで行くと、そうだ、と静かに声を上げた。
深知留は油が切れて軋むロボットのようにゆっくりとその方向へ顔を向ける。
「深知留……昨日の晩のことだけど……悪いが、忘れてくれないか?」
「え……?」
掠れた声が深知留の口から零れ出る。
「少し飲み過ぎていてね。単に女が欲しかった、それだけなんだ。捌け口に君を選ぼうとして悪かった。……忘れてくれ。前に言っただろう? 俺だって男だ、何するか分からない、って」
環はそれだけ言うと、結局深知留と一度も視線を合わせないまま部屋を出て行った。
残された深知留は、力が抜けてしまったのか、その場に崩れるようにぺたんと座り込んだ。そして、瞬きさえも忘れて環が出て行った戸を見つめていた。
その脳裏に浮かんでは消えていくのは、今まで聞いたこともないような冷たく低い声の環の言葉……
『君に彼氏がいようがキスをしようが、悪いけど俺には関係ないんだ』
同時に巡るのは彼の煩わしそうな仕草……
「わたし、環さんに……嫌われちゃったかなぁ……?」
誰も答えてくれやしない疑問を、深知留は空中へ投げかけた。
数拍ほどの間を置くが、もちろん答えはない。
だから深知留は自分で答えを出した。
「嫌われたって……関係ないよね……だって…………」
今度は別の環の言葉が深知留の脳裏を過ぎる。
『俺たちは恋人同士でも何でもない。所詮、仮初めの関係、だろう? 』
恋人同士でも何でもない、仮初めの関係――
そんなの、分かっているつもりだった。
だから深知留は、これまでに何度も何度も自分で自分に言い聞かせてきた。
自分と環は偽恋人なのだと。
それに環の言った通り、キスを拒んだ時だって深知留は確かにそういう趣旨のことを口にした。
そのくらい十分に理解していたはずだった。
それなのに……
『俺たちは恋人同士でも何でもない』
その一言を環の口から聞いた瞬間、深知留は改めて思い知らされた気がした。
見ているようで見ていなかった、分かり切っているようで目を背けていた現実……それを、目の前に突きつけられた気がした。
それも、環本人によって。
深知留はいつの間にか溢れ出そうになった涙を、上を向いてやり過ごそうとする。
「そう……だよね。わたしたち……仮初めの関係、なのよ……」
深知留は震える声でその言葉を繰り返し、改めて理解しようとた。
「単なる……偽恋人、だもん……ね……。そんなの……初めから……分かってた、事じゃない。今更……知ったことでも……ないじゃない……」
いつの間にか深知留の手は首筋のキスマークを押さえていた。それはまるで、何かに縋るように。
そして、
(分かってるのに……どうして、こんなに……苦しいの…………?)
(何でこんなに……胸が痛いの……?)
深知留はその胸に感じる苦しみと痛みを癒すように涙を流し、その理由を探そうとした。
何で、どうして……それを飽きるほどに自問し続けた末、彼女の中には一つの結論が浮かんだ。
(あぁ、そうか……わたし、環さんが……好きなんだ…………)
好きだからこそ息が詰まる様な苦しさを覚え……
好きだからこそ胸は切り裂かれる様に痛む……
胸の苦しみと痛みを狂おしいほどに自覚した時、人は初めて、恋という感情を認識するのかもしれない。
