ドアの隙間から見えた情景に深知留は思わず息を呑み、慌ててその口元を手で押さえた。
部屋の中には案の定環がいる。
しかし、そこにはもう一人……
環にしなだれかかる髪の長い女性がいたのだった。
(何……これ……?)
深知留は瞬きもできずに中を見ていた。
「環……環ぃ……」
女性はただ環の名を呼んで彼に縋る。
「少し落ち着け……」
環はゆったりとした声で宥める。その女性を優しく抱き留めながら。
深知留はそこから目を反らせなかった。
見ては駄目だと思うだけ、瞬きさえすることができない。
女性は嗚咽を漏らしながら泣いているようで、環に抱かれるその肩は小刻みに震えている。
そして、深知留が女性から環へと視線を動かした次の瞬間、
「大丈夫だ、ミチル……」
聞いてはいけない一言を、聞いた気がした。
◆◆◆
(な……に……?)
(一体……何な……の……?)
深知留は、元来た道を懸命に走っていた。震えるその手で口元を押さえたまま。
脳裏に甦るのは部屋の中の出来事……
嗚咽を漏らしながら環に縋る女性。
それを優しく抱き留める環。
そんな彼の口から零れたのは……
『大丈夫だ、ミチル……』
その言葉が終わるか終わらないかのうちに、深知留はその場を去った。
何も考えたくなかった。
それなのに、一つの現実が深知留の中で形成されていく。
(環さんと……恋人…………)
同時に、ぶわっと視界が歪み出す。
そのまま無我夢中で廊下を走り続けて、深知留はエレベーターへの最後の角を曲がった。
その時だった。
ドンッ
衝撃を受けて深知留は足を止める。
「危ないじゃないか……」
深知留は誰かにぶつかったようだった。
慌てて顔を上げると、何とそこには政宗がいた。
「……あれ、深知留さん……?」
政宗を認識した深知留は、慌てて涙を拭った。
「環様の所へいらしたのですか?」
「……その……ちょっと用事があって……」
深知留は涙に気づかれないよう深く俯き、何とか取り繕う。
「環様なら今役員室に……」
「あの……会えませんでした。お客様が……いたみたいで」
深知留は政宗を遮るように言った。
政宗はそれに少しばかり考える仕草を見せる。
「よろしければ、別のお部屋でお待ちになりますか?」
「良いんです。……大丈夫ですから。すみません、わたし急ぎますから……」
深知留は俯いたまま、政宗の横を通り過ぎた。
しかし、
「あの……吉里さん」
深知留は走り出そうとした足を止めた。
政宗は「何でしょう?」と応じる。
「……わたしが来たこと、環さんには……黙っていていただけませんか?」
深知留は背中を向けたまま言った。
その背中がわずかに震えていることに、政宗は少し前から気づいていた。
「よろしいんですか?」
「はい……。お忙しいところを……煩わせたく……ないんです。それ……では、失礼…します」
深知留は耐えきれずにポロポロと流れ落ちて止まらない涙を拭いながら、くぐもる声で言葉を紡いだ。
言葉を終えると、深知留はそのまま角を曲がってエレベーターに飛び乗り、一階のボタンを押しながらその壁に崩れるようにもたれ掛かった。
一方、政宗は深知留の背中が消えていった方向をジッと見ていた。
(お客様ねぇ……。確か今は彼女がいるはずだが)
政宗は時計を確認し、再びその視線を深知留の消えていった方向へと戻す。
(泣いてた……な。何を見たんだか……)
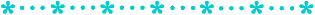
数十分後、政宗が役員室へ戻ると、そこにはもう環の姿しかなかった。
「失礼します。必要な書類を揃えてきました」
政宗はノックもそこそこに役員室へと入る。
環は重厚な作りの椅子に腰掛け、窓辺を向いていた。振り返るようにして政宗から書類を受け取ると、それに軽く目を通しながら再び窓の方へと体を向ける。
「状況はあまり芳しくないのですか?」
「……え?」
政宗の言葉が耳に入っていなかったのか、数拍の間をおいて環は尋ね直した。
「ミチルさんのことですよ」
「深知留がどうかしたのか? 屋敷から何か連絡が?」
環は驚いたように書類から目を上げ、焦りの混じった視線を政宗へ向ける。
「いえ……今、いらしていたミチルさんの話です」
「え、あ、あぁ……ミチルか。そうだな……あまり良い状況とは言えないだろうな」
環はようやく話が飲み込めたようで、再び視線を書類へと戻す。
「こちらとしては、もう打てる手は打ったんだ。あとは弁護士の手腕に掛かっているよ」
環は書類を机の上に置いた。しかし、何か仕事を始めるわけではなく、元のように窓の外を眺め始める。
政宗はそんな環の考えを見透かすかのように、彼を注意深く見ていた。
(また、深知留さんのことでも考えていらっしゃるのですか?)
政宗は心の内で環に問いかけた。
彼が、また、と言いたくなるのも無理はない。
ここ数日、環は仕事は難なくこなしていたが心はここにあらずの状態であった。
恐らくその原因は深知留で間違いなかった。
そもそも環がおかしくなったのは、深知留が恋人と一緒の所を見てからだ。
その翌日、政宗は深知留の首筋にキスマークを見つけた。環は、と言えばあれだけ自宅に帰ることに執着していたのに、どうしたわけか以前のようにホテルでの生活を始めた。
二人の間で何があったのか、勘の良い政宗は大体の所予測できた。
政宗でなくとも、本人に自覚がないだけで環の様子がおかしいことには雅も気づいていた。その雅は、政宗にコッソリと「深知留ちゃんと喧嘩でもしたのか?」と尋ねてきたほどだ。なぜかと問えば、「鈴が深知留ちゃんの様子が変だと言っていた」と。
答えようのない政宗は「まぁ、そのようなところです」と誤魔化すより無かったのだが。
当の環の脳裏を支配するのは、やはり政宗の想像通り、深知留の顔であった。
暗闇の中恋人と唇を重ねる深知留のシルエット、そして、あの日、気づいた時には乱れた姿で泣き顔を見せていた深知留……
それが浮かんでは消えていく。自分が狂っているのではないかと思うくらい執拗に。
再び脳裏に浮かんだその深知留の顔に、環はギュッと拳を握りしめた。
一時の感情に駆られて、酒の力に呑み込まれて深知留に酷いことをしてしまったと、環はあれから何度も後悔した。
そして、翌日には素直に潔く謝れば良かったのだとも思った。
しかし、あの時深知留が一生懸命に恋人の事を取り繕おうとする姿を見たら、環は苛々して仕方がなかった。誰か他の男を思い、庇う彼女の姿など見たくなかった。彼女が別の男の物なのだと思い知らされるようで。
その時、環はようやく自らの気持ちに気づいた。いや、気づかざるを得なかった。
深知留を好きなのだというその気持ちに。
だが、気づいたところで彼女は既に……人ノモノ。
――何故?
――どうして?
そんな疑問符を何度投げかけても、それは今更抗いようもない事実。
認めたくないのに認めざるを得ない事実。
――遅すぎた
それしか答えは見つからなかった。
深知留を好きだと気づくのも。何より、彼女と出会うのが、遅すぎたのだと。
そんな後悔をしたってどうしようもないことは分かっていた。しかし、それで納得できるほど環は出来た人間ではなかった。
すっかり感情のコントロールを見失った環は、最後は八つ当たり同然の突き放すような言い方しかできなくて、そのまま何もかもから逃げるように家を出た。
負け犬――そんな風に罵られようとも、あの時はそうすることしかできなくて。
環は窓の外、ネオンの瞬く夜景に向かって深い深い溜息を吐いた。
ふと脳裏に浮かんだのは、やはり、あの日のあられもない姿の深知留と、最後に見た怯えたような顔。
(あんな顔……させたくはなかった……)
見たいのは、思い出したいのは深知留の笑顔。
それなのに、環の記憶は怯えた深知留の顔しか呼び起こさない。
だからせめて、
(明日は……笑ってくれないだろうか……。他の男のじゃなく、俺だけのために。最後に……一度だけで良い……)
都合のよすぎる願いだと、今更無理なことだと思いながらも、環はそう願わずにはいられなかった。
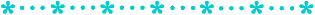
(自分だって……本当の恋人が……いるんじゃない……)
止めどなく流れる涙を拭ってひと晩をすごした深知留は、その答えを導かざるを得なかった。
環が女性と抱き合うシーン……それが頭に焼き付いて、離れない。
考えてはいけない、と思えば思うほどそのシーンは鮮明に映し出される。
それはもはや記憶を超越しているかのようで、その時の情景にあった全ての色味を深知留は詳細に思い出せた。まるでその瞬間、彼女の頭がシャッターを切ってしまったかのように。
(あの時、部屋の中なんて覗かなければ良かった……)
そんなこと、今更後悔したって仕方がないのに思わずにはいられない。
深知留はそんな風に一晩中思考と後悔を重ねた末、
(……失恋、しちゃった……)
そう言って納得するより無かった。
そして時折思い出したように脳裏に流れる環の声……
『大丈夫だ、ミチル……』
(ミチル……か。恋人、わたしと同じ名前なんだ……)
(環さんが……傍にいるべきミチルは……わたしじゃない…………)
深知留と環……
二人は一体いつから、どうして、釦を掛け違えてしまったのだろう。
