結局その日は大学に行くこともできず、深知留は気が付けば人形のように飾り立てられて雅やかなパーティー会場に連れて行かれていた。
「深知留ちゃん綺麗よ」
そうにこやかに褒めてくれる鈴に、深知留はなけなしの力を振り絞って笑顔を返しながら、
(こんなにいい人を騙したから……罰が当たったのかな?)
そう思った。
そして、パーティーが始まると今度は来場者たちの気遣いが深知留を追いつめた。
彼らが深知留と環をお似合いのカップルだよ、と褒めれば褒めるだけ、お互い素敵な人と巡り合えたね、と言えば言うだけ、深知留の心は悲鳴を上げた。
(わたしは……環さんの隣に立つべき相手じゃないのに……)
そんな負の感情と、
(これが、本当だったら……どんなに幸せなんだろう…………)
もはや諦めたはずの決して叶わぬ望みが深知留の中でせめぎ合う。
そんな気持ちを押さえ込むかのように、深知留は必死に鉄壁の笑顔を作り上げて受け答えていった。誰にも、その気持ちを気取られないように。
そして、常に隣にいる環を深知留は一目たりとも見ることができなかった。見てしまえば必死で抑えている気持ちが暴発してしまいそうだったから。
そうしてまでなぜ、深知留は忠実に環の恋人役をこなそうとしているのか……
深知留自身、こんな自分を馬鹿だと思い、滑稽だと罵りたかった。
本当は投げ出して、逃げてしまおうかと夕べから何度も思った。今この瞬間だって悲鳴を上げる心のままに逃げ出してしまいたかった。
しかし、深知留は最後の最後で好きな人が困る顔は見たくなかったのだ。
お日様のような環の笑顔を見ることはもう諦めた。もう叶わぬことだと理解した。
だからせめて、もう環の困った顔だけは見たくなかったのだ。
それが一晩泣き過ごした深知留が下した決断。
(これはお礼……色々お世話になったことへの恩返しなの)
深知留は逃げたい衝動に駆られるたびに、そう何度も自分に言い聞かせていた。
そして、今だけ我慢すればいい、と。
由利亜に言われて我慢をやめようと思ったのに、やはり自分にはそれがお似合いなのだと思うと溜息がこぼれる。
結局、人には向き不向きがあるということなのだ。
「……る……ちる……深知留?」
「え? ……あ、はい」
気を抜いていた深知留は環の呼びかけに気づかなかった。
「深知留? どうかしたのか?」
「いえ、何でも」
深知留はドレスを翻し、すぐに環の元へと駆け寄る。
「深知留、蓮条夫妻が君に挨拶をしたいって。それから深知留……」
来場者たちからかけられる言葉の他、もう一つ深知留には耐え難いことがあった。
それは、たった三文字の言葉。
深知留、ミチル、みちる……
そのたった三文字が環の口から紡がれるたび、深知留は胸が締め付けられる思いがした。
ありきたりだが、この世からその三文字が無くなって欲しいとさえ思うほどに。
「深知留、気分でも悪いのか?」
環はそんな深知留の心情も知らずにただ心配そうに彼女の顔をのぞき込む。
「……大丈夫です。ただ、こういう場には慣れなくて……」
――ねぇ環さん、貴方は一体、誰を呼んでいるんですか?
聞けない質問を飲み込んで深知留は環に笑顔を返す。
お見合い話を頼まれた日、深知留は苦労して『環さん』と呼んだのに対し、環は何の苦もなくさらりと『深知留』と呼んだ。
大人の余裕だ、とあの時は思ったが、それが呼び慣れた恋人の名前だとしたらそれは簡単に納得がいった。
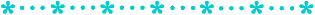
パーティー会場を中座した深知留は、窓辺から外を眺めていた。
「お前……大丈夫か?」
追って出てきたのは蒼だった。
「今にも倒れそうな顔してるぞ」
「大丈夫。少し寝不足なだけ。それと、人に酔ったの」
深知留は窓の外に視線をおいたまま答える。
「由利亜が……心配してたぞ?」
「落ち着いたら、そのうち連絡するって伝えておいて」
やはり、深知留は蒼の方をチラリとも見ない。
その後、二人の間には沈黙が流れた。
蒼も一緒に窓の外へと視線を向けると、そこには都会の煌びやかな夜景が広がっている。
しかし、深知留はただ眺めていると言うだけで、そのうちの何かを見ているわけでは無いようだった。
「ねぇ、蒼……」
深知留が消え入るような声で切り出したのは随分と経ってからだった。
「……環さんに恋人が居るって、蒼知ってたでしょう?」
「お前何でそれ……」
蒼は思わずその目を丸くする。
「やっぱり。だからあんな事言ったんだ。……もっとダイレクトに言えばいいじゃない」
一瞬、それは蒼を責め立てているようにも聞こえたが、深知留はそんなつもりではないようで表情には自嘲の笑みが混じっている。
『お前……龍菱さんのこと、あまりのめり込むなよ?』
少し前、蒼からそれを言われた時、深知留は何のことだか分からなかった。
あの時はただ、毎日環といることだけが楽しくて嬉しくて、そればかりに夢中になっていて周りが見えていなかった。
既に事情を知っていた幼馴染みが、警鐘を鳴らしてくれていたのにも関わらず、深知留は気づきもしなかったのだ。
冷静になればよく分かった。
不器用な幼馴染みは深知留を傷つけないよう、できるだけ遠回しに、それでも救おうと努力をしてくれていたのだ。
(あの時に……何で気づかなかったんだろう……)
今更しても仕方のない後悔が深知留の心に広がる。同時に、最近後悔ばかりをしていると思う。
「少し前、龍菱さんと女性が一緒にいるところを見たんだ。ただ俺はそれを見ただけで、確信はなかった。やっぱり彼女が恋人だったのか?」
「それ、髪の長い……綺麗な女性じゃない?」
深知留の問に、蒼は静かに頷く。
深知留はそれを確認するとくるりと振り返り、窓辺に寄りかかるようにした。
「用事があって会社に行ったら……二人が抱き合ってた。それを偶然、見ちゃったの」
「そうか……」
まるで泣くように笑ってみせる深知留に、蒼はそれ以上言葉が出なかった。
「見ちゃうって結構、決定的、だよね。誰に何を聞くより、一番真実味がある」
「ごめん、深知留……俺がもっと早く教えるべきだった」
蒼の謝罪に深知留は、あなたのせいじゃないとでも言うように俯いたまま大きくかぶりを振る。やはりその表情は今にも泣きそうである。
いつでも凛として強い幼馴染みがそんな顔をしているのを、蒼は初めて見た気がした。
「深知留……やっぱり、好き……なのか? 龍菱さんのこと」
その問いに、深知留はすぐには答えなかった。
蒼もそれを急かすことはしない。
それからたっぷり数十秒の間をおいて返ってきたのは、
「そうかも、ね……。ううん、そうだった、かな?」
そんな答えだった。
まるで人ごとのような答え。
それに蒼は顔を顰める。
「何だよそれ。深知留、お前……」
「蒼……昔わたしの言ったこと……覚えてる?」
少し声を張り上げた蒼を深知留は遮った。
「…………」
蒼は言葉を止め、ただ深知留を見つめる。
「夢物語みたいな……幻想曲のような恋をしたいって言ったわたしに、蒼、こう答えたよね? 夢物語なら覚めたら終わるって……本当にその通りだった」
深知留はいつの間にかその視線を持ち上げ、会場内へと向けていた。
その目は虚ろのようにも見え、まるで夢でも見ているかのようだ。
「わたし、希望通り良い夢が見られた。絶対出会えないような人と出会って、一緒にいて、こんな綺麗なドレスまで着せて貰って、楽しかった。……でも、蒼の言う通り、夢は必ず覚めてしまう」
「深知留……」
「このドレスを脱いだら、夢を見る前と何も変わらない元の生活に戻るだけ……。環さんと会う前の日常に……戻るだけ。まるで魔法の解けたシンデレラみたいね」
深知留は蒼に言葉を許さずに言い切ると、フッと寂しそうな笑みを零した。
別に何も変化はない。これが終われば環と出会う前の単調な生活に戻る、ただそれだけのこと。
そう思うのに、深知留の心はまるで嫌だとでも言うかのようにざわつく。
嫌だと思ったところで、もうどうすることもできないのに。
そんな深知留の視線が無意識に追うのは、会場内で遠目に見える環の姿……
蒼はそんな深知留を無言のままジッと見ていた。
