五月、季節でいえば春も後半――町中は様々な植物の緑が競い合うように茂っており、深呼吸をすると植物独特の香りが鼻腔に広がる。日差しが強い日などはもう長袖では汗が滲み出るような温かさだ。
そんなある日の午後、
そもそも用事があったのは京で、特にこれといって読みたい本もなかった由利亜は京が会計に行っている間目的もなく店内をふらふらと歩き回っていた。
そして週刊誌の積んである棚にさしかかった時、視線を遊ばせていた由利亜の目にある文字が飛び込んできたのだ。
『財界の若き獅子、華宮グループ次期総帥の素顔を直撃!!』
由利亜はその文字に歩みを止められて週刊誌を手に取り、その記事が書かれたページまでパラパラとめくる。
華宮グループ――由利亜の興味を引いたのはその固有名詞。
由利亜の父、崇は華宮グループの一人息子である。いや、正確には――一人息子であった、だ。
由利亜はその事実を随分と昔に父親本人から聞かされていた。そして、訳あって既に絶縁状態であるということも。
だからコレといって由利亜と華宮家の間にはなんの関係もないのだが、単なる好奇心がくすぐられたのだ。
目的のページを開くと、次期総帥と言われる割にはずいぶんと若い男性の写真が掲載されていた。
由利亜としては普通におじさんを想像していた。まあ『若き獅子』というくらいだから一応は三十も前半のそこそこ若いおじさんを想像していたわけだが、そこに載っていたのは由利亜とさほど変わらないような男性である。
男性は線の細い綺麗な顔立ちをしており、世間一般では美男子と呼ばれる部類の者だった。写真だけ見れば絶賛売り出し中の芸能人のようにも思える。
由利亜が同じページ内にあるインタビューの内容を読み始めようとしたその時だった。
「おまたせ。……何これ。次期総帥は現役大学院生?」
会計を済ませて由利亜の元に戻ってきた京は、由利亜が食い入るように見ていた記事の一部を読んだ。
「あ、これ
「京……知ってるの?」
由利亜は後ろから週刊誌を覗く京を振り返る。
「うん。いろんなパーティーでよく見かけるわよ。以前、パパのところに挨拶に来て紹介されたことがあるのよ。まぁそんなに親しい訳じゃなくて、会えば話すくらいの仲だけどね」
「……そうか、そういうつながりね。京も一応天下の樹月グループご令嬢だものね」
「あら、失礼ね。一応って何よ」
京は頬を膨らませて怒る素振りを見せた。
由利亜の親友、樹月京は樹月グループの末っ子次女である。その父は樹月グループの総帥で母は前官房長官の娘という正真正銘の超サラブレッドなお嬢様だ。
樹月グループは華宮と同様、鉛筆からロケットまで幅広く事業を展開させており世界的に有名である。つまり、『華宮』と『樹月』は現代日本の財界における二大巨頭といったところだ。
そんな超ハイレベルなお嬢様である京だが、彼女は日常生活の中でコレといってお嬢様らしい素振りを見せない。
そもそも二人の通う高校は決してお嬢様が通う高校ではない。近場にはお金持ちの子息や令嬢が通う私立高校もそれなりにあるのに、京は『そんなところには行かない』と今の公立高校を選んだ。それも猛勉強をして受験をパスして、だ。
そして、学校への登下校も普通ならば高級車で送迎されるであろうところを、京は一般庶民と同様に電車通学をしている。ごく希に実兄の高級外車で送迎をしてもらっているが、それも妹思いの兄がどうしてもと譲らなくて、とかそんな理由だ。
京が上流階級仕様の生活を嫌うのには多々事情があるのだが、その一つとして本人曰くとにかく『極力普通に暮らしたい』のだそうだ。
そのため、京は普通のお嬢様なら考えられないような学校帰りの寄り道だって今日のように珍しいことではない。そんな風だから、彼女がお嬢様だということはついつい忘れられがちになってしまう。
「なかなかいい男でしょ?」
「そうね、芸能人に負けないくらいいい顔してるわ」
「彼、モテるんだよ。でも、不思議と女の噂は一度も聞いたことないんだけどね。もう決まった婚約者でもいるのかもね」
由利亜は京の話を半分以上聞き流しながら週刊誌に見入っていた。
(この人がお祖父様の跡継ぎ……お父さんの代わり、か…………)
「……利亜、……由利亜!」
「は、はい?」
すっかり物思いに耽っていた由利亜は京の呼びかけに慌てて返事をした。
「なぁに、そんなに真剣に見入っちゃって。惚れちゃった?」
京は冗談交じりに笑いながら由利亜の顔を覗き込んでいる。
「そんな……違うわよ。次期総裁、って割には随分若いと思ってね」
「あぁ、詳しくは知らないけど、前の総帥が彼を養子にしたのよ。元々前総帥には一人息子がいたんだけど、その息子がメイドと勝手に駆け落ちして絶縁状態になったから、蒼さんを養子に迎えたって聞いたことがあるわ」
「へぇ、養子にね。……この世界も色々複雑なのね」
(……一人息子はメイドと勝手に駆け落ち、か)
由利亜の中に京の言葉の一部が残った。
京は由利亜と華宮の関係を知らない。由利亜は京に華宮家との血縁について話したことはない。
世の中には知らなくて良いこともある。たとえそれが親友同士でも、である。
だから、まさか京も自分の隣に華宮家の直系の孫娘がいるとは思っていないだろう。今のもそれ故の発言だ。
そもそも樹月と華宮は財界の二大巨頭と呼ばれるだけあって、昔からのライバル同士なのだ。その事情を踏まえれば、由利亜が京に真実を話せるわけがなかった。
きっと親友でなくなってしまう――由利亜はそんな結末に怯えていた。
「由利亜、もう帰ろう」
「うん」
由利亜は週刊誌を元あった場所へと戻した。
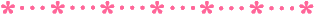
「お父さん、お母さん、久しぶりだね。元気だった?」
由利亜は京と分かれた後、自分の住むアパートの近くにある共同墓地に寄った。
書店で華宮の名前を目にしたことで、由利亜は妙に二人のことが気になったのだ。
四年前、由利亜の父は出張先のニューヨークに母と二人で行き、帰りの飛行機で事故にあって亡くなった。
夫婦とも親戚と呼べるような存在を持たなかったため、由利亜はその時から天涯孤独の身となったのだ。
墜落事故で遺体は全焼し骨も何も残らなかったが、二人の親しかった友人や同僚の人達が一人娘の由利亜のために、と形だけではあるがこうしてお墓だけを整えてくれた。
由利亜は両親の墓に向かって手を合わせ、順に心の中で話しかけていく。
――ねえ、お父さん?
お父さんの代わりにお祖父様が養子をとったこと知っていた? 今日見たけれど、まだすごく若かった。
――ねえ、お母さん?
天国でも大好きな人と一緒で幸せ? ……きっと、すごく幸せだろうね。
『お母さんはね、大好きなお父さんと……最愛の人と一緒になれたから幸せなのよ。だから由利亜も、いつかそんな人と出会って幸せになりなさい』
不意に由利亜の脳裏に母の口癖だった台詞が浮かんだ。
同時に今まで閉じていた目をゆっくりと開く。
由利亜の両親は本当に仲が良かった。夫婦はいつも一緒で互いを大切にし、それは時に子供の由利亜が嫉妬をするほどに。
結局最期の最期まで二人一緒だった父と母。死さえも彼らを引き裂くことは不可能だった。
両親が死んだ当時、由利亜は悲しみに沈んで毎日泣いて暮らしていた。しかし、今はそんな二人を少しだけ羨ましく思っている。
「ねぇ、お母さん。わたしの運命の人はどこにいるのかしらね?」
由利亜は春の温かい風に吹かれながら、墓前で二人の思い出に耽っていた。
「……さてと、そろそろ帰るね。また来るから」
しばらくして由利亜は再び墓前で手を合わせ、二人に別れを告げた。
不意に由利亜の脳裏に母の口癖だった台詞が浮かんだ。
同時に今まで閉じていた目をゆっくりと開く。
由利亜の両親は本当に仲が良かった。夫婦はいつも一緒で互いを大切にし、それは時に子供の由利亜が嫉妬をするほどに。
結局最期の最期まで二人一緒だった父と母。死さえも彼らを引き裂くことは不可能だった。
両親が死んだ当時、由利亜は悲しみに沈んで毎日泣いて暮らしていた。しかし、今はそんな二人を少しだけ羨ましく思っている。
「ねぇ、お母さん。わたしの運命の人はどこにいるのかしらね?」
由利亜は春の温かい風に吹かれながら、墓前で二人の思い出に耽っていた。
「……さてと、そろそろ帰るね。また来るから」
しばらくして由利亜は再び墓前で手を合わせ、二人に別れを告げた。
