両親の墓前を離れて歩いていると、墓地の外周の道に黒塗りの高級車が何台も止まっているのが見えた。
どこかのお偉いさんでも亡くなったのだろうか、と由利亜は勝手な想像をしながら、墓地を出て通り道となるお寺の中庭に入った。
中庭に入ってすぐ、由利亜は庭の片隅に生える欅の大木に一人の男性が俯き加減にもたれかかって立っていることに気づく。
由利亜は一度だけ男性を見て、彼のすぐ前を通り過ぎようとした。
そして、それは由利亜が男性と擦れ違おうとしたその時だった…………
「華宮早次郎の直系の孫娘……榊、いや華宮由利亜。華宮崇の一人娘だな?」
一瞬、由利亜は何が起こったのか理解することができない。
ただその言葉に驚き、由利亜はまるで魔法でも掛けられたかのようにその場で固まるように歩みを止める。
「……あなた……」
――一体誰ですか?
由利亜がそう言葉を紡ごうとした時、一瞬強い風が吹き、欅の木をザァッと揺らす。
風が収まった後、由利亜は乱れた髪をかき上げ、再び男性へと視線を送る。
すると、彼の目はゆっくりと由利亜の顔に向けられる。
(────!!)
由利亜の視線は瞬時にしてその男性に釘付けとなった。
そこに立っていたのは、そう――先程由利亜と京が見ていた週刊誌の人物。
忘れようと思っても忘れられないあの顔…………
彼は華宮蒼、本人に間違いなかった。
短いようでずいぶんと長い沈黙が周りを包みこんでいる。
「三日後、忘れるなよ」
沈黙を先に破ったのは華宮蒼だった。
(え? 三日後……? )
由利亜はそれを理解することができなかったが、聞き直すことも動くこともできずにその場に立ち尽くしていた。
気が付くと、本堂の方から黒のスーツを着た大柄な男性が二人、こちらに走ってくる。
「蒼様、突然お姿を消されては困ります」
駆け寄ってきた男性のうち一人が華宮蒼に向かって言う。ずいぶんと探し回ったようでその呼吸はいくらか乱れていた。
大きくしっかりとした体格の男性たちは、スーツの上からでも鍛えられている感じが伝わってくる。その容姿から由利亜はボディーガードという名詞を連想する。
「こちらの方は?」
蒼に真っ先に声をかけた男性が、由利亜に視線を移す。
「何でもない。行こう」
蒼は目を細め、一瞬不敵な笑みを浮かべるとそのまま歩き出した。
しかし、彼らがいなくなってからも、由利亜はしばらくそこを動くことができなかった。
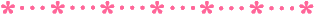
由利亜が自宅のアパートに帰ると、ポストにはいくつかのダイレクトメールに混じって一通の改まった白い封筒が入っていた。差出人の欄は――華宮本家。
由利亜は部屋に鞄を置くなりテーブルの上にあったハサミを乱暴に取って、急いで封を切った。そしてすぐに文面に目を通す。
文章は季節の挨拶から始まり長々と書かれていたが、要約すると今日から三日後の五月十二日、午後五時より華宮総本家にて早次郎の遺言発表が行われる、と記されていた。
(三日後……これだ)
華宮蒼のあの不敵な笑みがふと由利亜の頭に浮かぶ。
華宮グループ総帥、早次郎が持病の心臓病で突然亡くなったのは今から約一ヶ月前のことである。
彼の死は新聞やテレビのトップニュースで大々的に報じられたので、由利亜もそれはよく覚えている。
お通夜も葬儀も大きく行われたらしいが、由利亜がそこに足を運ぶことはなかった。だって、そもそも絶縁されている自分が行く義理はないから。
それに、早次郎と面識のない由利亜にとっては祖父が亡くなったというよりは財界のトップが亡くなったという感覚の方がしっくりときたのだ。
だから、もちろん由利亜はこの遺言発表にも出席するつもりはなかった。
(遺産なんて、誰が相続したってわたしの知ったことじゃない)
由利亜は部屋のソファーに横になると、ため息をひとつ吐いてクシャクシャに丸めた手紙をごみ箱に向かって投げた。
手紙はごみ箱の縁に当たり床に落ちたが、由利亜はそれを拾いに立つわけでもなくただ眺めていた。
華宮蒼の顔がいつまでも頭の中を駆け巡っていてなんだか変な気分だ。
ふと他のダイレクトメールに目をやると、その中に混じって薄いブルーの封筒があることに気づいた。
由利亜は飛び起きてすぐにその封筒を手に取る。その顔からは自然と笑みがこぼれる。
薄いブルーの封筒――それは由利亜にとって特別なものである。
差出人の名前は
差出人の詳しい素性を由利亜は知らない。分かっているのはその差出人が資産家の老婦人であり、昔、由利亜の父に世話になったということだけ。
手紙の内容はいつも同じで、由利亜を気遣う文面と銀行へのお金の振り込みの知らせである。
初めは由利亜も正体不明の差出人から支援を受けることを拒んだ。しかし、文面から滲み出る小夜子の人柄の良さと『是非恩返しをしたい』『奨学金と思ってくれればいい』という強い申し出に由利亜はついに断り切れなくなってしまったのだ。
しかしながら、由利亜は小夜子に会ったことはない。
『会わないこと、会いたがらないこと』
小夜子が一番初めに提示したその条件のために、由利亜は会いたいと思っても我慢してきた。そのため、手紙が来るたびに想像を膨らませ、由利亜は小夜子がどんな人物なのかを自分の中で楽しく想像していた。
手紙を受け取り、お礼の返事を送る――今となってはそれが由利亜の楽しみの一つだった。小夜子の手紙が来ると二週間が経ったことがわかる。二週間が経ちそうになると由利亜はそわそわしながらポストを見る。それがいつの間にか習慣となっていた。
しかし、その手紙は一ヶ月前に突然来なくなってしまったのだ。小夜子が体調を崩したのかとも思い、由利亜は数回手紙を送ったがそれにも返事は無かった。住所しか知らない由利亜は手紙を送るしか連絡する方法を思いつかなかったから。
本当ならば住所を探し当てて会いに行くことは簡単だったが、それでは小夜子との約束を破ってしまう。だからじっと小夜子からの手紙を待つしかなかったのだ。
由利亜は焦る気持ちを抑えながら久しぶりの小夜子の手紙を丁寧に開いた。
先ほどの華宮家からの手紙はあんなに乱雑に扱ったのに、と由利亜は自分でも笑ってしまう。
封筒とおそろいの薄いブルーの便せんには、ずっと連絡ができなかったことのお詫びと由利亜を案ずる内容が綺麗で繊細な字で綴られていた。
(よかった……小夜子さん元気だったんだ)
由利亜は手紙を読みながら安堵のため息を漏らした。
それからすぐに机に向かい、小夜子への返事を書き始めた。
