しばらく落ち込んだ後、夜風にあたって少し気分転換をしようと思った由利亜は部屋からバルコニーへ出た。
肌寒い空気がスッと頬を掠める。
(いくら京でもさすがに怒るよね……。騙していたも同然だもの……)
由利亜は再び大きなため息を吐いた。
(遺産相続に結婚……か)
二つの言葉が頭を駆けめぐる。
(お祖父様はどうしてわたしなんかに相続したのかな?)
由利亜の中にふと疑問が生まれた。
十七年間生きてきて、由利亜が初めてきちんと見た祖父の顔は遺影だった。正確に言えば、彼が亡くなった時に新聞記事やテレビのニュースで見たが、それはあくまで小さなカットである。
遺影の中の早次郎は眉間に深く入った皺が印象的で、由利亜はそこから頑固で融通が利かないというイメージを持った。しかし、顔立ちはどことなく父、崇に似ている気がした。
父と母を決して認めなかった人――由利亜はもっと厳格で近寄りがたい人物を想像していた。が、思った通り頑固そうではあったものの、その顔が崇に似ているせいもあってか由利亜は親近感を覚えたくらいだ。
(もし……お祖父様がお父さんとお母さんを認めていて、今三人とも生きていたら? どうなっていたのかな?)
突如湧き出た疑問であったが、答えはすぐに出た。
考えたところでどうなることでもないのだ。いくら考えても夢のような話。現実には決してあり得ないこと……
由利亜は考えを払拭するようにブンブンと頭を振る。
と、その時、
由利亜の手に持たれていた携帯電話がブルブルと振動して着信を告げる。
「もしもし、京!?」
着信先の名前を見て、考えるより先に由利亜は通話ボタンを押していた。
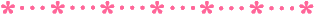
京は怒っていた。完全に。
由利亜が友達をやってきて既に十年近くが経過するが、その中でもトップレベルである。
「さぁ、由利亜。説明、してくれるわよね。わたしはあなたの口から直接事の次第を聞きたいの」
これ以上ないほどの笑みを浮かべる顔とは裏腹に、京の全身からは得も言われぬオーラが放出されていた。
あれから一晩が明け、時間は放課後、場所は京の指定により基が一人暮らしをしているマンションの一室。
由利亜はテーブル越しのソファに座る京に対し、背中に嫌な汗をかいている。
夕べの電話で、京は由利亜が謝りの言葉を述べるより先に一言言った。
『明日の放課後、時間を空けて。話はその時に聞くから』
で、今この状況というわけだ。
「良いのよ。遠慮しなくて。何でも言って。人に聞かれたら困ると思って、基お兄ちゃんに頼んで場所借りてるんだから、遠慮なんてしないでね?」
語調は語尾にハートマークが付きそうなくらい柔らかいのだが、とにかくそのオーラが怖すぎる。
「京、お前怖いよ。由利亜ちゃん、完全に怯えてるって」
京の隣に座る基が妹をなだめるように言うが、京はそれを目で射殺す。
今のこの京の状態……想像しようと思えばできたことだが、さすがの由利亜も恐怖を覚えていた。
昨日の夢によれば、京は寂しそうに泣いて去っていく予定だったのだが、まぁそんなわけもなく……。だいたい京の普段の性格を考えればあの夢は逆夢だと簡単に理解できたはずだ。
京がここまで怒る気持ちを由利亜は分からないでもなかった。とにもかくにも、今回は全て隠していた由利亜に非があるのだから……
由利亜は自分を落ち着けるように、基が出してくれた紅茶を一口飲んだ。
そして話した。
自分が誰の子か、昨日は何の日だったか、そして昨日あれから何が起こったのか――それらを順を追って説明していった。
ただ一つ、結婚の事を除いて。
「由利亜。わたしってそんなに信用ならないわけ?」
話を聞き終えた京はまず初めにそう言った。
「違う。京のことは信用してる。誰よりも信用してるわ」
「じゃあ、何で黙ってたの?」
「それは……」
由利亜は言いかけてやめた。
「それは、何? 黙っていたのが信用してない証拠でしょ?」
京はわずかに声を荒げた。そして、少しだけ寂しそうな顔をした。
「わたしはずっと由利亜を信用して、一番の親友だと思っていたのに……」
辺りに短い沈黙が走る。
その時、寂しそうな顔をしたのは由利亜も同じだった。
「……だからよ。だから言えなかったんじゃない」
由利亜は京を見ながら呟くように沈黙を破った。
そして、堰を切ったように話し出す。
「京がわたしを信用してくれてるから。だから言えなかったのよ。……初めから自分の素性を知ってたらわたしだって京に教えたわよ。でもそれを、京と知り合ってもう離れられないくらい仲良くなった後に知ったから、だから言えなかったのよ。自分を信用してくれて、一番の友達だって言ってくれる子に、ある日突然『わたしはおたくのライバルグループの孫娘です』なんて言えたと思う? ……そんな裏切り行為みたいなことできるわけないじゃない!」
「……ゆ、由利亜?」
今までため込んでいたものを一気に放出するように話し出した由利亜を、京は唖然として見つめていた。
しかし、由利亜は止まらない。
「そりゃわたしなんて単に血がつながってるって事実だけで、これまでお嬢様も閨閥も関係なかったわよ。でも、もしそれで京がわたしを見限って、離れて絶交なんてされた日にはどうするのよ? 責任取ってくれるの? そんな風になったらわたしどうやって生きていったらいいのよ? ……無理に決まってるじゃない」
由利亜の言葉が止まると辺りは再び沈黙という名の静けさに包まれた。
息継ぎさえ忘れて話しきった由利亜はゼイゼイと肩で呼吸をしていた。その瞳にはわずかに涙が浮かんでいる。
最後の方は興奮しすぎて、由利亜自身、自分でも何を言っているのかよく分からなかった。意味の分からないことも多く言った気がするが、言いたいことは言った。由利亜が京に伝えるべき事は言った。
「ぷっ……」
しばらくの沈黙の後、吹き出す、というなんともその場にそぐわない行動で沈黙を破ったのは基だった。
基はそのままげらげらと笑った。お腹を抱えて本当に苦しそうに、でも楽しそうに。
しこたま笑った後、基は言った。
「京、お前、愛されてるねぇ、由利亜ちゃんに」
基は笑いすぎて出てきた涙を拭う。
「由利亜ちゃんも、大丈夫だよ。京はそんなことで由利亜ちゃんと絶交なんかしたりしない。どちらかと言えば、由利亜ちゃんが自分から離れていっちゃう……って夕べ一晩中ここで泣いてたくらいだから」
「ちょ、ちょっと……お兄ちゃん!!」
京は突然の兄のカミングアウトに動揺する。
「だって本当のことだろ? そいうの、きちんと言わなきゃ伝わらないよ。だからお前たち、今もこうしてお互いのことこれ以上ないくらい思いあってるのに、通じてないんじゃないか。そんなのもったいないだろう」
基は妹の頭をポンポンと叩いた。
京は少し膨れてみせる。
「てわけで、由利亜ちゃん。君が華宮の直系だとしても、そんなの京には関係ないんだ。もちろん俺もね。世間一般では樹月と華宮の不仲説が定着しているけれど、それだって言うほどのものじゃない。特に蒼さんが華宮を取り仕切るようになってからは、業務提携も進んでかなり歩み寄ってるよ」
基は穏やかな表情で由利亜に言い聞かせるように話した。
「そうよ。だいたい樹月グループをわたしが継ぐ訳じゃないんだから、例え華宮とうまくいってなくてもそんなのわたしには関係ないわ。だいたい、由利亜はわたしのこと家柄で友達を切り捨てる人間だと思ってたわけ? ……悪いけど、誰に頼まれたってわたしはあんたと絶交なんてしてやらないんだから」
拗ねたような仕草の京を見ながら、由利亜はふふっと笑みをこぼした。
そうだった――京はそんなことで友達を取捨選択するような子ではない。
失うことばかりに目線が行き過ぎて親友の本来の姿を見失い、一番大切なことを信じられなくなっていた自分を由利亜は少しだけ後悔した。
