「樹月基と、付き合っているのか?」
竜臣が運転する車に戻った後、蒼はまるで何事もなかったかのように先ほどまで手にしていた書類に再び目を通していた。
「…………」
由利亜は無言のまま仏頂面でそっぽを向いた。
基の車から引きずり出されてこの車に連れ込まれ、開口一番がこれである。謝罪の言葉を口にするでもなく、これである。
由利亜がその不当な扱いに憤慨するのも無理はなかった。
「聞こえないのか? 質問に答えろ」
蒼は書類から目を離さず声を少し苛つかせる。
「お答えする義務はありません」
由利亜も由利亜で窓の外から視線を動かさない。
二人の間にしばしの沈黙が走る。本当は運転席に竜臣がいるが、そこと後部座席の間は防音かつ目隠し用と思われる黒色のガラスで仕切られている。
蒼が由利亜を連れ込んだ時にリモコンでそれを操作したのだ。
初めから由利亜と基の関係を聞くつもりでの彼なりの配慮なのかもしれないが、そんなことは由利亜に関係ない。
しばらくの沈黙を経て、蒼はため息混じりに口を開いた。
「もう一度だけ聞く。樹月基と恋人同士なのか?」
「だから……そんなこと、あなたに答える必要がどこにあるんです? だいたい、蒼さんがさっきしたことに対して、わたしは理由を話していただきたいくらいです」
由利亜は負けじとピシャリと言い放った。
その時だった。
「じゃあ……教えてやるよ」
そんな言葉が聞こえたかと重うと、バサァッという音共に蒼が今まで手にしていた書類が飛び散る。
そして、由利亜は蒼にその腕を強く引かれた。
「……え?」
一瞬の出来事に由利亜は何が起こっているのか理解できなかった。
気が付けば、今まで視界に入っていた窓から見える風景は消え去り、代わりにあり得ないほどアップになった蒼の顔が見え、更にその先には車の天井が見える。
そして、由利亜の体に重なる人の体温と唇に感じる柔らかく温かい……
(――――!!)
「……んっ……」
ようやく状況を把握した由利亜は、すぐさま抵抗しようとその身を捩った。
しかし、大人の男の手で押さえられた体はびくともしない。両手首は蒼の手により車のシートに縫いつけられたかのようだった。おまけに唇に重ねられた蒼の唇は、由利亜が顔を背けることさえ許さない。
「ふ……やぁ……」
それでも抵抗しようとすると、その弾みで開いた由利亜の口内に蒼の舌が侵入してきた。
由利亜の体を乱暴に抑えつける手とは裏腹に、それは優しく愛おしむように由利亜の口内を犯す。焦らすように歯列をなぞり、ぴくりとも動かさない彼女の舌を絡め取って淫らにエスコートした。
次第に、その甘美な誘惑は由利亜の思考回路をも浸食し始める。
「……ン……ふぅ……」
いつの間にか抗議の代わりに漏れ出た由利亜の吐息と、互いの舌が絡み合う淫靡な音だけが辺りを支配していた。
やがて、由利亜の思考は最低限のレベルでさえ危うくなる。
(どうやって息するんだっけ……?)
それさえも忘れてしまいそうな程に。
しかし、由利亜はほんのわずかに残っていた理性を総動員させて、両の掌をきつく握りしめる。
それはまるで、駄目だ、と自分で自分に言い聞かせるように。
そして、
ガリ……と、音がするほどに由利亜は自身の唇を噛んだ。
突然感じた鉄の味に蒼はその唇を由利亜から離す。一方で由利亜は、唇を噛んだ痛みに顔を歪めながら蒼の顔を見る。
一瞬、得も言われぬ様な悲壮な表情の蒼を由利亜は見た気がした。
(……なんで蒼さんが、泣きそうな顔するのよ……)
由利亜はすぐにでもそう問いたかったが、蒼が離れたことで一気に入ってきた酸素をできるだけ多く回収することに一生懸命だった。
蒼はそんな由利亜をじっと見つめている。
彼女の唇はどちらのものとも分からない唾液と滲む血液で淫らな艶を纏い、細い肩は息苦しさからか上下して目も潤んでいる。
本人に全くその気はないが、それは艶めかしく男を誘っているようにも見えた。
「そんな顔して……基さんより良かったか?」
いつの間にか不敵な笑みを浮かべていた蒼を由利亜は睨み付けた。
と言っても、本人がそうしたと思っているだけで、実際はうつろな視線で蒼を見つめているだけだ。
「何、して……くれた、んですか。……最、低…………」
由利亜は意識が朦朧とする中、独り言のようにポツリと呟いた。同時に、ゆっくりとその意識を飛ばし始める。
「ちょ……オイ……由利亜!」
何だか異常に焦る蒼を見ながら、
「……ファーストキス……だったのに…………」
恨み言のようなそれを、言葉にしたのか、それとも思っただけなのか、由利亜は記憶に留められずに意識を手放した。
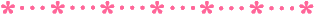
目が覚めると、見慣れはしないが見知った天井が由利亜の視界に飛び込む。
(あれ? わたし……)
身を起こすと、由利亜は華宮家で与えられた自室のベッドの上にいた。
「……痛っ」
ズキッと痛んだ唇に触れると、由利亜の脳裏に先ほどの出来事がフラッシュバックする。
(確か……わたし、蒼さんにキスされて……気絶しちゃったんだ)
由利亜はキスごときで我ながら情けないと思ったが、それでも自分にとって衝撃的だったのは確かだ。
(ファーストキス、だったのにな……)
由利亜は再び痛む唇に触れて、小さく一つため息をついた。
そのまま由利亜はベッドを降りて、ざわつく心を静めようと昨日と同じようにバルコニーに出た。
由利亜は一度大きく息を吸って、何かを決意したように夜空を見上げる。
そこには満点の星空が広がっている。
「綺麗……吸い込まれそう」
今夜の星空は綺麗すぎて怖いくらいである。
由利亜が星空を見上げるのはいったいどれくらいぶりのことだろう。
由利亜の両親は星空を好んでよく見た。もちろん由利亜も二人と一緒に見ていた。しかし、両親が亡くなってから由利亜が星空を見ることはなくなった。
見ることを忘れていたわけではない。由利亜は故意的に見ないようにしていたのだ。見てしまえば嫌でも両親のことを思い出してしまうから……
『死んでから星になれたらいいのにな』
案の定、星空に見入っていた由利亜の脳裏に崇の口癖が過ぎる。
崇は星を見るたびに必ずそう言っていた。彼がその言葉を出すと、有希子は決まってこう言った。
『せっかくお星様になるのなら、隣の星は好きな人がいいわね。ロマンチックじゃない?』
「本当……星になれたらいいのにね。そしたら毎晩会えるもの」
由利亜は一際輝く星と、それに沿うように光っている星に焦点を合わせた。
「ねぇ、お父さんもお母さんも星になったの? ……そこにはお祖父様も一緒にいる?」
由利亜はその星に問いかけるように言う。もちろん、返事がないのは承知の上で。
「わたしだけ仲間はずれにして……みんなで仲良く、して……るの……?」
言葉が終わらないうちに、由利亜の頬を一筋の涙が伝った。
両親のことで由利亜が涙を流すのは二人のお葬式以来。
ざわついた気持ちのまま思い出に浸ったのが悪かったのだろうか、それとも、思い出で気が抜けてしまったのだろうか。
由利亜の瞳から涙がポロポロとこぼれ落ちた。
(泣いたらダメ…………)
由利亜は自分に言い聞かせながら涙を拭った。しかし、涙は流れてくる。由利亜は奥歯をきつく噛みしめて涙がこぼれないようにしたが、喉が焼け付くように痛んだ。
(わたしは強いんだから、こんな事で泣いたらダメ)
由利亜は再び自分に言い聞かせようとしたが、逆に涙がどっと溢れてきた。
(……わたしは……わたしは強くなんてない……よぉ……)
涙に比例するように胸の内で本音がこぼれ出た。
由利亜は両手を口に当て、声を押し殺して泣き始めた。もう、そうせずにはいられなくて……
