コンコン……
「蒼、いるの? いるなら返事して」
深知留は部屋のドアをノックすると返事も待たずにドアを開け、そのまま通った声で室内に呼びかけた。
「おかしいわね、いないのかな? ……ちょっと待っててね」
随分と慣れている様子の深知留は、由利亜を残して部屋の中へと消えてしまう。
由利亜はそんな彼女を待っている間に物珍しそうに廊下の掲示物や辺りを見回していた。高校とは違う造りに違う雰囲気……それが由利亜にとっては新鮮である。
しばらくすると、深知留のはしゃぐ声と蒼の聞き慣れた声が近づいてきた。
由利亜がそれに気づいて部屋の中を覗くと、そこには仲良さそうに並んでお互いに笑いながら喋る二人の姿があった。
(……すごく、仲良いんだ。蒼さんて……あんな風に笑うんだ……)
思って、由利亜の心はなぜだかざわついた。
「あ、由利亜ちゃん。蒼、奥の部屋にいたんだって」
深知留がドアの隙間から覗く由利亜の元へ小走りに近寄ってきた。
後を追うように、蒼もやってくる。
「由利亜、それ……書類、持ってきてくれたのか?」
気づけば、そう言った蒼の顔からは、先ほど由利亜が見たような笑顔は消えていた。
(あ、蒼さんまた機嫌悪いかも……)
由利亜は思う。そして、由利亜自身の表情もそれによって曇ってしまう。
すると、
「ちょっと蒼、何よその顔と態度は。せっかく届けに来てくれたのに由利亜ちゃんに失礼でしょう? 笑ってありがとうくらい言ったらどうなのよ?」
深知留は不服そうに蒼の体を肘でつつく。
「深知留うるさい。お前、今実験追い込みなんだろう? 用が済んだらさっさと研究室に戻れよ」
「あら、邪魔者扱いする気? いいじゃない、せっかく噂の由利亜ちゃんに会えたんだから少しくらい仲良くしたって。ねぇ、由利亜ちゃん」
「え……あ、その……」
突然話を振られた由利亜はしどろもどろになる。
「ほら、深知留。由利亜が困ってるから。連れてきてくれたのは感謝する。でも、もう帰っていい」
「あーはいはい。分かりましたよ。オバサンは退散します。後は若い二人で仲良くやってください。まぁ、わたしがオバサンなら蒼はオジサンだけど。……じゃあ由利亜ちゃん、またね」
深知留がそう言って部屋を出て行こうとした時だった。
由利亜は思わず深知留の着ていた白衣の裾をクッと引く。
「あの、わたし……これだけ渡せばすぐに帰るので。じゃあ、失礼します」
由利亜は言い切るか言い切らないかのうちに、蒼に書類の入った茶封筒を押しつけるように渡した。そして、そのまま蒼の顔も深知留の顔も見ないよう俯いてその場を走り去る。
「ちょ、ちょっと由利亜ちゃん!?」
背中で深知留の驚く声が聞こえた気がしたが、由利亜は足を止めずに走った。
そして、その時、なぜか今まで感じたこともないような胸の苦しみが由利亜を支配していた。
そんな由利亜の脳裏には、『蒼』『深知留』という慣れ親しんだ様子で呼ぶお互いの声が、壊れたテープレコーダーのように何度もリフレインしていた。
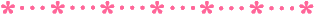
「一体どうしたのよ?」
「別に、どうもしない」
「どうもしないってことはないでしょ。日曜に人のこと呼び出して、おまけにそんなクマだらけの顔して」
「これは……夕べちょっと寝られなかっただけ」
「でしょうね。だから、わたしは何で寝られなかったのか、って聞いてるの。あんたもそれを話したくてわたしを呼び出したんでしょ?」
「…………」
喫茶店で由利亜は京から顔を隠すように机の上に突っ伏した。
由利亜は夕べ、結局一睡もできなかった。
楽しそうに会話をする深知留と蒼の姿が頭の中に焼き付き、お互いの呼称が延々に終わらないBGMのように延々と流れ続けていたから。
由利亜はそれがどうしてそんなにも気になるのか、自分でも分からなかった。ただ、モヤモヤとした嫌な気持ちがいつまでも心の中に存在している。
それが嫌で、何とか振り払いたくて日曜の午前中からこうして京を呼び出したわけなのだが……
「ねぇ、由利亜。話したいことがあるなら話して。流石のわたしも、あんたの表情とオーラから事の次第を察するのには無理があるわ」
京はしばらく前に運ばれてきたアイスティーに浮かぶ氷をストローで突く。その刺激で、氷がカラリンと涼しげな音を立てる。
由利亜は少し頭をもたげてその氷を見つめていた。
「話す気になった?」
由利亜はその視線をゆっくりと京の目線にまで持ち上げると、「あのね……」とゆっくりと言葉を紡ぎ始める。
そして、昨日までの出来事を順序立てて京に話した。
数日前、基との仲を蒼に疑われたことから昨日深知留に出会ったこと、そして蒼と深知留が仲睦まじい様子だったことまで……
「で、その女の人……深知留さんだっけ? その人って蒼さんの彼女なわけ?」
「幼なじみって言ってた」
「幼なじみ? 本当にソレだけ?」
京は少し不満そうな顔をする。
「わたしは幼なじみとしか聞いてないもん」
「じゃあ、もしかしたらその深知留さんが、蒼さんの恋人ってオチがあるかもしれないって事よね?」
今度の由利亜の答えに、京は少し嬉しそうな顔を見せる。
「ねぇ京……深知留さんが蒼さんの彼女の方が、良いの?」
由利亜はふと疑問に思ったことを率直に尋ねる。
なぜ京がそんなにも嬉しそうな顔をするのか、由利亜には分からなかったのだ。
「そりゃあもちろん、良いに決まってるじゃない」
京の答えは至って簡単だった。
「だってねぇ、考えてもみなさいよ。蒼さんに相手がいるなら、それを巧く使えば由利亜は望まない結婚なんてしなくて良いのよ? そんなラッキーなことないじゃない。もしかしてこれは千載一遇のチャンスかもしれない」
「チャンス……?」
人ごとなのに俄然やる気を見せる京に対し、由利亜はまるで人ごとのように呟く。
「ちょっと由利亜、本人がその調子でどうするの! そりゃ基お兄ちゃんとの仲を誤解されて文句言われたのにも関わらず、蒼さんには彼女がいて……って状況にあんたは頭にきてるかもしれないわよ? それも分からなくはないわ。だけど、蒼さんに彼女がいるならそれを利用しない手は無いんだから。ね?」
力説する京に由利亜はすぐには答えず、しばらくアイスティーを飲みながら彼女の言葉をよく考えていた。
そして、
「そっかぁ……そうだよねぇ……。わたし、頭に来ただけなんだぁ……」
言われて始めて気づいた様に呟いた。
京はそんな由利亜の顔を少し不安そうに覗き込む。
「……違うの? 頭に来たからそれ愚痴るためにわたしを呼び出したんでしょう? ……そうじゃなかったの?」
「…………」
「ねぇ、由利亜……?」
「そう……そうよ。頭に……来たの。わたし頭に来たのよね。京に愚痴りたかったの」
(ねぇ、わたし……本当に頭に来ただけ?)
(基さんとのことを咎めたのに、蒼さんには深知留さんっていう存在がいることに……本当に頭に来ただけ?)
京に答えながら、由利亜は心の隅で自問自答を繰り返していた。
