メイド達の見事な仕事により仕立て上げられた由利亜は、待ち合わせの噴水の前で携帯電話を開いた。
時間は五時五十分。少し早く着いたが、そろそろ蒼が来てもいい頃だ。
手持ち無沙汰な由利亜は藤乃が選んだ淡桜色のワンピースの裾を軽く摘み、居心地が悪そうに膝を摺り合わせる。
制服でスカートは穿き慣れているが、こんなモノのいいワンピースを着せられては緊張して仕方がなかった。
よく考えれば、こんなに着飾っておしゃれをして出かけた経験など最近の由利亜にはない。
(蒼さん……早く来ないかなぁ)
由利亜がそう思った時だった。
「由利亜。ごめん、待たせた」
仕事先から来たのか、スーツ姿の蒼が由利亜の元へ駆け寄ってきた。
駆け寄ると、蒼はしばし黙って由利亜の支度を上から下まで丁寧に見る。
今日の由利亜はいつもと様子が違った。
いつもは垂らしている髪も、今日は綺麗に結い上げてうなじを見せている。元々色素が薄い濃茶色の由利亜の髪は綺麗に巻かれ、そのカールが彼女のかわいらしさを引き立てていた。
また、着ている淡桜色のワンピースは抜けるように白い由利亜の肌色に良く合っている。おしゃれをしたのが照れくさいのか、時折膝を摺り合わせている仕草は微笑ましい可愛らしさだ。
そして、今日はいつもと違って少し化粧も施しているようだ。
――綺麗だ
そんな風に蒼は素直に思った。
「あの……蒼さん?」
いつの間にか蒼に見られていることに気づいた由利亜は体裁が悪そうに呼びかけた。
「あぁ……ごめん。なんでもない」
――綺麗だよ
本当はそんな台詞の一つも言ってやる場面なのだが、残念ながら蒼はそれほど器用な男ではない。
「由利亜、突然……どうしたんだ? 何かあったか?」
我に返った蒼は由利亜に尋ねた。
「え……?」
由利亜は蒼の問いを理解することができなかった。
「俺に話があるんだろう?」
「何の話……ですか?」
再び尋ねられた由利亜は思わず問い返してしまう。
そんな由利亜に蒼は何を思ったのか、少しの間考える仕草を見せた。
「お前……今日、誰に何て言われてここに来た?」
「藤乃さんが……蒼さんと食事してきなさいって。蒼さんがホテルのレストランを予約してくれたからって」
由利亜は藤乃に言われたままを話した。
そんな由利亜の言葉を聞いて、蒼はすぐに、なるほどね、とため息混じりに言った。
「何か……違うんですか?」
「だいぶ違うな。少なくとも俺は、由利亜が俺に大事な話があるってここに呼び出されたんだよ。……藤乃に上手いこと計られたな」
言われて、由利亜は藤乃の顔を思い出した。
よくよく考えれば、藤乃の嬉しそうな顔は何かの企みを仄めかしていたような気もする。
「……まあいい。由利亜、このまま食事をして帰ろう? せっかくおしゃれもしてるしな」
蒼は由利亜の手を取ってホテルへと歩き始めた。
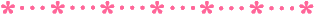
その日、ホテルのレストランは由利亜と蒼の貸し切りだった。ホテルの最上階にあるここをそんな風に貸し切ってしまうのは、流石華宮の力としか言いようがない。
由利亜と蒼は広いフロアの中央に座り、運ばれてくる料理に舌鼓を打った。
食事をしながら二人は他愛もない会話を交わした。
由利亜は少しだけ、無言のまま黙々と食事だったらどうしようかと心配していたが、そんなものは不必要であるくらいに会話は続いた。
蒼が大学で何を勉強しているのか、とか、由利亜の学校生活はどうか、など……些細な話題ではあったが、互いに会話を楽しんだ。それまで二人が気まずい雰囲気だったことも忘れてしまうほどに。
よくよく考えれば、こんな風にゆっくりと落ち着いて二人で話すのは初めてだった。
だから、ある意味この時間はとても有意義だったのだ。
(もっと早く……こうやって話せば良かった)
少なくとも、由利亜がそう思うくらいには。
そんな楽しい時間はすぐに終わるのが世の常で、前菜から始まった料理もあっという間にメインディッシュまで進んでいき、残すところデザートが来るのみだった。
デザートを待っていると、フロア内に由利亜の聞き覚えがある曲が流れ始めた。
(あれ……コレ、何だっけ?)
(どこかで聞いたことがあるような……)
由利亜は目を閉じて、流れてくる旋律に集中する。
少し前、どこかで聞いたことのあるこの曲調……
「コレ、星空のセレナーデ……ですよね?」
目を開けて蒼に尋ねると、彼も目を閉じて由利亜と同じように旋律に耳を傾けていた。
「よく分かったな」
蒼はゆっくりと目を開け、意外、という顔をする。
「この前、蒼さんの部屋で聞きましたから。確か同じ旋律だな、と思って」
蒼は再び目を閉じて、旋律に浸るように耳を傾け始めた。
由利亜もそれを真似るよう、再び目を閉じる。
お互い旋律に身を委ね、穏やかな沈黙が辺りを包んだ。
「蒼さん、セレナーデが好きなんですか?」
由利亜がそう尋ねたのはしばらくしてからだった。
「昔から、好きなんだ」
「やっぱり。お部屋にもたくさんCDが置いてありましたものね」
由利亜は蒼の部屋で見たいくつものCDを思い出した。ジャケットにはどれも『セレナーデ』かもしくは『小夜曲』の文字が入っていた。
「由利亜、セレナーデの意味、知ってる?」
「意味……ですか?」
「そう、意味」
「……うーん……分かりません」
少し考えて答えた由利亜に蒼は柔らかく笑う。
そして、
「愛する女性を思って、彼女のために奏でる曲……それがセレナーデだよ。まぁ諸説はあるけどな」
言い終えて蒼はその視線を徐に空中へと遊ばせた。それはまるで、流れる旋律を見るかのように。
その時の蒼の表情は、今までに由利亜が見たことがないくらい穏やかで、柔らかく、そして優しい微笑みを浮かべていた。
それはあたかも、すぐ目の前に愛する女性がいて、蒼本人が今にもセレナーデを奏で始めるのではないかと思うほど……――
由利亜はいつの間にか、そんな蒼に見とれていた。瞬きをするのも忘れて、蒼に見入ってしまっていたのだ。
「……何だ?」
「へ?」
突然の蒼の声に由利亜は急に我に返る。
「俺の顔に何か付いてるか?」
「いえ……別に。ただ……蒼さんてそんな顔もするんだな、と思って」
「悪いか?」
蒼は少し照れたような、拗ねたような顔をする。
それがなんだかおかしくて由利亜はクスッと笑ってしまった。
「全然。そんな蒼さんも良いですよ。わたしといる時は仏頂面が多いから、蒼さん、わたしには笑ってくれないのかと思ってました」
由利亜は言い終えると、今度は満面の笑みを蒼に見せた。
蒼が笑ってくれたことが由利亜は素直に嬉しかったのだ。そして、蒼の意外な一面を垣間見たことで、由利亜は今までよりも蒼に親近感を持ち始めていた。
「……由利亜はそうやってずっと笑ってる方が良いな。俺こそ、由利亜がもうそんな風に笑ってはくれないかと思ったから」
蒼は由利亜の笑顔を見ながら呟くように言った。
由利亜は蒼の言っている事が分からず、わずかに首を傾げる。
「この前……基さんのことで酷いことを言っただろう? 昨日、大学に来た時もすぐに帰ったから、由利亜が怒っているものだと……」
「あれは……」
――蒼さんが深知留さんと楽しそうにしてたから
言いかけて、由利亜はやめた。
もうそんなこと、今の由利亜にはどうでもよかったから。
その時なぜか、由利亜の心はとても温かかった。いつの間にか、一晩中抱えていたはずのモヤモヤした気分もスッキリとどこかに消えて無くなっていたのだ。
「あの時は、少し……苛々してて……。その……今更だけど……悪かった。……ごめん」
由利亜がまだ怒っているのだと思った蒼は、体裁が悪そうにそう口にした。
そんな蒼を由利亜は微笑ましく見つめていた。
(氷室さんが言った通り……本当に感情表現が苦手なのね)
「もう、怒ってませんよ。大丈夫です。わたしこそ、行動が軽率でしたから」
由利亜が再び満面の笑みを見せれば、それにつられるように蒼もその表情を綻ばせた。
その晩、帰宅した二人を迎えた藤乃は、小さくガッツポーズをし、一緒に出迎えた氷室に目配せをした。
それに対し、氷室はやれやれといった仕草を見せた。もちろん、由利亜と蒼には気づかれぬようこっそりと。
