蒼と由利亜が二人で食事に出かけたあの日――それから何かが変わり始めた。
それはまるで、どこかの歯車がカチャリとはまったかの様に、全ては動き出したのだ。
蒼は日中に全ての仕事を片づけ、夜はできるだけ早く帰宅して由利亜と過ごすようになった。
二人は一緒に食事をしながら他愛もない会話を交わし、食後は二人一緒にテレビを見たり、DVDを見たり、セレナーデを聴いたり、と穏やかで充実した時を過ごす。
蒼の帰りが遅い時でも、由利亜は蒼を待ち、食事だけは共に摂る。
やがて、いつの間にか、華宮の屋敷ではいつでも笑い声が聞こえるようになった。
由利亜の楽しそうな笑い声、それにつられるように起こる蒼の笑い声、そしてそんな二人を微笑ましく見守る使用人達の笑い声。
氷室と藤乃はその様子を優しく見守りながら、まるで崇と有希子が屋敷にいた時のようだと心のどこかで感じていた。
「蒼さん、今日はお仕事忙しいんですか?」
朝の登校前、由利亜は玄関で靴を履きながら同じように出社の支度をする蒼に尋ねた。
最近、華宮家でよく見かけられるようになった朝の一コマである。
当人たちはもちろん分かってないが、使用人たちは密やかにこれを『新婚夫婦の朝の一風景』と呼んでいる。
「ん? 午前中に会議が一本、午後は竜臣に聞かないとちょっと……ただ、夕方は少し大学に寄ろうと思ってる。でも、七時の待ち合わせには問題ないよ」
待ち合わせ――今日は平日には珍しく、二人でデートの日である。お互い仕事に学校が終わったら、待ち合わせをして映画を見に行こうという計画だ。
「相変わらず……朝から晩まで忙しいんですね。映画、やっぱり止めておきます? どうしても見なきゃいけないってものでもないし……」
由利亜は心配そうな表情を見せた。
それも無理はない。蒼はここ数日毎日帰りが深夜近くである。
しかも、返ってきても部屋の明りは遅くまで消えず、いつ寝ているのか不安になるくらいだ。
心配になった由利亜がそれとなく竜臣に尋ねると、今は大きなプロジェクトが大詰めで忙しいのだと言っていた。
「大丈夫だよ。由利亜、あの映画見たかったんだろう? 俺の仕事が調整付かなくて今日まで延ばしてしまったんだし……それに、確か今日が最終日だったろう?」
「でも、わたしは別にDVDになるまで待っても……」
「良いんだよ」
気遣う由利亜の言葉を蒼は優しく遮った。
「俺が映画館で一緒に見たいんだ。だから絶対に行こう、由利亜」
そう言った蒼は何だか少し照れていた。
由利亜はそれにクスリと笑みを零す。
最近の蒼は、自分のしたいこと、嫌なこと、は由利亜にこうしてきちんと伝えるようになっていた。
それは氷室的に言うと『眼鏡もずり落ちる劇的変化』らしく、由利亜にすればその変化は嬉しいような恥ずかしいような、何だか不思議な気持ちだった。
でも、悪くはない気持ちだ。
「ほら由利亜、学校遅れるぞ。七時にはあの噴水の前で待ってるから。お前こそ、遅れるなよ」
蒼は由利亜の頭をポンポンと叩いて玄関を先に出て行った。
「遅れませんよ。……ありがと、蒼さん。楽しみにしてますね」
由利亜は蒼の触れた場所を手で触りながら、その背中を見送った。
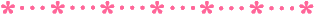
「それで、昨日はわたしがじゃんけんに勝ってラブロマンス物のDVDを見てたんだけどね、それがもうすっごい感動ものだったのよ!! 当たり、って感じでね。初めはぶつぶつ言ってた蒼さんも、気づけば真剣で最後の方なんてわたしが少しでも物音立てると怒っちゃって」
昼休み、由利亜は少し興奮気味に昨日の出来事を楽しそうに話していた。
そんな由利亜の前には京がいる。
「その後で、蒼さんが新しく買ってきたCDを聴いてたんだけど……」
京は頬杖を付きながら、嬉しそうに喋り続ける由利亜を見ていた。
(ホント、一体全体……何がどうなってるんだか)
京がそう思うのも無理はなかった。
少なくともここ一週間以上、由利亜は毎日この調子だ。
彼女が何かを話せば『蒼さん』が出てくる。それも楽しそうな笑顔付きで。
その頻度ときたら素晴らしいほどのもので、統計なんて取る必要も無いくらいに極頻出だ。
そんな由利亜の異変、を京が感じ始めたのは喫茶店に呼び出されたあの日の翌日からだ。
そもそも、あの日曜日、あれだけ落ちていたのにもかかわらず、翌日には驚くほどスッキリとした顔をしていた由利亜。その時点でもう何かがおかしかった。
ゆっくりたっぷり寝ただけではあれほどいい顔はできない。
何かあったのかと思って京が尋ねれば、由利亜は、ただ蒼と仲直りしただけだ、と言った。
その頃から由利亜は、京が放課後誘いを掛けてもあまり乗らなくなった。
今までは京が誘えば由利亜は大概は応じてくれたし、彼女から誘ってくれることも往々にしてあったのに、ここのところ京は連戦連敗である。
それも用事があるのかと問えば、「蒼さんが帰ってくるから、早く帰らなきゃ」と言うだけだった。
初めは京も由利亜が蒼に脅されて早く帰宅しているのかとも思った。しかし、毎日の彼女の表情からすぐにそうではないことがうかがい知れた。
今日のように本当に楽しそうに『蒼さん、蒼さん』と毎日連呼されれば、脅しではなく由利亜が本当に自ら望んで『蒼さん』のために帰っていることが京には簡単に分かった。
初めはそれこそ、由利亜のあまりに急激な変化に、蒼に変な薬でも飲まされたのではないかと疑ったりもした。
それでも、
――由利亜と蒼の間で何かしら関係性に変化が生じた
勘の良い京はすぐにそれを察した。
細かい状況や心理説明を受けていなくても、由利亜の纏う雰囲気でそれは感じ取れた。
と言っても、今回は由利亜が以前のように京に対して隠し事をしているわけではない。
どちらかと言えば、今日のように、由利亜はあった出来事は必要以上に詳しく京に話している。
ただ、由利亜が、当の本人にであるにもかかわらず、自分と蒼との関係の変化に気づいていないのだ。
それは京的に言えば『だって由利亜は鈍ちんだから』である。
(気づいてないのに、話せってのは無理よね〜)
京は由利亜の顔を見ながら思った。
「ねぇ、京聞いてるの?」
「え? あ……聞いてるわよ」
物思いに耽っていた京は慌てて返事をした。
「それで、由利亜は楽しかったの?」
京は少し含みのある言い方で由利亜に尋ねた。
そんな京に由利亜はニコリと笑って答えた。
「うん。ハッピーエンドだったし、すごく楽しかったよ。でもラスト数分は泣けるかも。京も今度是非見て!」
「……そっか。じゃあ、今度の週末にでもね」
(DVDじゃなくて、蒼さんといて楽しいか、ってことなんだけどね……鈍い由利亜にはやっぱり無理か)
京は言えない言葉を噛みしめながら、やれやれといった風に笑った。
二人の関係性の変化に気づいたところで、今の京はとやかく口を出す気は無かった。むしろ、少し見守ることにしたのだ。
だって、あくまでも由利亜は楽しそうであったから。
(そのうち気づくかな……? )
それまで見守るのも悪くはないと京は思っていた。
「ところで、由利亜、今日の放課後少し時間はある?」
京は話を切り替えた。
「放課後? ……夜、蒼さんと映画に行く約束してるけど、待ち合わせは七時だし……それまでだったら良いわよ? それじゃ時間足りない?」
「ううん。十分、ちょっと付き合って欲しいところあるんだ」
「それなら、大丈夫。付き合うよ」
由利亜が答えるのと同時に、始業のチャイムが教室内に鳴り響いた。
