その日、由利亜が華宮の屋敷に戻ったのは夜九時近かった。
気づけば外は雨が降っていて、その雨脚はだいぶ強くなっている。そんな音にも気が付かないほど、由利亜はずっと京のところで泣いていたのだ。
京はそのまま泊まっていってもいいと言ったが、由利亜は華宮の家に帰ることを選んだ。
蒼との約束もすっぽかし、また怒られるかな、と思ったが今はそんなことどうでも良かった。
それ以前に、今の由利亜は蒼と顔を合わせる気になど到底なれなかったが、それでも、藤乃や氷室に心配を掛けたくはなかったのだ。
彼らはきっと、心配して由利亜を待ってくれているはずだから。
京に車で送り届けてもらい、屋敷の門をくぐって由利亜は小さく一つため息を吐いた。
傘にバタバタと振り落ちる雨音だけが聞こえる中、京が帰りの車の中で言った言葉が不意に思い出される。
『今の由利亜には酷だけど……』
京は神妙な面持ちで話した。
それは由利亜の今後の身の振り方について。
蒼に恋人がいると知った今、由利亜は嫌でも身の振り方を考えなければならなかった。と言うのも、気づけばもう婚姻を成立させるまでの約束の期間は一週間を残すだけとなっていて、残された時間があまり無かったから。
『華宮の家を出たら?』
京が言わんとしていることは由利亜にもよく分かった。
もう、蒼のそばにはいない方がいい――そういうことだ。
こんな状態で万が一にも遺言のまま結婚してしまったら、辛いことしか待っていない。
蒼には深知留という愛する女性がいてその傍らでの結婚生活……誰も幸せなはずがないのだ。
強いて言うならば、結婚をすれば由利亜は好きな蒼のそばにはいられる。例え蒼の心が由利亜になくとも一緒にいることだけはできる。法律上の夫婦でもいられる。
でも、そんなこと……そんなエゴむき出しのような馬鹿げたことなど、してはいけないことくらい由利亜だって分かっていた。
もし、そんなことをすれば由利亜も蒼も深知留も全員傷つく。皆が皆、不幸せになるだけ。
だから由利亜はもう、蒼のそばにいられない、のではなく、いてはいけない、のだった。
京は真剣な表情で言った。
『由利亜、遺産相続に対して、相続放棄って言葉知ってる?』
相続放棄――由利亜はその詳しい内容までは知らなかったが、社会か何かの教科書で、そんな言葉を目にしたことはあった。
『由利亜が初めて事情を話してくれた日、わたしちょっとだけ調べたの。何とか由利亜を救い出す方法はないかって。その時に、見つけたのよ。相続放棄って手段があることを』
今、その相続放棄という言葉が由利亜に重くのしかかる。
こうなってしまえば、由利亜はもうこれ以上蒼にすがるつもりはなかった。気づいてしまった自分の気持ちをすぐに割り切れる自信は無かったが、それでも深知留という存在がいる以上、蒼のことは諦めなくてはならない。
短時間ながら、精一杯冷静になって由利亜はなんとかそう納得した。
(今ならまだ……引き返せる。まだ諦められる……)
そう納得した。
したはずだったのに……実際そんな風に相続放棄などと具体的な法を指し示されると、由利亜はもう本当に蒼との関係を絶たなければならないのだと宣告されている気分だった。たったの一パーセントも、見込みはないのだと。
京は最後にこう付け足した。
『今すぐ返事をしろとは言わないわ。それでも早いに越したことはないと思うの。由利亜の気持ちが決まったら、すぐにでもうちの専属弁護士に相談してみるから。わたしは、いつでも由利亜の味方だからね』
早いに越したことはない――京の言っていることは正しいと由利亜は思う。
相続放棄という手段を取るのが早ければ早いほど、立つ波風は最小限で済む。それが誰も傷つかない最善策なのだということも由利亜は十分に理解できる。
そして、そこまで自分を考えて、的確に指示をしてくれる京の存在を由利亜は心底ありがたいとも思っていた。もし、彼女がいなければ、こんな状況に陥ってもしばらく泣き暮らして、何も出来ないまま流れに呑まれるより仕方がなかったはずだから。
しかしそれでも、由利亜は今すぐ「相続放棄をします」「華宮家からは出て行きます」と即決できるほどに、心の整理ができていなかったのだ。
それも無理はない……――
「好きって気づいたとたんに失恋しちゃったね……わたし、馬鹿みたい…………」
由利亜は呟いて、雨の降り落ちる空を見上げる。
その状況で、数時間のうちに全ての身の振り方を決めるなど、まだ十七歳の由利亜には酷なことだった。
だって彼女は……誰かを本気で好きになるという感情さえ、知ったばかりなのだから。
「ねぇ……どうしたらいいんだろう? もう……どうにもならないんだよね? お母さん……」
どんなに空を見上げても、今夜は星が見えない。降り落ちるのは冷たい雨粒ばかり。
それでも由利亜は、見上げずには居られなかった。
傘の中、吹き込む雨が由利亜の頬を、体を、濡らしていく。
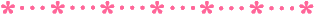
京が由利亜を送り届けて自宅に戻ると、メイドの一人がすぐに部屋へと訪ねてきた。
「それで、電話は来たの?」
京は彼女を部屋へ迎え入れるなり言った。
「はい……。由利亜様がまだいらっしゃるうちに二度。それからつい先ほど一度」
メイドの答えに京は、やっぱりね、と小さくため息を吐く。
京は事前にある予測を立て、メイドに言伝をしていた。
蒼から由利亜の居場所を問い合わせる電話があっても決して取り次がないように、と。
由利亜と蒼の間に何かがあった、と感づいた段階で京は先手を打っておいたのだ。
「彼には何て言ったの?」
「はい、お嬢様が仰ったようにお伝えさせていただきました。『お嬢様はただいま外出中です。由利亜様もこちらにはいらしておりません』と」
「戻ったら折り返し電話しろって?」
「いえ、そのようなことは承っておりません。しかしお嬢様……華宮様は随分と必死なご様子でしたが、これでよろしかったのでしょうか?」
メイドはいくらか不安そうな表情を見せた。いくら主の指示に従ったとはいえ、彼女はどこか罪悪感を覚えているのだろう。
「いいのよ。……あなたは何も気にしなくて良いわ。変なこと頼んでごめんなさいね。ありがとう」
メイドはそれ以上は何も聞かず、京に一礼して部屋から下がっていった。
京はソファに腰掛け、ふぅっと大きく一つため息を吐く。
(悪いわね、蒼さん。……でも、由利亜を傷つけたんだから、わたしなりにあの子を守らせてもらう。わたしの大切な友達だもの……)
