「由利亜、お前……何を馬鹿なこと……」
一瞬、耳を疑った蒼はすぐさま否定の言葉を述べようとした。
が、
「馬鹿なことじゃありません。だって……だって蒼さんには深知留さんがいるじゃないですか。それなのにわたしに優しくするのは、わたしが遺産相続人だからでしょう? ……そうなんでしょう!?」
由利亜が再び声を荒げてそれを止めた。
(こんなこと……言っちゃいけない)
そう思うのに止められなかった。
ただこの時、堪えきれなくなったやるせなさを由利亜は放出させずにはいられなかったのだ。
ここに来るまでの間、由利亜には一つだけ考えたことがある。
それは、蒼には深知留という大切な存在がいるのに、なぜ由利亜との結婚に異論も述べず、そして優しくしてくれたのか、ということ。
そんなこと、大して考えなくても案外あっさり分かった。
答えは簡単、それは由利亜が華宮の全てを相続できる人物だから。
蒼にとっては大切にしておいて、優しくしておいて損はないのだ。
しばらく前に、京が言った事があった。
あれは、そう……泣きわめいた由利亜を蒼が優しく慰めてくれた日の翌日。
『計算、ね。冷たくするより、優しくしておく方が後々悪いことは無いからね』
(そういうことだったのか……)
今更になって由利亜は納得した。悲しいことに、それで全ての辻褄は合ってしまったのだ。
蒼が自分に向けてくれた全ての裏にそんな答えがあったのだと思ったら、由利亜は寂しくて仕方がなかった。裏切られたような気分だったのだ。
だから、
(もう……優しくされても信じちゃ駄目だよ……)
由利亜はそう思った。
なのに、今また蒼はこうして雨の中自分のことを待ってくれて、心配してくれて、抱きしめてくれて……
駄目だと思うのに、由利亜の胸を確かな幸福感が掠めていく。
(蒼さんは、わたしが相続人だから優しくするだけ……)
そうやって甘美な夢から自分を覚まそうとするのに、どうしても駄目だった。
これ以上は、自分がどんどん惨めになるだけだというのも分かっているのに、できることなら由利亜は夢から覚めたく無かった。
それが不幸な結果しか生まないと分かっていても。
(でも、本当にもう……駄目なの……)
「もう……いいんです。蒼さん……」
由利亜は意を決してドンッと蒼の体を突き放した。
「もう……優しく……しないでください。心配しなくても……すぐに相続放棄の手続きを……取りますから。深知留さんと……どうかお幸せに…………」
由利亜はいつの間にか込み上げてきたものを堪えながら絞り出すように言った。
「由利亜、落ち着け。とにかく、俺の話を……」
「嫌です! ……聞かない。聞きたくない!! わたし、もう……惨めな思いはたくさんです!」
これ以上は耐えられなかった。
蒼の口から真実を告げられたら、由利亜は正気を保つ自信など無かった。
引き留めようと腕に掛けられた蒼の手を由利亜は振り払って、踵を返す。
そして、それは由利亜が頬を流れてくる涙か雨か分からないものを拭いながら歩き始めた時のこと。
背中でドサリという聞き慣れない鈍い音がした気がした。それは、何かが崩れるような、そんな音。
由利亜はその足を止め、ゆっくりと振り返る。
瞬間、
(――――!!)
由利亜は目に入ったものに息を呑んだ。
そこには、力なく地面に横たわる蒼の姿があった。
「蒼さん!?」
叫ぶのと同時に、由利亜は倒れた蒼に駆け寄っていた。
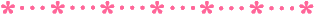
「疲れが溜まっているところに、無理をしたのでしょう。薬を出しておきますので、しばらく安静にしていてください。それから、栄養のある食事も」
「ありがとうございました」
蒼を診察した医師に藤乃が深々と頭を下げる。由利亜もそれに習うように医師にお辞儀をする。
医師とそれを送り出すために部屋を出て行った藤乃を見送って、由利亜は小さく一つため息をついた。
(馬鹿だよ……蒼さんは)
自室のベッドで静かに眠る蒼に語りかけるように由利亜は思った。
熱が高いせいなのか、頬は紅潮し、呼吸は乱れている。
健康な人間が長時間雨に当たっても風邪くらい引くのに、日頃の激務で疲れている蒼が何とも無いはずがなかった。
(わたしなんて……待ったりするからいけないのよ)
あれから由利亜は竜臣を呼びに行き、迅速な彼の判断で、すぐさま蒼を屋敷へと連れ帰った。
由利亜はいつの間にか蒼の額に浮かんできた汗を、タオルでそっと拭ってやる。
「……ん……」
わずかに声を漏らした蒼に、由利亜は起こしてしまったのかとその手をスッと引く。
「……う、ン……」
続けて、呻くような声が蒼の口から漏れ出る。
何か辛く怖い夢でも見ているのか、蒼はその眉間に深く皺を刻んでいた。
「……どこ……だ? ……どこに、いる……?」
「ここに……いますよ」
熱に浮かされる蒼に由利亜はそっと応えてやった。
しかし、蒼には聞こえていない様子だ。
「行くな……。どこにも……行かないで……」
誰かを捜しているのか、蒼はその手を狂おしそうに伸ばす。
「ここに……ここに、いますよ」
由利亜はそれを思わず握ってしまった。
すると、蒼はそれを離すまいとしっかりと握り返す。恐ろしいほど熱い手が、彼の体調の悪さを物語る。
「どこにも……どこにも行くな……」
「大丈夫、ずっと傍にいます……」
由利亜はそう答えながら、
(もしかして、深知留さんを……探しているの?)
そんなことに気づいてしまった。
気づいた瞬間、由利亜の心がツキリと痛む。
(この手を握って良いのは……わたしじゃない。ここにいていいのも……わたしじゃない)
でも、由利亜は蒼の手を離すことが出来なかった。
やがて、蒼は薬が効いてきたのか、その表情を穏やかにして規則的な寝息を立て始める。
由利亜はずっと握っていた蒼の手をそっと離し、それをブランケットの中へと戻してやる。
そのまましばらく、由利亜は蒼の寝顔を見ていた。
何を思うわけでも、何を考えるわけでもなく見ていた。
ただ、見ていたいと思ったから。
◆◆◆
どれくらいそうしていたのだろうか。
コンコン……
部屋のドアが控えめに静かに叩かれた。
「はい」
由利亜がそう答えると、やはり控えめに顔を覗かせたのは藤乃だった。
「由利亜様……あの……」
藤乃はそれ以上言葉を発しなかった。
「どうかしましたか?」
由利亜はドア口まで歩いて行く。そこまで行くと、藤乃の後ろには誰か人影があるのが見えた。
藤乃は先ほどよりも少しだけドアを引くと、ゆっくりとその目線で後ろの人影を由利亜に指し示す。
「深知留様が、お見えでございます」
藤乃の視線の先にいた深知留は、真剣な眼差しで由利亜をじっと見つめていた。
