「起きて……大丈夫なんですか?」
ベッドの上で上体を起こし、ヘッドボードに体を預けるようにした蒼に由利亜は怖ず怖ずと尋ねた。
「薬が効いて一眠りしたから、随分楽だよ」
「そう……ですか。それは良かったです……」
由利亜はそれ以上は言いようが無くて俯いてしまった。
深知留はあれから、
『だいたい泣かせた大元の原因は蒼でしょ!!』
と言って、子供のようにアッカンベーをすると、そのまま引き留める間もなくバイバイと帰ってしまった。
「いつから……起きてたんですか?」
由利亜はふと疑問に思ったことを尋ねた。
「由利亜が深知留に涙声を荒げた時だよ。……あぁ、また泣いてるのかって思って目が覚めた」
蒼は柔らかい笑みを見せて由利亜の頬に手を寄せた。
その手は、まだ熱が残っているせいで温かい。
「由利亜、今度は……きちんと俺の話を聞いてくれるか? 義父さんが残した遺言の話も、深知留の話も、それから、柚木小夜子の話も……少し長くなるけど、大切なことだから」
言って蒼は由利亜が手に持つブルーの封筒に視線を向けた。
由利亜はそんな蒼に了承を伝えるため、ゆっくりと頷く。
「俺が、初めて由利亜を見たのは今から六年前のことだった……」
そうして、蒼は話し始めた。
まだ、蒼が高校生だった頃の昔話を……――
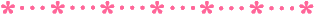
六年前――――
蒼が華宮の家に引き取られて既に十年以上が経過していた。
当時高校三年生だった蒼は、進学先も早々に決まり、最後の高校生活を特に何もすることなく消化していた。
そんなある日、メイド達の話を聞いてしまったのがそもそもの始まりだったのかもしれない。
『崇様って結局今どこで何してるのかしら? 』
『有希子と結婚して幸せに暮らしてるでしょ。どこかでね』
『娘が一人生まれた、ってそんな噂も聞いたわよ?』
『あーあ。崇様も馬鹿よね。有希子のために約束された将来も何もかも、全部捨てちゃったんだから』
記憶に寄れば、そんな会話だった。
有希子、という名は蒼が初めて耳にする名前だった。一方で、崇という名は既に知っていた。
いつだったか、よけいなお節介をする親族がいて、幼い蒼に吹き込んだことがあったのだ。
『お前が貰われてくる前は、崇という一人息子がいたんだよ』
と。
そして、その一人息子が屋敷のメイドと駆け落ちをしたということも、蒼は人の噂で聞いていた。だからすぐに、有希子という女性がそのメイドなのだろうと蒼は想像できた。
今にして思えば、たまたま聞いただけのそんな他愛もない会話なんて聞き流せば良かったのかもしれない。
それでも、その時の蒼はなぜか崇と有希子という人物に興味を持ったのだ。
(会ってみたい……)
気づけばそんなことを思っていた。
理由はもう一つあった。
それは義父、早次郎に関すること。
早次郎は厳格な人柄で、いつでも無表情な人間だった。感情を露わにする所など、義息子の蒼でさえ見たことがないほどに。
そんな早次郎が時折、何とも悲壮な表情を見せることがあった。
そのシチュエーションは必ず決まっていて、夜の静まりかえった自室で古ぼけた一枚の写真を一人で見ながら、だ。
ある晩、偶然その場面を覗き見てしまった蒼は、興味本位で早次郎の留守中に彼の部屋へと忍び込んだ。そして、引き出しを開けると中には写真と指輪がひとつ入っていた。
写真には若い早次郎と好江、学生服を着た一人息子の崇が写っていた。その好江の指には、写真と共に置かれていた指輪がはめられていた。
写真の中の家族は全員嬉しそうに笑っていた。普段は無表情の早次郎も、写真の中でその顔をほころばせていた。
(義父さんは……崇さんを忘れていないんだ)
蒼は思った。
崇に会おうと決めた蒼は、当時早次郎の腹心の部下を務めていた氷室に頼んだ。
しかし、色よい返事はもらえなかった。
それでも食い下がる蒼に、氷室は「遠くから見るだけなら」と渋々了承してくれた。
ある日曜の昼下がり、蒼は車の中から崇達一家を見た。
庭で楽しそうに過ごす一家はまるで絵に描いたようで、崇も有希子も由利亜もみんな楽しそうに笑っていたのを今でもよく覚えている。
特に娘の由利亜の笑顔は輝いていて、幸せそうだな、と蒼は思った。
そして、この子達がこれからも幸せであるようにと一人祈った。
事態が急展開を見せたのはそれから二年が経った時のことだった。
崇と有希子が事故で亡くなったと、早次郎の元に連絡が入ったのだ。
あまりのショックに早次郎は体調を崩して入院。当時、既に副総帥の座にあった蒼は義父が空けた穴を補わねばならなかった。
そんなある日、蒼は娘の由利亜がたった一人残されたことを知らされた。
病床の早次郎に言われて蒼が様子を見に行くと、そこには二年前とはまるで別人の彼女がいた。
瞳から光を失い、すっかり無表情になってしまった由利亜がそこにはいたのだ。
(彼女を助けたい……)
何より先に蒼は思った。
状況を把握した早次郎も、由利亜をすぐさま華宮の家に引き取ろうとした。
しかし、それは叶わなかった。
親族にも、会社関係者にも、異論を述べる者が多すぎたのだ。
既に後継者として蒼という存在がいるのに、直系の孫娘である由利亜を引き取れば将来的に揉めるだけだ、と。
全ては華宮という一大グループを守る上でのこと――仕方がないことだった。
由利亜を引き取るということ、それはもはや早次郎の祖父としての情だけでどうにかなることではなかったのだ。
それでもなんとか由利亜を救おうと、蒼は早次郎に掛け合った。そして相談の末、苦肉の策として、資金援助だけをこっそりと行うことにした。
蒼は“昔、崇に世話になった老婦人、柚木小夜子”という架空の人間を作り上げ、支援をしたいと由利亜に申し出た。
その時に、蒼が手紙の書き手として選んだのが幼なじみで気心の知れた深知留だった。
蒼が文面を考え、深知留が推敲して女性らしさを出し、女性らしい文字で清書する……そんな努力が功を奏したのか、最初は頑なに拒否していた由利亜もやがては心を開き、その支援を受けるようになった。
そこから、二週間に一度の手紙のやりとりが始まった。
すっかり小夜子を信用していた由利亜は、手紙で色々なことを話した。学校のこと友達のこと、時折思い出す両親のこと……
蒼は小夜子になりきって話を聞き、由利亜を励ましたり、慰めたり、アドバイスをしたりした。由利亜の特別な日には深知留に協力して貰い、女の子が好みそうな花やプレゼントを送った。
由利亜はそれらの一つ一つに対して、感謝と喜びの手紙を丁寧に送ってくれた。
いつの間にか、蒼は由利亜からの手紙を楽しみに待っていた。
もちろん、由利亜が向けてくれる全ては小夜子へのものだと理解はしていた。それでも、蒼は嬉しくてたまらなかったのだ。
だから、気づいた時には、蒼はもうどうしようもない程に由利亜が好きだった。
蒼にとって由利亜はかけがえのない存在で、そばに置きたくて、守ってやりたくて堪らなかった。
小夜子ではなく、華宮蒼、という独りの人間として由利亜の近くに行きたいと望んだ。
そして、早次郎の亡くなる半年前、思いを募らせた蒼は彼にはっきりと言った。
『由利亜を好きになりました。“小夜子”の素性を明かして、僕の思いを伝えても良いですか?』
しかし、早次郎は口を噤んだまま何も答えなかった。
それは蒼が何度言っても変わらず。
(あぁ……駄目なのか)
やがて蒼はそう納得するより無かった。
もう何も期待をしてはいけない、と。
(彼女は俺には縁のない子だったんだ……)
そう言って諦めようとした。
結局、早次郎はその件に関して蒼に何の返事もしてくれずに逝ってしまった。
最期の最期も、
『華宮を頼む』
それだけ言って旅立ったのだ。
