蒼が話し終えた後、由利亜は何も言わず、ただ封筒を握りしめて蒼を見ていた。
蒼はそんな由利亜を見ながら、呼吸を整えるように小さく一つ息を吐く。
「でもね、由利亜。義父さんは最後の最後にきちんと答えを遺していってくれた」
「遺言、ですか?」
蒼は由利亜の答えに静かにかぶりを振る。
そして、そのままベッドサイドに置いてある引き出しの中から小さな箱を取り出した。
蒼はそれを開いて由利亜に見せる。
「……これって……」
中から姿を見せたのは一つの指輪だった。
「義母さんの遺品だそうだ。遺言と一緒に、山名さんに預けていたらしい。婚姻の際に由利亜に渡すように、と。この指輪は、華宮の女主人が受け継ぐ物だと氷室が教えてくれた」
蒼が言葉を終えるとしばらくの沈黙が続いた。
どちらも何も言わないまま時は流れていく。
由利亜は蒼の話を聞いて考えたいことが山ほどあった。同様に聞きたいことだってたくさんあった。なのに、その時は考えることも聞くことも何一つできなかった。
「由利亜……」
しばらくして沈黙を破ったのは蒼。
由利亜はそんな蒼に焦点を合わせる。
「俺のやり方は……決して褒められた物じゃないと思う。遺言を理由に強引に由利亜を囲って、逃げられなくして……卑怯だと思われても仕方がない。でも、そうするより他に……俺は由利亜を捕まえる方法が見つけられなかったんだ」
蒼は徐に由利亜の手を握った。
「それでも、手に入れられた瞬間は、嬉しさの方が強かった。後悔なんてするはずがない、と思ってた。なのに、お前の心にはいつでも基さんがいて……結局、後悔したよ。俺が由利亜の幸せを奪ったんじゃないか、ってね」
待ち望んでようやく手に入れた由利亜は、既に別の男を追っていた……蒼にとっては受け入れがたい事実。
仕方ない、そう思おうとしても蒼は割り切れなかった。既にそれほどまでに、蒼の心が由利亜に向いていたから。
彼女の幸せを思うなら手放してやるべきだったのかもしれない。
しかし、蒼にはできなかった。
「だけど、俺はどうしても由利亜をそばに置きたかった。傷つけてしまうかもしれないと思っても、手放してやれなかった。……由利亜、俺はお前のことが好きだ。今までも、そしてこれからも。お前の笑顔を……ずっと傍で見ていきたい」
蒼は由利亜を見つめる。
その目は酷く真剣で、そして切なさをも含んでいた。
由利亜もまた、瞬きもせず蒼を見ていた。
再び、沈黙という名の静けさが辺りを包み込む。
蒼はわずかにその手に力を込める。
「今すぐ……返事が欲しいとは言わない。考えてくれればいい。その結果出た答えなら、俺はどんなものでも受け入れる。ただ、由利亜がもし……俺と深知留のことを誤解して少しでもショックを受けてくれたのなら……俺にはまだチャンスがあると、そう思って良いか?」
尋ねた蒼に由利亜はすぐには答えなかった。
蒼の表情は次第に暗くなっていく。
しばらくして、由利亜はそんな蒼の手をゆっくりと握り返した。
彼女は答えなかったのではない。
(早く答えなきゃ……)
そう思うのに涙に声が詰まって答えられなかったのだ。
感情表現の苦手な蒼がこんなにもストレートに告白をしてくれて、それにどう答えたらいいのか、どうやったら自分の気持ちを一番伝えられるのか……
つい先ほどまで、懸命に諦めようと押さえ込んでいた感情が、この時由利亜の中で次から次へと溢れ出ようとしていた。
「泣くほど……嫌なのか?」
蒼は由利亜の瞳に浮かんだ涙を不安そうな面持ちで見つめている。
由利亜はそうではないと伝えたくて、その顔に一生懸命笑顔を作った。
それでも涙は溢れて、顔は泣き笑いのような変な顔になってしまう。
「蒼さん……チャンスなんて……いりません。わたしはもう……蒼さんが好きなんです。深知留さんに嫉妬するくらい……どうしようもないくらいに、わたしの心には蒼さんしかいないんですよ」
蒼は一瞬、その目を見開いた。
「由利亜、それは……本当か? ……本当、なのか?」
由利亜の言葉が信じられないのか、蒼は途切れ途切れに確認する。
「本当ですよ。わたしは蒼さんのことが好きなんです」
由利亜は涙を拭って、今度こそ蒼に極上の笑みを見せた。
その笑顔は、六年前に蒼が初めて見たものととてもよく似ていて……――
蒼の顔が由利亜の笑顔につられるように綻ぶ。
この時、蒼の仲では長い冬の終わりが来たような、そんな気がした。
ただ由利亜を見守り、幸せを願うことしかできなかった時の自分とはもう違う。これから先はこの手で彼女を幸せにすることができるのだと、その思いを蒼は強く噛みしめていた。
「由利亜……こんな時、俺はどうしたらいいんだろう? 嬉しくて……嬉しくてたまらないこんな時はまずどうしたらいい?」
「しっかり抱きしめてください。蒼さんのその腕の中に、しっかりと」
次の瞬間、蒼は感情を抑えきれない様子で由利亜の体を苦しいほどに抱き寄せた。
そんな不器用な蒼が大好きで愛おしくて、由利亜は応えるように蒼を抱きしめ返す。
(あなたが、好きです……)
そう伝えるように。
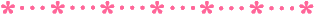
数日後――――
「由利亜、ここにいたのか」
「あ、蒼さん。おかえりなさい。お仕事ご苦労様」
庭先で星空を見上げていた由利亜は背後の蒼を振り返った。
「星を……見てたのか?」
「はい。結婚しましたよ〜、って父達に報告してたんです」
「崇さん達……に?」
「ほら、あそこ……見えますか? あれがお父さんで、隣がお母さん。そのそばにあるのがお祖父様。その右はお祖母様……だったらいいな、って勝手な願望ですけどね」
由利亜は星を指さしながら嬉しそうに笑う。
蒼と由利亜は指定期間の残り数日を待たずに、本日付で婚姻届を出した。
思いの通じ合った二人に迷いは無かったから。
「婚姻届、きちんと山名さんに渡してくれましたか?」
「あぁ。確かに渡したよ。由利亜……今更だけど、本当に後悔しないな?」
「しませんよ」
不安げに尋ねる蒼を余所に由利亜は即答した。
「あのね、蒼さん……最愛の人と一緒になれたら、それでもう幸せなんですよ」
「……え?」
由利亜は思い出を懐かしむように遠い目をしていた。
『お母さんはね、大好きなお父さんと……最愛の人と一緒になれたから幸せなのよ。だから由利亜も、いつかそんな人と出会って幸せになりなさい』
(お母さん……わたし、ちゃんと出会えたよ)
不意に思い出された母の声に、由利亜は心の内でそっと語りかける。
「それね、母の口癖だったんですよ。由利亜も最愛の人と幸せになりなさいってね。それも今報告してたところです。素敵な人が見つかりましたよ、って。……そういう蒼さんこそ、後悔しませんか?」
いつの間にか、由利亜は視線を蒼に向け、その表情に悪戯っぽい笑みを浮かべていた。
そんな由利亜に、蒼はフッと笑みを零す。
「するわけ無いだろう? 俺が何年待ったと思ってる? ……由利亜、お前初めて“小夜子”の名前を聞いたのいつだか覚えてるか?」
「確か……手紙のやりとり初めて一年くらいでしたよね? それまでずっと“柚木”って姓しか教えてくれなかったから、わたしが手紙で聞いたんです。そしたら、お返事に“小夜子です”って」
「その“小夜子”の意味、分かるか?」
言われて、由利亜は少し考えた。
しかし、すぐに頭の中である物と小夜子の名前が重なり合う。
「もしかして……小夜曲、ですか?」
――愛する女性を思っています
蒼が何も言わずとも、そんな言葉が由利亜の中で響いた。
「そうだよ。その時からずっと、由利亜のこと待ってたんだ。後悔なんてしようと思ってもできないさ」
蒼はそっと由利亜の肩を抱き寄せる。
二度目のキスは優しくて……そして温かかった。
